電気自動車の航続距離は、これまで多くの消費者にとって購入を躊躇させる大きな要因でした。しかし、2025年10月31日から11月9日まで東京ビッグサイトで開催中のJapan Mobility Show 2025では、その常識が完全に覆されようとしています。700km超の航続距離を誇る新型EVが続々と登場し、国内外の自動車メーカーが技術の粋を結集した次世代モデルを披露しています。かつて「東京モーターショー」として親しまれていたこのイベントが「ジャパンモビリティショー」へと進化したことは、自動車という個別の製品から、より広範な移動のエコシステムへと視点が移行したことを象徴しています。本記事では、Japan Mobility Show 2025で注目を集める新型EVの航続距離を徹底比較し、各メーカーの戦略と技術革新を詳しく解説していきます。ガソリン車からEVへの乗り換えを検討されている方、最新のEV技術に興味をお持ちの方にとって、必見の情報をお届けします。

Japan Mobility Show 2025が示す電動化の新時代
現在開催中のJapan Mobility Show 2025は、日本の自動車産業が電動モビリティへと本格的に舵を切る歴史的な転換点として記憶されることになるでしょう。このショーの中心テーマは「電動化の深化」と「AIを活用した知能化」の融合という二つの巨大な潮流によって定義されています。もはや自動車は単なる移動機械ではなく、知性を備えた社会とつながるインテリジェント・デバイスへと変貌を遂げつつあります。
会場には、トヨタ、日産、ホンダといった国内メーカーだけでなく、BMW、メルセデス・ベンツ、アウディ、ヒョンデといった海外の強豪も集結し、電動化時代の覇権を賭けたグローバルな競争が繰り広げられています。特に注目すべきは、日本メーカーの本気度です。2025年度には、国内メーカーから少なくとも6車種以上の新型EVが市場に投入されると報じられており、これはまさに新型ラッシュと呼ぶにふさわしい状況となっています。
かつて、初代リーフなどでEVの先駆者となった日本勢ですが、航続距離やセグメントの多様性において世界の潮流から一歩遅れを取っているとの見方もありました。しかし、Japan Mobility Show 2025で示されているのは、その評価を完全に覆すほどの力強いコミットメントです。航続距離700km超へと劇的な進化を遂げた新型リーフ、同じく740km超の領域に踏み込んだ改良型bZ4X、そして各社から続々と登場する競争力のある新型車たち。これらは単なるモデルチェンジではなく、クロスオーバー、SUV、軽商用車といった市場のあらゆる需要に応えるべく展開される産業全体を挙げた戦略的な攻勢なのです。
航続距離800kmの頂点に立つ欧州プレミアムブランド
日本のメーカーが本格的な反撃の狼煙を上げる中、欧州、特にドイツのプレミアムブランドは、EVの技術的到達点を遥か高みへと引き上げることでその存在感を誇示しています。彼らが提示する驚異的な航続距離は、2025年以降のEV市場における新たなグローバル・ベンチマークとなっています。
その筆頭が、アウディが放つ空力の傑作「A6 e-tron」です。このモデルが叩き出す数値は、まさに圧巻の一言に尽きます。オプションの「レンジプラスパッケージ」を装着した「A6 Sportback e-tron」は、WLTCモードで最大846kmという、現行の内燃機関車に匹敵あるいは凌駕する航続距離を実現しています。この驚異的な数値を支えるのは、94.9kWhという大容量バッテリーだけではありません。むしろ注目すべきは、その徹底的に突き詰められた効率性にあります。
Cd値(空気抵抗係数)0.21という数値は、アウディ史上最高の空力性能であり、走行中のエネルギー消費を極限まで抑えるための技術的な執念の結晶です。さらに、ポルシェと共同開発したEV専用の「プレミアム・プラットフォーム・エレクトリック(PPE)」の採用により、フラットなフロアを実現しています。これにより、バッテリー搭載スペースの最適化と広大な室内空間という二律背反の要素を両立させています。流麗なクーペスタイルの「Sportback」と実用的なステーションワゴン「Avant」、そして高性能版の「S6」まで揃えた盤石のラインナップは、アウディがこのセグメントを完全に掌握しようとする強い意志の表れです。
一方、メルセデス・ベンツは、ラグジュアリーと長距離性能を両立させる二方面からのアプローチで市場に挑んでいます。新型「CLA EV」は約750kmという卓越した航続距離を達成しています。さらに、その真価は充電性能にあります。最新の急速充電技術により、わずか10分間の充電で最大200km分の航続距離を回復できます。これは、ガソリンスタンドでの給油時間に迫る利便性であり、EVの長距離移動における心理的な障壁を大きく引き下げるものです。そして、人気のミドルサイズSUVセグメントには、最大713kmの航続距離を誇る新型「GLC EV」を投入しています。
これらの欧州勢の動きが示すのは、EV時代の覇権争いが単なるバッテリー容量の大きさ比べから、より高度な次元へと移行したという事実です。大容量バッテリーは前提条件に過ぎません。真の競争領域は、空力性能、パワートレイン効率、熱管理、そしてそれらを統合する専用プラットフォームといった車両全体のシステム効率をいかに突き詰めるかにあります。アウディがCd値を繰り返し強調し、メルセデスが800Vアーキテクチャによる超高速充電をアピールするのは、まさにこのためです。
日産リーフの大胆な再創造と進化
EVのパイオニアである日産は、その象徴たるリーフを大胆に再定義することで電動化戦略の新たな章を開いています。8年ぶりのフルモデルチェンジで登場した新型リーフ(B7型)は、従来のハッチバックという姿を捨て、市場の主流である流麗なクーペクロスオーバーSUVへと生まれ変わりました。このセグメントへの転換は、リーフをニッチな存在から、より幅広いユーザー層にアピールする量販モデルへと昇華させるための戦略的な一手です。
その最大の進化は、航続距離の飛躍的な向上にあります。78kWhの大容量バッテリーを搭載する上位グレード「B7」において、WLTCモードで最大702kmという驚異的な数値を達成しています。これは、もはや日常使いの域を遥かに超え、本格的な長距離ドライブを余裕でこなす性能です。また、55kWhバッテリーを搭載し、航続距離490kmを実現するエントリーグレード「B5」も設定され、ユーザーのニーズに応じた選択肢を提供しています。
この長大な航続距離は、インバーター、モーター、減速機を統合し、従来比で10%の小型化を実現した新開発の電動パワートレイン「3-in-1」や、Cd値0.26まで磨き上げられた空力性能、そしてルートに応じてバッテリー温度を最適化する高度なエネルギーマネジメントシステムといった技術の結晶です。充電性能も向上しており、150kWの急速充電に対応し、78kWhのバッテリーを約35分で10%から80%まで充電可能となっています。
日産の電動化戦略は、ピュアEVだけに留まりません。Japan Mobility Show 2025では、高級ミニバンの新型エルグランドも披露されていますが、こちらには先進のシリーズハイブリッドシステム「第3世代e-POWER」が搭載されています。これは、EVで培った電動駆動技術を活かしつつ、充電インフラに依存しない電動化の選択肢を提供する日産独自のデュアルパス戦略の現れです。さらに、欧州市場向けには、最大航続距離408kmの新型EV「マイクラ」も発表しており、アライアンスによるプラットフォーム共有と地域特性に合わせた開発力を示しています。
トヨタbZ4Xの戦略的進化とメインストリーム市場への挑戦
自動車業界の巨人が、EV市場においてもその支配力を確立すべく本格的な攻勢に転じています。その中核をなすのが、大幅な改良を受けて生まれ変わった「bZ4X」です。
2025年モデルのbZ4Xは、単なる改良ではなく、市場の評価を覆しトップランナーに躍り出るための逆襲と位置づけられています。その象徴が、74.7kWhの大容量バッテリーを搭載したFWDモデルが達成する最大746km(WLTCモード)という驚異的な航続距離です。この数値は、国内メーカーのEVとしては最高水準であり、欧州のプレミアム勢が築いた700km超の領域に真っ向から挑むものとなっています。
トヨタは、このトップエンドモデルだけでなく、より幅広い層にEVを届けるための戦略も周到に準備しています。新たに設定された57.7kWhバッテリーを搭載するエントリーモデルは、それでも544kmという十分な航続距離を確保しています。そして、74.7kWhバッテリーは、AWDモデル(航続距離687km)にも展開されます。
さらに重要なのが価格戦略の見直しです。新型bZ4Xは、エントリーグレードの価格を480万円に設定しています。これは、長距離EVの購入ハードルを劇的に引き下げるものであり、トヨタが持つ圧倒的な生産能力とコスト競争力を背景に、EVの本格的な普及を目指す強い意志の表れと言えます。
一方で、トヨタはBEV(バッテリーEV)への一本化ではなく、多様な選択肢を提供するマルチパスウェイ戦略を堅持しています。そのもう一つの柱が、PHEV(プラグインハイブリッド)です。新型「RAV4 PHEV」は、EVとしての航続距離を従来の95kmから150kmへと大幅に延伸しています。これは、パワートレインに搭載された炭化ケイ素(SiC)半導体による効率向上とバッテリー容量の拡大によって実現されました。この150kmという距離は、多くのユーザーの1日の走行距離をカバーするに十分であり、日常の移動はほぼEVとしてゼロエミッションでこなしつつ、週末の長距離移動ではガソリンエンジンによる安心感を得られます。これは、まだBEVへの完全移行に踏み切れないユーザー層への現実的かつ魅力的な橋渡しとなる戦略です。
レクサスが追求するパフォーマンスと電動化の完璧な融合
トヨタのプレミアムブランドであるレクサスは、電動化時代においても走りの味と上質な体験というブランドの核を追求し続けています。その姿勢は、大幅に刷新されたEV専用モデル「RZ」に色濃く反映されています。
改良新型RZは、BEVシステムの全面的な見直しにより基本性能を徹底的に磨き上げました。その結果、航続距離は大幅に伸長し、FWDモデルの「RZ350e」は575km、AWDモデルの「RZ500e」は500kmを達成し、実用性を大きく向上させています。
しかし、レクサスの真骨頂は単なる航続距離の追求に留まらない点にあります。新たに追加されたハイパフォーマンスモデル「RZ550e F SPORT」は、その象徴です。システム最高出力300kW(407.8PS)を発生する強力なデュアルモーターを搭載し、圧倒的な加速性能を誇ります。そのパフォーマンス志向のため、大径ホイールの装着なども影響し、航続距離は450kmとやや控えめになりますが、これはレクサスが電動化においても多様な価値観に応えようとしている証拠です。
さらに、レクサスは航続距離以外の領域でも革新を続けています。新型RZには、ステアリングホイールとタイヤを機械的に切り離し電気信号で操舵する「ステアバイワイヤシステム」が搭載されています。これにより、よりダイレクトで自然な操舵フィールを実現するとともに、ドライバーに不要な振動を伝えない上質な乗り心地を両立させています。これは、電動化技術を走りの深化へと応用するレクサスの哲学を体現する技術です。また、将来の方向性を示すコンセプトカー「LF-Z Electrified」は、EV専用プラットフォームをベースに航続距離600kmを見据えており、レクサスの電動化に対する長期的なビジョンと野心を示唆しています。
アライアンスを活用したスズキとスバルの挑戦
EV開発には莫大な投資が必要となるため、メーカー間のアライアンス(提携)が成功の鍵を握ります。スズキとスバルは、それぞれのブランド哲学を維持しつつ、トヨタとの協業を通じて競争力のあるEVを市場に投入しています。
スズキにとって初のグローバルBEVとなる新型「e-VITARA」は、極めて戦略的なモデルです。その最大の特徴は、実用性と価格の絶妙なバランスにあります。バッテリーは2種類設定され、49kWh仕様は433km、61kWh仕様は2WDモデルで最大520km、AWDモデルでも472kmという、ファミリーユースに十分な航続距離を確保しています。
注目すべきは、バッテリーにLFP(リン酸鉄リチウムイオン)を採用した点です。LFPバッテリーは、高価なコバルトを使用しないためコストを抑えられる上、安全性や長寿命性に優れるという利点を持ちます。この採用により、e-VITARAは399万円からという戦略的な価格設定を実現し、多くの人々が手に届く実用的なEV SUVというポジションを確立しています。
一方、スバルが投入する新型EV「アンチャーテッド」は、トヨタのC-HR EVと基本骨格を共有する兄弟車であり、トヨタのeTNGAプラットフォームをベースに開発されています。74.7kWhのバッテリーを搭載し、航続距離はFWDモデルで最大約482km、AWDモデルで約467kmを達成します。
このモデルにおいてスバルが最も重視したのは、ブランドのDNAをいかにEVで表現するかという点です。その答えが、長年培ってきた独自のAWD技術をEVに最適化した「シンメトリカルAWD」と、悪路走破性を高める「X-MODE」の搭載です。これにより、アンチャーテッドは単なるシティ派EVではなく、雪道やオフロードでも安心して走れるスバルらしい全天候型の走破性を備えたモデルとなっています。
ホンダが描く多様な電動化ビジョン
ホンダは、単一の方向性ではなく、多様な価値観に応える電動化のビジョンを提示しています。そのアプローチは、走りの楽しさを追求したコンパクトEVから、モビリティの概念そのものを変えようとするインテリジェント・ビークルまで、幅広いスペクトラムに及びます。
Japan Mobility Show 2025で注目を集めているのが、小型EVのプロトタイプ「Super ONE Prototype」です。かつての「シティターボ」を彷彿とさせるこのモデルは、航続距離よりも走りの楽しさを優先した設計思想が貫かれています。推定されるスペックは、最高出力110ps、航続距離約250kmとなっています。これは、長距離移動を目的とするのではなく、都市を俊敏に駆け抜ける喜びや意のままに操る楽しさを提供するためのEVという新たな価値提案です。
その対極に位置するのが、ソニーとの合弁会社ソニー・ホンダモビリティが開発した「AFEELA 1」です。このモデルは、自動車を移動空間からエンターテインメントと知性の空間へと変革することを目指しています。航続距離は約483kmと実用的でありながら、その本質は高度なAI技術、センシング技術、そしてソニーが持つエンターテインメントのノウハウを融合させたこれまでにないユーザー体験にあります。約1400万円というプレミアムな価格設定は、この車が単なる移動手段ではなく最先端技術を体験するためのプラットフォームであることを示しています。
マツダ、三菱、ダイハツの着実な電動化の歩み
主要メーカーの華やかな新型車に加えて、他の国内メーカーも着実に電動化への歩みを進めています。
マツダは、2025年にも米国市場で新型EVを発売する計画を発表しています。これは既存のプラットフォームを活用したSUVモデル、おそらくは「CX-5」ベースになる可能性が高いと見られていますが、現時点で具体的な航続距離などのスペックは明らかにされていません。
三菱自動車は、欧州市場向けに新型「エクリプス クロス EV」を投入しています。ルノーとのアライアンスを通じて開発されたこのモデルは、87kWhの大容量バッテリーを搭載し、約600kmという非常に競争力のある航続距離を実現しています。これは、グローバルなアライアンスがEV開発のスピードとコスト効率をいかに高めるかを示す好例です。
そして、日本の自動車市場で重要な役割を担う軽自動車セグメントの電動化も進んでいます。ダイハツは、商用軽バンEVのコンセプトモデル「e-アトレー」や「e-ハイゼット」を公開しています。これらのモデルでは、長大な航続距離よりも、限られたスペースでの積載性や使い勝手、そして低いランニングコストといった商用車としての本質的な価値が追求されています。
これらの多様な動きから浮かび上がるのは、日本の自動車産業が採用するポートフォリオ戦略です。一部の海外メーカーがBEVへの全面移行を急ぐ中、日本勢はBEV、PHEV、そしてe-POWERのような先進的なハイブリッドといった多様な電動化技術を市場のニーズやインフラの整備状況に合わせて提供する、より現実的でリスクを分散させたアプローチを取っています。
新型EV航続距離ランキング2025の全体像
2025年のEV市場は、航続距離という一つの指標を巡る壮大な競争を繰り広げています。ここでは、各モデルが持つスペックをその背景にある技術や哲学と共に階層的に見ていきます。
800kmクラス:電動グランドツーリングの頂点に君臨するのは、最大航続距離846kmを誇るアウディ「A6 Sportback e-tron」です。この圧倒的な数値は、大容量バッテリー、EV専用プラットフォーム(PPE)、そしてCd値0.21という驚異的な空力性能という技術的なパーフェクトストームによって達成されました。
700kmクラスは、新時代のメインストリーム・ベンチマークとなっています。この最も華やかな舞台で三つ巴の激しい戦いが繰り広げられています。最大746kmを達成したトヨタ「bZ4X」は、驚異的な航続距離を戦略的な価格引き下げによってより多くの人々に提供する現実的なチャンピオンとしてその地位を確立しています。対するメルセデス・ベンツ「CLA EV」は、約750kmという同等の航続距離に、プレミアムなデザイン、最先端のテクノロジー、そしてブランドの威信という付加価値を纏った豪華な長距離ランナーです。同じく713kmの航続距離を持つSUVの「GLC EV」と共に、メルセデスはラグジュアリーセグメントの基準を再定義しています。そして、最大702kmを達成した日産「リーフ」は、EVの代名詞であったその名を背負い、クロスオーバーSUVへと大胆に変身を遂げトップレベルの性能を手に入れた偉大なる再発明者の物語を体現しています。
600km級では、欧州市場で約600kmの航続距離を誇る三菱「エクリプス クロス EV」がスタイリッシュなパッケージで優れた航続距離を提供しています。
500km級は最も競争が激しく市場のボリュームゾーンとなっています。レクサス「RZ350e」(575km)と「RZ500e」(500km)は、十分な航続距離に加えてレクサスならではの上質な乗り心地と洗練された内外装を提供します。スズキ「e-VITARA」の61kWh仕様(520km)は、求めやすい価格と実用性を両立させた賢明な選択肢として際立ちます。そして、トヨタ「bZ4X」(544km)と日産「リーフ」(490km)のエントリーモデルは、最新のプラットフォームがもたらす恩恵をより手頃な価格で享受する機会を提供します。
400-500km級では、スバル「アンチャーテッド」(最大約482km)がAWDによる全天候型の走破性を最大の魅力としています。ソニー・ホンダモビリティ「AFEELA 1」(約483km)はソフトウェアとユーザー体験という新たな価値軸を提示します。レクサス「RZ550e F SPORT」(450km)は航続距離と引き換えに心を昂らせるドライビングダイナミクスを提供します。欧州市場向けの日産「マイクラ」(408km)もこのカテゴリーに含まれます。
400km未満のクラスでは、航続距離の最大化を第一目標としない明確な目的を持ったモデルたちが存在します。ホンダ「Super ONE Prototype」(約250km)は、キロメートルではなく運転の楽しさと都市での俊敏性に価値を置いています。また、ダイハツ「e-アトレー」のような軽商用EVは、長距離性能よりも積載効率や経済性といったビジネスにおける実用性が最優先されています。
長距離性能を支える革新的な技術群
2025年のEVが実現した航続距離の飛躍的な向上は、単にバッテリーを大きくした結果ではありません。その背後には、バッテリー材料、プラットフォーム設計、システム効率、そして充電技術という多岐にわたる領域での地道かつ革新的な技術開発が存在します。
バッテリー技術の進化において、現在のEV革命を支えるリチウムイオンバッテリーはその内部構成において進化を続けています。その一つが、スズキ「e-VITARA」などが採用するLFP(リン酸鉄リチウムイオン)バッテリーの台頭です。従来のNMC(ニッケル・マンガン・コバルト)系バッテリーに比べてエネルギー密度では一歩譲るものの、コストが低く熱安定性が高いため安全で充放電サイクル寿命が長いという大きな利点を持ちます。これによりより手頃な価格で長く安心して使えるEVの実現が可能になります。
そして、その先に見据えるのが次世代バッテリーの本命と目される全固体電池です。電解質を液体から固体に変えることで、エネルギー密度、充電速度、安全性を飛躍的に向上させる可能性を秘めています。2025年は、この全固体電池が研究開発フェーズから社会実装フェーズへと移行する転換点と位置づけられています。ホンダ、日産、出光興産などがパイロットラインの構築に着手し、トヨタは2027年から2028年の実用化を目指しています。全固体電池の量産化が実現すれば、EVの航続距離は更なる新次元へと突入するでしょう。
プラットフォームの重要性も見逃せません。航続距離を決定づけるもう一つの重要な要素は、車両の基本骨格であるプラットフォームです。アウディのPPEやトヨタのeTNGAのようなゼロからEVとして設計された専用プラットフォームは、内燃機関車のプラットフォームを流用したものに比べて決定的な優位性を持ちます。床下にバッテリーを効率的に、かつ構造体の一部として組み込むことができるため、低重心化による走行性能の向上、より大きなバッテリーの搭載、そしてフラットな床面による広大な室内空間の実現が可能になります。
システム効率の徹底追求において、長い航続距離はエネルギーを多く積むことだけでなく賢く使うことによってもたらされます。第一に空力性能です。アウディ「A6 e-tron」のCd値0.21や日産新型「リーフ」のCd値0.26という数値が示すように、ボディ形状、フラットな床下、格納式ドアハンドルなど空気抵抗をわずかでも減らすための設計が、特に高速走行時のエネルギー消費を劇的に削減します。
第二にパワートレインの小型化と統合です。日産の「3-in-1」e-Axleやスズキの統合型「E-Axle」のように、モーター、インバーター、減速機を一つのコンパクトなユニットにまとめることで重量とサイズを削減し部品間のエネルギー伝達ロスを低減することができます。
第三に先進的な半導体の採用です。トヨタが「RAV4 PHEV」のパワーコントロールユニットに炭化ケイ素(SiC)半導体を採用したのが好例です。SiCは従来のシリコン半導体に比べて高電圧・高周波での電力損失が少なくより小型で高効率な電力変換を可能にします。これはパワートレイン全体の効率を底上げする重要な技術です。
充電技術の進化も見逃せません。EVの利便性は航続距離だけでなく充電性能にも大きく依存します。2025年には150kW以上の急速充電が新たな標準となりつつあります。さらにその先を見据え、ヒョンデはJapan Mobility Showの会場で最大出力350kWを誇る次世代の超急速充電器「SERA-400」を展示しています。このようなインフラの進化は充電時間を劇的に短縮しEVの利便性をガソリン車に近づけるでしょう。
また、ハードウェアだけでなくソフトウェアも重要です。改良型「bZ4X」やスバル「アンチャーテッド」に搭載される「バッテリープレコンディショニング」機能は、急速充電を開始する前にバッテリーを最適な温度に調整することで特に気温の低い冬場などでも安定して高速な充電を可能にします。
新たな電動化の地平を航行するために
Japan Mobility Show 2025が描き出す未来は、電動化がもはや特別な選択肢ではなく自動車の新たな常識となる時代の到来です。航続距離700kmが現実的なベンチマークとなり、日本と欧州のメーカーが技術の粋を尽くして覇を競い、市場には多様なニーズに応える様々なEVが溢れかえっています。この劇的な変化は、バッテリー技術の進化、専用プラットフォームの普及、そしてシステム効率の飽くなき追求という揺るぎない技術的基盤の上に成り立っています。
しかし、これからEVを選ぶユーザーにとって、カタログに記載された航続距離という一つの数字が全てではないことを理解することが重要です。その数字の裏側にある電費(Wh/kmやkm/kWh)、すなわち1km走行するのにどれだけの電力を消費するかという効率こそが実際のランニングコストを左右します。そして、充電速度は長距離移動の快適性と時間的価値を決定づけます。航続距離がわずかに短くても圧倒的に速く充電できる車の方が結果的に実用性が高いというケースも十分にあり得るのです。
2025年は、EVが本格的な普及期へと突入する重要な節目です。そしてその先には、全固体電池の実用化や超高速充電インフラの拡充といったさらなる技術革新が待ち受けています。我々が今目にしているのは、まだ壮大な変革の序章に過ぎません。Japan Mobility Show 2025は、その先の未来への期待と興奮を掻き立てる新たな電動化の地平線を示しています。電気自動車の時代は、もはや未来の話ではなく現在進行形の現実となりました。この歴史的な転換点を目撃できる私たちは、次世代のモビリティ革命の最前線に立っているのです。

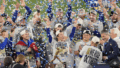

コメント