2025年6月に成立した年金制度改正法により、厚生年金保険の標準報酬月額の上限が大きく変わることになりました。現在65万円となっている上限が、2027年9月から段階的に引き上げられ、最終的に2029年9月には75万円に達します。この改正は、高所得者層を中心に保険料負担に影響を及ぼすため、会社員として働く方々や企業の人事担当者にとって重要な変更となります。特に報酬月額が66万5千円以上の方は、具体的にいつから保険料が変わるのか、どのくらい負担が増えるのか、そして将来の年金額にどう影響するのかについて正確に理解しておく必要があります。また、企業側も従業員への説明責任や給与計算システムの更新、人件費予算の見直しなど、施行時期までに準備すべき事項が多くあります。本記事では、厚生年金の標準報酬月額上限75万円への引上げについて、施行時期を中心に詳しく解説していきます。

標準報酬月額の上限引上げはいつから実施されるのか
厚生年金保険における標準報酬月額の上限引上げは、2027年9月から開始されます。ただし、一度に75万円まで引き上げられるわけではなく、3年間をかけて段階的に実施される仕組みとなっています。この段階的なアプローチは、対象者や企業への影響を緩和し、準備期間を確保するための配慮と言えます。
第1段階として2027年9月に実施される改定では、現行の65万円から68万円へと引き上げられます。この時点で、厚生年金の等級表に第33等級が新設されることになります。続いて第2段階は2028年9月に行われ、上限が68万円から71万円へと引き上げられ、第34等級が追加されます。そして最終的な第3段階として2029年9月に、上限が71万円から75万円へと引き上げられ、第35等級が新設されることで、3年間にわたる段階的な引上げが完了します。
このスケジュールによって、対象となる高所得者層は毎年少しずつ保険料負担が増えていくことになりますが、急激な負担増を避けることができます。また、企業側にとっても、給与計算システムの段階的な更新や予算計画の調整がしやすくなるというメリットがあります。
法律の成立から施行までの経緯
標準報酬月額の上限引上げを含む年金制度改正法は、正式には「社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律案」という名称で、2025年5月16日に第217回通常国会に提出されました。その後、国会での審議を経て、衆議院での一部修正を加えられた上で、2025年6月13日に成立し、同年6月20日に公布されました。
法律が成立・公布されてから実際の施行まで約2年の準備期間が設けられているのは、この改正が社会保険料の負担に関わる重要な変更であるためです。企業は給与計算システムの更新や従業員への周知、予算の見直しなどを行う必要があり、また対象となる個人も将来の家計計画を見直す時間が必要です。こうした準備期間を十分に確保することで、スムーズな制度移行を実現しようという意図があります。
実際の保険料への反映は、2027年9月分の保険料からとなります。多くの企業では、当月分の保険料を翌月の給与から天引きする仕組みをとっているため、実際に給与明細に変更が反映されるのは2027年10月支給の給与からとなるケースが多いでしょう。ただし、企業によって給与の締め日や支払日が異なるため、具体的なタイミングは各自の勤務先で確認することが重要です。
どのような人が対象になるのか
今回の標準報酬月額の上限引上げは、厚生年金に加入しているすべての人に影響するわけではありません。対象となるのは、報酬月額が66万5千円以上の高所得者層に限定されます。この金額は、賞与を除いた月々の給与が基準となっており、年収ベースでは約798万円以上の方が該当します。ボーナスを含めた年収で考えると、おおむね1000万円を超える方が対象となる可能性が高いと言えます。
現在の統計データによると、厚生年金加入者全体のうち、標準報酬月額の上限である65万円に該当する方は約6.2パーセントです。男性被保険者に限定すると約9.6パーセント、人数にして約243万人が該当するとされています。つまり、大多数の厚生年金加入者にとっては、今回の改正による保険料負担の変更は発生しないということになります。
重要な点として、報酬月額が66万5千円未満の方については、今回の改正による厚生年金保険料の負担増は一切ありません。この点は誤解されやすいため注意が必要です。上限引上げの影響を受けるのは、現在すでに標準報酬月額の上限に到達している高所得者層のみであり、それ以外の方々の保険料は現行のまま変わりません。
対象となる方々の職業や立場は様々です。大企業の管理職や役員、医師や弁護士などの専門職、外資系企業の従業員、成果報酬型の営業職で高い成果を上げている方などが典型的な例として挙げられます。また、複数の企業で厚生年金に加入している場合、それらの報酬を合算した額が基準となるため、副業による収入も含めて判断する必要があります。
保険料負担はどのくらい増えるのか
標準報酬月額の上限が75万円まで引き上げられることで、対象者の保険料負担は増加することになります。具体的な金額を2025年度の保険料率を基準に計算すると、賃金などが月75万円以上の方の場合、厚生年金保険料の本人負担分は月9100円増加します。これは年額にすると約10万9800円の負担増となります。
ただし、社会保険料は所得税や住民税を計算する際に所得から控除される仕組みとなっているため、税負担が軽減される効果があります。この社会保険料控除による所得税・住民税の減少を考慮すると、実質的な負担増は月約6100円、年額では約7万3200円程度となります。このように、名目上の保険料増加額と実質的な手取り減少額には差があることを理解しておくことが重要です。
現在、最も高い区分での厚生年金保険料の自己負担額は月5万9475円となっています。これは標準報酬月額65万円に対して、2025年度の保険料率18.3パーセントを適用し、労使折半で半分を本人が負担する計算によるものです。見直し後の最終的な上限での保険料は、標準報酬月額75万円で計算すると月6万8625円となります。
段階的な引上げに伴い、保険料負担も段階的に増加していきます。2027年9月時点で上限が68万円となった際には、月約4575円の負担増となります。その後、2028年9月に上限が71万円になると、さらに追加の負担増が発生し、最終的に2029年9月に上限75万円に到達した時点で、現行と比較して月約9100円の負担増となる計算です。
社会保険料は労使折半の仕組みとなっているため、従業員本人の負担が増える分、事業主側も同額を負担することになります。つまり、標準報酬月額75万円の従業員を雇用している企業は、従業員1人あたり月9100円、年額約10万9800円の追加負担が発生することになります。高所得者層を多く雇用している企業では、この影響が人件費に大きく反映される可能性があります。
将来受け取る年金額への影響
保険料負担が増える一方で、将来受け取る年金額も増加します。この点は、今回の改正を評価する上で非常に重要なポイントとなります。標準報酬月額75万円の状態が10年間続いた場合、月約5100円増額した年金を一生涯受け取ることができます。税金を考慮すると、実質的には月約4300円の年金増額となります。
年額で考えると、約6万1200円の年金増額となり、税引後では約5万1600円の増額です。この増額された年金は、65歳から受給を開始した場合、その後一生涯にわたって受け取り続けることができます。平均寿命まで生きた場合の受取総額を考えると、かなり大きな金額になることが分かります。
保険料の追加負担と年金の増額を単純に比較すると、年金受給開始後、おおむね18年から20年程度で保険料として支払った金額の元が取れる計算になります。65歳から年金受給を開始した場合、83歳から85歳頃には損益分岐点に達することになります。現在の平均寿命を考えると、多くの方がこの年齢を超えて生きる可能性が高いため、長期的には保険料負担増に見合った給付が得られると言えます。
ただし、この計算は物価上昇率、賃金上昇率、保険料率の変動などを考慮しない単純な試算であることに注意が必要です。実際には、年金額はマクロ経済スライドなどの仕組みによって調整されますし、保険料率も将来変更される可能性があります。また、遺族年金の額にも影響するため、単純に個人の損得だけで判断できない側面もあります。
なぜ上限が引き上げられるのか
標準報酬月額の上限が引き上げられる背景には、複数の理由があります。最も大きな理由の一つは、近年の賃金上昇への対応です。日本では長年デフレや賃金の停滞が続いていましたが、近年は徐々に賃金が上昇傾向にあります。特に高所得者層の報酬は大きく伸びており、現在の上限である65万円では実態に合わなくなってきているという状況があります。
厚生年金制度には、もともと上限を見直すための仕組みが組み込まれています。具体的には、全被保険者の標準報酬月額の平均の2倍が、現行の上限を超える状態が続くと、政令で新しい等級を追加することができるというルールです。実際、賃金の上昇により、この条件を満たす状況となっており、制度上のルールに従った見直しが行われることになりました。
もう一つの重要な理由は、分布の偏り解消です。現行制度では、標準報酬月額の上限である65万円の第32等級に、厚生年金被保険者の6.2パーセントが集中しています。本来であれば、報酬月額に応じてより細かく等級が分かれるべきところ、上限があるために一つの等級に多くの人が集まっている状態です。この偏りを解消し、より実態に即した標準報酬月額を設定することが求められています。
制度の公平性確保も大きな目的の一つです。賃金などが月65万円を超える方に、その収入に応じた保険料を負担していただくことで、負担の公平性を高めます。現行制度では、月収70万円の人も100万円の人も、同じ65万円の上限が適用されるため、収入に対する保険料負担率が異なってしまいます。上限を引き上げることで、より収入に見合った保険料負担となり、公平性が向上します。同時に、現役時代の収入に見合った年金を受け取れるようにすることで、給付面での公平性も向上します。
さらに、高所得者層からの保険料収入を増やすことで、年金財政の持続可能性を高める効果も期待されています。ただし、これは副次的な効果であり、主目的は上記の公平性の確保にあります。政府の試算によれば、今回の上限引上げにより、年間で数百億円規模の保険料収入増が見込まれています。
健康保険との違いについて
厚生年金保険と健康保険では、標準報酬月額の上限が大きく異なります。健康保険の場合、協会けんぽの標準報酬月額の上限は139万円となっています。これは報酬月額が135万5千円以上の方が該当する金額です。一方、厚生年金保険の標準報酬月額の上限は現行65万円であり、今回の改正後も75万円にとどまります。
このように大きな違いがあるのは、それぞれの制度の性質が異なるためです。健康保険の場合、医療費の実費を保険でカバーするという性質上、高所得者でも医療費が極端に高額になる可能性があります。特に長期入院や高度な医療を受けた場合、医療費は数百万円から数千万円に達することもあります。そのため、より高い上限が設定されているのです。
一方、年金の場合は、給付額の格差を一定範囲に抑えるという考え方があります。もし上限を設けなければ、高所得者と低所得者の間で、年金額に極端な差が生まれてしまいます。年金制度には所得再分配機能も含まれているため、過度な格差を防ぐという観点から、健康保険よりも低い上限が設定されているのです。
今回の改正により、厚生年金保険の上限は75万円となりますが、それでも健康保険の上限である139万円とは大きな開きがあります。この違いを理解しておくことで、給与明細を見た際に、健康保険料と厚生年金保険料の計算基準が異なることが分かります。
介護保険料への影響
40歳以上65歳未満の方は、健康保険料に加えて介護保険料も負担しています。介護保険料も標準報酬月額をベースに計算されるため、標準報酬月額の上限引上げの影響を受けます。2025年度の介護保険料率は全国一律で1.59パーセントです。
標準報酬月額が65万円から75万円に上がった場合、介護保険料の本人負担分は月795円増加します。現行の標準報酬月額65万円では、介護保険料の本人負担は月5168円ですが、標準報酬月額75万円では月5963円となります。この増加額は、年額では約9540円となります。
厚生年金保険料の増加と比較すると、介護保険料の増加額は比較的小さいですが、それでも無視できない金額です。ただし、介護保険料率は毎年見直されるため、実際の金額は将来の保険料率によって変動します。近年、高齢化の進展に伴い介護保険料率は上昇傾向にあるため、標準報酬月額の上限引上げと保険料率の上昇が重なることで、介護保険料の負担増はさらに大きくなる可能性があります。
企業が準備すべきこと
標準報酬月額の上限引上げは、対象となる従業員を雇用する企業にも影響を及ぼします。社会保険料は労使折半のため、従業員の保険料負担が増える分、企業の負担も同額増加します。標準報酬月額75万円の従業員1人あたり、企業負担も月9100円、年額約10万9800円増加することになります。
企業が準備すべき事項として、まず従業員への説明が挙げられます。上限引上げを知らない従業員が給与明細を見て驚くケースも考えられます。企業としては、対象従業員に対して事前に説明を行うことが望ましいでしょう。特に、2027年9月の給与計算から変更となるため、同年8月頃までには周知を完了させる必要があります。説明資料には、具体的な金額や施行時期、将来の年金額への影響なども含めることで、従業員の理解を深めることができます。
給与計算システムの更新も重要な準備事項です。給与計算システムが標準報酬月額の上限変更に対応できるよう、システムの更新が必要です。クラウド型のシステムを利用している場合は自動的に更新される可能性が高いですが、独自システムを使用している場合は、ベンダーとの調整が必要です。システム更新には時間がかかることもあるため、早めの対応が求められます。
対象従業員が多い企業では、社会保険料の予算見直しも必要になります。社会保険料負担の増加が経営に一定の影響を及ぼす可能性があるため、人件費予算の見直しや、中長期的な人件費計画の調整が必要になるでしょう。特に、高所得者層を多く雇用している大企業や専門職の多い企業では、影響額が大きくなる可能性があります。
標準報酬月額の上限引上げにより、高所得者層の手取り額が減少します。これが従業員のモチベーションに影響する可能性もあるため、報酬体系や福利厚生の見直しを検討する企業も出てくるかもしれません。例えば、保険料負担増を考慮した基本給の調整や、手当の新設、福利厚生の充実などが選択肢として考えられます。
標準報酬月額の決定方法
標準報酬月額は、いくつかのタイミングで決定や改定が行われます。まず、資格取得時決定は、新たに厚生年金に加入する際に行われます。新入社員が入社したときや、パート従業員が条件を満たして加入するときがこれに該当します。資格取得時の報酬を月額に換算して、標準報酬月額が決定されます。
定時決定は、毎年1回、定期的に標準報酬月額を見直す手続きです。これは算定基礎届とも呼ばれ、7月1日時点で厚生年金に加入しているすべての被保険者が対象となります。4月、5月、6月の3か月間に支払われた報酬の平均額を算出し、その金額に基づいて9月から翌年8月までの標準報酬月額が決定されます。事業主は、毎年7月10日までに算定基礎届を年金事務所または事務センターに提出する必要があります。
随時改定は、定時決定で決まった標準報酬月額が、年度途中に大きな報酬の変動があった場合に改定される仕組みです。随時改定が行われる条件は、固定的賃金の変動があったこと、変動月から継続した3か月間の報酬の平均額と現在の標準報酬月額との間に2等級以上の差があること、変動月以降の3か月とも支払基礎日数が17日以上であることの3つをすべて満たす場合です。
2027年9月に標準報酬月額の上限が引き上げられた場合、既に上限に達している方については、その時点で新しい等級が適用される見込みです。その後の定時決定や随時改定のタイミングで、正式に新しい標準報酬月額が決定されることになります。
在職老齢年金制度との関係
今回の標準報酬月額の上限引上げと同時に、在職老齢年金制度についても見直しが行われています。在職老齢年金制度とは、60歳以降も働きながら厚生年金を受給する場合、報酬と年金額の合計が一定額を超えると、年金の一部または全部が支給停止となる制度です。この制度は、働く意欲のある高齢者の就労を阻害する要因として、長年にわたり見直しが求められてきました。
2025年の年金制度改正法では、在職老齢年金の基準額が50万円から62万円に引き上げられました。これにより、月収と年金月額の合計が62万円までは、年金が全額支給されることになります。以前は50万円を超えると年金が減額されていたため、大幅な改善と言えます。
標準報酬月額の上限引上げと在職老齢年金の基準額引上げは、いずれも同じ年金制度改正法に含まれています。これらは、働き方の多様化への対応、高所得者層の公平な負担、制度の持続可能性と公平性のバランスといった共通の目的を持っています。より多くの人が長く働き、保険料を納付し続けることで、年金制度の持続可能性が高まります。一方で、働くことによる年金減額を緩和することで、就労インセンティブを維持します。
在職老齢年金の対象となる高齢の従業員を雇用している企業は、標準報酬月額の上限引上げと在職老齢年金の基準額引上げの両方を理解しておく必要があります。特に、60歳以上の従業員については、報酬月額が66万5千円以上の場合、厚生年金保険料が増加する一方、年金の支給停止基準が緩和されるため、手取り収入への影響を個別に試算して説明することが望ましいでしょう。
過去の上限変更の歴史と今後の見通し
標準報酬月額の上限は、過去にも何度か変更されています。主な変更としては、2006年7月に上限が62万円となり、その後2010年9月に上限が65万円に引き上げられました。最後の変更から17年が経過しており、今回の75万円への引上げは、久々の大きな見直しとなります。
この間、平均賃金は緩やかに上昇し、特に高所得者層の報酬は大きく伸びました。その結果、上限である65万円の等級に多くの被保険者が集中する状況が生まれ、今回の改正につながりました。今回の改正により、2029年9月に標準報酬月額の上限は75万円となりますが、これで終わりというわけではありません。
将来的な見直しの可能性は十分にあります。賃金水準は今後も変動すると予想されます。インフレや経済成長により賃金が上昇すれば、再び上限の見直しが必要になる可能性があります。制度上、全被保険者の標準報酬月額の平均の2倍が現行の上限を超える状態が続けば、新しい等級を追加できる仕組みになっています。将来、この条件を満たせば、さらなる上限引上げが検討されるでしょう。
一部の専門家からは、標準報酬月額の上限を賃金上昇に応じて自動的に調整する仕組みの導入を求める声もあります。そうすることで、今回のように大きな時間を空けて改正を行うのではなく、より機動的に制度を調整できるというメリットがあります。ただし、自動調整メカニズムの導入には、制度設計や国会での審議など、多くの課題があります。今後の年金制度改革の議論の中で、この点についても検討される可能性があります。
具体的な計算例で理解する
実際の数字を使って、保険料負担の変化を計算してみましょう。ここでは、東京都在住で協会けんぽに加入している45歳の方を例に、2025年度の保険料率を使用して計算します。厚生年金保険料率は18.3パーセント、健康保険料率は9.98パーセント、介護保険料率は1.59パーセントです。
報酬月額70万円の方の場合、現行制度では上限65万円が適用されます。厚生年金保険料の本人負担は月5万9475円、健康保険料の本人負担は月3万2435円、介護保険料の本人負担は月5168円で、合計9万7078円となります。改正後の2029年9月以降は、実際の報酬月額70万円が標準報酬月額となります。厚生年金保険料の本人負担は月6万4050円、健康保険料の本人負担は月3万4930円、介護保険料の本人負担は月5565円で、合計10万4545円となります。増加額は月7467円、年額では8万9604円です。
報酬月額100万円の方の場合、現行制度では上限65万円が適用されるため、厚生年金保険料の本人負担は月5万9475円です。健康保険料は実際の報酬月額で計算されるため月4万9900円、介護保険料も同様に月7950円で、合計11万7325円となります。改正後は、報酬月額が100万円でも厚生年金の標準報酬月額は上限の75万円が適用されます。厚生年金保険料の本人負担は月6万8625円、健康保険料と介護保険料は変更なしで、合計12万6475円となります。増加額は月9150円、年額では10万9800円です。
このケースでは、報酬月額が100万円ありますが、厚生年金の標準報酬月額は上限の75万円までしか反映されないため、増加額は一定額にとどまります。このように、超高所得者層にとっては、上限があることで保険料負担が抑えられる効果があります。
国際比較から見た日本の制度
日本の年金制度における標準報酬月額の上限を、他国の制度と比較すると、興味深い違いが見えてきます。アメリカの社会保障制度では、課税対象となる所得に上限があります。2025年時点で、年間約16万8600ドル、日本円で約2500万円までの所得が課税対象となっています。この金額は毎年、賃金上昇に応じて調整されます。
ドイツの年金保険では、東西で異なる上限が設定されています。2025年時点で、西部地域では月7600ユーロ、日本円で約126万円、東部地域では月7450ユーロ、約124万円が上限となっています。イギリスの国民保険では、所得に応じて保険料率が段階的に変わる仕組みになっていますが、日本のような明確な上限は設定されていません。
日本の上限である改正後の75万円は、国際的に見ると中程度のレベルと言えます。ただし、年金制度の仕組みや給付水準が国によって大きく異なるため、単純な比較は難しい面もあります。各国の年金制度は、その国の社会保障政策や税制、労働市場の状況などを反映して設計されているため、上限の高低だけで制度の優劣を判断することはできません。
よくある疑問と回答
標準報酬月額の上限引上げについて、多くの方が疑問に思う点について解説します。まず、自分の保険料が本当に上がるのかという疑問ですが、報酬月額が66万5千円未満の方は保険料の変更はありません。66万5千円以上の方のみが対象となります。
いつから給与に反映されるのかについては、2027年9月分の保険料、つまり10月納付分から反映される見込みです。給与から天引きされるタイミングは、企業の給与支払日によって異なります。パートタイマーやアルバイトも対象になるのかという疑問については、雇用形態に関わらず、報酬月額が66万5千円以上であれば対象となりますが、この金額に達するパートタイマーやアルバイトは極めて稀です。
既に退職して年金を受給している場合については、この改正によって年金額が変更されることはありません。ただし、在職中の保険料納付実績に応じて、既に決定された年金額に反映されています。副業による収入も含まれるのかという疑問については、副業先でも厚生年金に加入している場合、本業と副業の報酬を合算した額が標準報酬月額となります。合算後の額が66万5千円以上であれば、今回の改正の影響を受けます。
賞与の標準賞与額の上限も変わるのかについては、賞与の標準賞与額の上限である1回あたり150万円は、今回の改正では変更されません。変更されるのは、毎月の給与をベースとした標準報酬月額の上限のみです。健康保険料も一緒に上がるのかについては、健康保険料はそれぞれの報酬月額に応じて計算されます。報酬月額が70万円以上の方の場合、厚生年金の標準報酬月額が上がっても、健康保険の標準報酬月額は実際の報酬月額で計算されるため、厚生年金ほどの影響はありません。
専門家からのアドバイス
社会保険労務士などの専門家は、今回の改正について様々なアドバイスをしています。高所得者層の方々に対しては、報酬月額が66万5千円以上の場合、将来的に保険料負担が増加することを理解し、ライフプランニングを行う際にこの変更を織り込んで老後資金の計画を立てることが重要だとアドバイスしています。ただし、将来受け取る年金額も増えるため、長期的には必ずしも損とは言えません。
また、個人型確定拠出年金であるiDeCoや、つみたてNISAなどの税制優遇制度を活用した資産形成も併せて検討することで、老後資金の準備をより効果的に進められます。厚生年金だけに頼るのではなく、多様な資産形成手段を組み合わせることが推奨されています。
企業に対しては、対象従業員を雇用する場合、人件費の増加を見込んだ予算計画が必要だとアドバイスされています。また、従業員への適切な説明を行うことで、給与明細を見た際の混乱や問い合わせを減らすことができます。給与計算システムの更新については、ベンダーとの早めの調整が推奨されます。特に、独自システムを使用している企業は、システム改修に時間がかかる可能性があるため、早期の対応が求められます。
人事・総務担当者に対しては、制度改正の内容を正確に理解し、対象従業員の洗い出しを早めに行うことが重要だとアドバイスされています。また、経営層への報告や予算調整の提案も必要になるでしょう。従業員向けの説明資料を準備する際は、具体的な数字を示すことで、変更内容をわかりやすく伝えることができます。
厚生年金保険における標準報酬月額の上限は、2027年9月から段階的に引き上げられ、2029年9月に最終的に75万円となります。この改正は、2025年6月に成立した年金制度改正法に基づくものであり、対象となるのは報酬月額66万5千円以上の高所得者層のみです。それ以外の方には保険料負担の変更はありません。対象者の保険料負担は最終的に月約9100円増加しますが、将来受け取る年金額も月約5100円増加します。企業にとっても対応が必要な重要な改正であり、施行時期までに十分な準備を行うことが求められます。

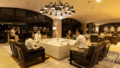
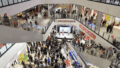
コメント