2026年秋、JR東日本と株式会社パスモ、PASMO協議会の3者が共同で提供を開始する新コード決済サービス「teppay(テッペイ)」は、モバイルSuicaおよびモバイルPASMOアプリに統合される形で展開されます。teppayの最大の特徴は、従来のSuicaやPASMOが抱えていた「2万円のチャージ上限」という制約を突破し、最大30万円までの決済が可能になる点です。また、JCBが提供する決済スキーム「Smart Code」を採用することで、サービス開始時点から全国160万か所以上の加盟店で利用できます。さらに、ユーザー間での送金機能やオンライン決済に対応した「teppay JCBプリカ」の発行も可能となり、単なる決済手段にとどまらない総合的な金融サービスへと進化します。teppayという名称には「Travel(旅)」「Easy(簡単)」「Partnership(連携)」という3つの理念が込められており、鉄道利用者の日常生活から旅行シーンまでをシームレスにカバーする新しい決済体験を提供することを目指しています。本記事では、2025年11月25日に発表されたteppayのサービス内容について、その詳細な機能や特徴、展開スケジュール、競合サービスとの比較などを網羅的に解説します。

- teppayとは何か JR東日本が仕掛ける新時代のコード決済サービス
- teppayの具体的なサービス内容と機能詳細
- teppay JCBプリカによるオンライン決済への対応
- Smart Code採用による全国160万か所以上での即時利用開始
- 地域限定バリュー「バリチケ」による地方創生への貢献
- teppayポイントによる還元プログラム
- SuicaとPASMOの歴史的提携がもたらす意味
- 競合するコード決済サービスとの比較分析
- MaaS戦略における決済機能の重要性
- FeliCa技術とQRコード決済の共存
- キャッシュレス疲れへの処方箋としてのteppay
- セキュリティ対策と安全性への配慮
- teppayの収益モデルとビジネス戦略
- 将来展望と鉄道ペイの全国展開可能性
- teppayサービス開始までのスケジュール
- まとめ teppayがもたらす決済体験の変革
teppayとは何か JR東日本が仕掛ける新時代のコード決済サービス
teppay(テッペイ)は、JR東日本、株式会社パスモ、およびPASMO協議会が2025年11月25日に発表した新しいコード決済サービスです。このサービスは2026年秋にモバイルSuicaアプリから先行して提供が開始され、2027年春にはモバイルPASMOアプリにも対応する予定となっています。teppayという名称は単なる造語ではなく、JR東日本が掲げる3つの重要な理念を象徴しています。「Travel」は移動や旅を軸とした利便性の向上を意味し、駅構内だけでなく旅行中のあらゆる消費シーンをカバーすることを目指しています。「Easy」は幅広い年齢層が直感的に操作できることを示しており、既存の交通系アプリのユーザーインターフェースを踏襲することで学習コストを最小限に抑えています。「Partnership」は私鉄各社やPASMO、JCBなどの他社との連携を通じて、排他的ではないオープンな経済圏を構築する姿勢を表しています。
teppayの最も革新的な点は、独立した新しいアプリを提供するのではなく、既存のモバイルSuicaおよびモバイルPASMOアプリに機能を統合するという設計思想にあります。ユーザーは新たなアプリをダウンロードしたり、煩雑な会員登録を最初から行ったりする必要がありません。アプリのアップデートを行うだけで、トップ画面に新しく設置される「teppayボタン」を通じて、即座にコード決済機能にアクセスできるようになります。この設計は昨今のアプリ市場で問題視されている「アプリ疲労」を深く理解したものであり、ユーザーがこれ以上ホーム画面に新しい決済アプリを追加したくないという心理に配慮しています。日常的に最も起動頻度の高い交通系アプリの中に決済機能を埋め込むことで、既存のアクティブユーザー率を維持したまま、自然な形で新サービスへと誘導することが可能になっています。
teppayの具体的なサービス内容と機能詳細
teppayが提供する機能は多岐にわたりますが、その中核となるのは従来の交通系ICカードの制約を解消する革新的な決済システムです。従来のSuicaやPASMOはFeliCa技術を基盤としたプリペイド型電子マネーであり、チャージ上限額が2万円に設定されていました。この「2万円の壁」は鉄道運賃の精算を主目的として設計された結果であり、高額な買い物や食事、サブスクリプションサービスの決済には不向きでした。teppayではこの問題を解決するため、交通系IC残高とは別にサーバー管理型の「teppay残高」を新たに設ける仕組みを採用しています。このteppay残高の上限額は30万円に設定される見込みであり、従来の15倍もの金額を取り扱えるようになります。
teppayにおける資金の入金方法は複数用意されています。まず銀行口座連携機能により、アプリに登録した銀行口座から直接teppay残高へチャージすることが可能です。また、セブン銀行ATMなどを利用した現金チャージにも対応しています。さらにJR東日本グループのクレジットカードであるビューカードを登録することで、残高不足時でもチャージ不要で決済できる機能の提供が予定されています。出金や資金移動についても柔軟な設計がなされており、teppay残高からモバイルSuicaやモバイルPASMOの交通系IC残高へチャージすることができます。この機能により、例えば親が銀行口座からteppayに入金し、それを子供のモバイルSuicaへ送ることで通学定期券や交通費に充てるという「デジタル小遣い」のような使い方が実現します。加えて、teppayユーザー間での残高の送受金も可能となっており、SuicaユーザーとPASMOユーザーの間でもアプリを跨いだ送金ができる画期的な機能が提供されます。
ただし、いくつかの制約事項も存在します。交通系IC残高からteppay残高への資金移動はできません。また、teppay残高を銀行口座へ出金して現金化することも不可とされています。これは資金決済法上の「前払式支払手段」としての運用を想定しているためと考えられ、本人確認のレベルやマネーロンダリング対策のコストバランスを考慮した結果と推測されます。
teppay JCBプリカによるオンライン決済への対応
teppayの機能は実店舗での決済に留まりません。アプリ内で「teppay JCBプリカ」を発行することが可能となっています。これはバーチャルカードという形態であり、物理的なプラスチックカードは発行されずカード番号のみが発行されます。このバーチャルカードを利用することで、JCB加盟店であるECサイトでの支払いにteppay残高を使用できるようになります。対応するECサイトにはAmazonや楽天をはじめとする大手ショッピングサイトや、各種サブスクリプションサービスなどが含まれます。
この機能は特にクレジットカードを持たない学生や、オンラインショッピングでカード情報を入力することに抵抗を感じる層にとって大きなメリットをもたらします。鉄道利用で日常的に馴染みのあるアプリを通じてネットショッピングができるようになることで、EC決済市場への新たな参入路が開かれます。JCBの加盟店網は国内のみならず海外にも広がっているため、海外のオンラインサービスでも利用できる可能性があります。
Smart Code採用による全国160万か所以上での即時利用開始
後発のコード決済サービスにとって最大の障壁となるのは加盟店の開拓です。PayPayが数年をかけて築き上げた数百万規模の加盟店網に、短期間で追いつくことは現実的に困難です。この課題に対してteppayは戦略的な解決策を講じています。具体的には、株式会社ジェーシービーが提供する決済スキーム「Smart Code」を採用することで、サービス開始と同時に全国規模での利用を可能としています。
Smart Codeは、JCBが決済事業者と店舗の間に入り、決済処理を一括して行うプラットフォームです。2025年10月末時点でSmart Code加盟店は全国160万か所以上に達しており、teppayはこの既存インフラを活用することができます。主要なコンビニエンスストアであるセブン-イレブン、ローソン、ファミリーマートをはじめ、スーパーマーケット、ドラッグストア、百貨店など、日常的に利用する多くのチェーン店が既にSmart Codeに対応しています。これにより、teppayユーザーは「使える店がない」という後発サービス特有のストレスを感じることなく、サービス開始直後から幅広い場所で決済を行えます。
Smart Codeによる全国展開に加えて、JR東日本は自社グループの商業施設を中心とした独自の「teppay加盟店」の開拓も進めています。ルミネ、アトレ、エキュート、NewDaysなどの駅ナカ・駅チカ施設では、Suica決済との棲み分けや特定のキャンペーン展開が予想されます。2026年夏頃からは加盟店募集が開始される予定であり、サービス開始に向けて加盟店網の拡大が本格化します。
地域限定バリュー「バリチケ」による地方創生への貢献
teppayには地域経済活性化のための独自機能として「地域限定バリュー」、通称「バリチケ」が実装されます。これは利用できるエリアや店舗が限定されたデジタル商品券のような機能であり、自治体や地域の観光協会などが特定地域での消費を促進するために活用できます。具体的な活用例としては、温泉地や観光地エリア限定で使えるポイントの発行や、特定の市区町村における子育て世帯向け給付ポイントの配布などが想定されます。
この機能がもたらすメリットは多方面に及びます。自治体にとっては従来の紙の商品券の発行・印刷・配布・回収にかかるコストを大幅に削減でき、さらに利用データの分析が可能になることで政策効果の測定も容易になります。ユーザーにとってはスマートフォン一つで特典を受け取り利用できる手軽さがあります。JR東日本にとっては新幹線や特急列車での移動とセットにした観光プロモーションが可能になり、単なる決済手数料ビジネスを超えた自治体向けのDXソリューションビジネスへの展開が見込めます。
teppayポイントによる還元プログラム
teppayでの決済時には、利用額に応じて「teppayポイント」が付与される仕組みが導入されます。具体的なポイント還元率については2025年11月時点ではまだ発表されていませんが、競合する他社のコード決済サービスが基本還元率として0.5%から1.0%程度を設定していることから、同水準かあるいはビューカード利用時に優遇される設計が予想されます。
既存の「JRE POINT」との関係性も注目されるポイントです。JRE POINTは鉄道に乗って貯まるという独自の強みを持っており、これとteppayポイントをどのように連携させるかが今後の焦点となります。ユーザーにとってポイントが分散することはデメリットとなるため、長期的には両ポイントの統合、あるいは等価交換などのシームレスな連携が図られることが期待されます。「鉄道に乗って貯まる」JRE POINTと「買い物で貯まる」teppayポイントを循環させることで、JR経済圏全体の求心力を高める狙いがあると考えられます。
SuicaとPASMOの歴史的提携がもたらす意味
teppayの発表において特筆すべき点は、SuicaとPASMOが同一のコード決済プラットフォームを採用し、相互運用性を前提とした提携を行ったことです。かつて首都圏の交通系ICカード市場においてJRと私鉄連合は競合関係にありましたが、コード決済という新たな領域においては手を組み、共通の競合相手である巨大IT系決済事業者に対抗する姿勢を明確に打ち出しています。
この提携により、首都圏のほぼ全ての鉄道利用者がteppayの潜在的なユーザー基盤となります。モバイルSuicaとモバイルPASMOの利用者数を合算すると3,500万人を超える規模となり、この巨大な既存ユーザー基盤を活かしてコード決済市場への参入を図る戦略は極めて合理的といえます。2026年秋にモバイルSuicaで先行開始し、2027年春にモバイルPASMOが追随するというスケジュールにより、段階的かつ着実にサービスを拡大していく計画です。
競合するコード決済サービスとの比較分析
現在の日本国内コード決済市場は、PayPay、楽天ペイ、d払い、au PAYという4つの大手サービスによる寡占状態にあります。これらはいずれも通信キャリアやEC事業者を母体としており、それぞれ独自のポイント経済圏を構築しています。ここに「鉄道系」として参入するteppayは、異なる強みと課題を持っています。
PayPayや楽天ペイなどの先行サービスは、通信キャリアの顧客基盤やEC会員を起点としてユーザーを獲得し、大規模な還元キャンペーンを展開することで急速に普及しました。これらのサービスの強みはポイント経済圏の規模と、自社営業部隊による積極的な加盟店開拓にあります。一方で、決済のためにわざわざアプリを起動する手間や、通信障害時の脆弱性といった課題も抱えています。
teppayの強みは、通勤・通学という生活の動線に深く組み込まれた交通系アプリをベースとしている点にあります。毎日の移動で必然的にアプリを開くユーザーにとって、決済機能の追加は自然な拡張であり、アプリの起動頻度という点で他社を大きく上回ります。また、長年にわたって築かれてきたSuicaブランドへの信頼感も重要な資産です。JR東日本の調査によれば、人生で初めて利用したキャッシュレスサービスとしてSuicaやPASMOを挙げる人は5割を超え、若年層では7割に達するとされています。この「馴染み」という感情的なつながりは、過度なポイント還元競争に参加せずとも一定の利用が見込める基盤となります。
一方でteppayの課題としては、後発であることによる加盟店数の不足や、ポイント還元の魅力度で先行サービスに劣る可能性が挙げられます。Smart Codeの採用により加盟店数の問題はある程度解消されますが、PayPayが独自に開拓した小規模店舗などではteppayが使えないケースも生じる可能性があります。
MaaS戦略における決済機能の重要性
teppayの戦略的意義を理解するためには、JR東日本が推進するMaaS(Mobility as a Service)構想との関連を考える必要があります。MaaSとは、鉄道、バス、タクシー、シェアサイクルなど複数の交通手段を統合し、シームレスな移動体験を提供するコンセプトです。JR東日本はMaaSアプリ「Ringo Pass」などを通じてこの構想を推進してきましたが、これまで決済手段の登録がサービス利用のボトルネックとなっていました。
teppayがモバイルSuicaに統合されることで、鉄道の予約からタクシーの配車、シェアサイクルの利用、そして旅先での飲食や土産物の購入までを、単一のIDとウォレットで完結させることが可能になります。これは移動に伴う全ての消費データをJR東日本が捕捉できることを意味しており、将来的なデータビジネスの可能性を大きく広げます。「誰が、どこから来て、何を買ったか」という解像度の高いマーケティングデータは、行動ターゲティング広告やパーソナライズされた旅行提案の精度を劇的に向上させるでしょう。
FeliCa技術とQRコード決済の共存
技術的な観点から見ると、teppayの導入によりモバイルSuicaアプリ内には2つの異なる決済インターフェースが共存することになります。一つは従来からあるFeliCa技術を基盤としたタッチ決済であり、改札通過時に0.2秒という高速処理を実現しています。もう一つがteppayのQRコード決済であり、アプリを起動して画面を店員に見せる方式です。
JR東日本はこの2つの使い分けとして、改札や混雑するキオスクではスピードを重視してSuicaのタッチ決済を、高額な買い物や座って注文する飲食店では金額の柔軟性を重視してteppayのコード決済を推奨しています。アプリのユーザーインターフェースにおいては、利用者が迷わず適切な決済手段を選べるよう、直感的な切り替えボタンである「teppayボタン」の配置などが工夫されています。
ただし、QRコード決済はサーバーとの通信が必須となるため、オフライン環境では利用できません。Suicaのタッチ決済は端末が通信圏外でも決済可能という強みがありますが、teppayではその恩恵を受けられません。地下街や山間部の観光地など電波状況が不安定な場所では利用できないリスクがあり、JR東日本としては駅構内や車両内のWi-Fi環境整備を含め、通信インフラの安定性確保が重要な課題となります。
キャッシュレス疲れへの処方箋としてのteppay
JR東日本が実施した調査によると、消費者の多くが「キャッシュレス決済の多様化・複雑化」に対してストレスを感じているという結果が出ています。約76.1%の人が「決済手段をなるべく分散させたくない・まとめたい」と回答しており、2019年のキャッシュレス・ポイント還元事業以降に乱立した「○○ペイ」の増加が消費者に認知的な負担を強いていることが明らかになっています。それぞれの決済アプリが独自のポイントプログラムや還元ルールを持っているため、「どの支払い方法が最もお得か」を常に計算しなければならない状況は、多くの人にとって煩わしいものとなっています。
同調査では、決済手段をまとめるなら「馴染みのあるブランド・サービス」が良いと答えた人が77.5%に達しています。teppayはまさにこの消費者心理に応える形で設計されています。新規のコード決済アプリをインストールさせるためのマーケティングコストは非常に高くつきますが、既にインストールされている交通系アプリに機能を追加する場合、ユーザーの心理的ハードルはほとんどありません。JR東日本はSuicaが持つ圧倒的な「信頼資本」と「接触頻度」を武器に、分散していた消費者の決済行動を自社プラットフォームへ再統合しようとしています。
セキュリティ対策と安全性への配慮
コード決済サービスにおいては、不正利用やフィッシング詐欺への対策が重要な課題となります。特に銀行口座との連携機能を持つサービスでは、過去に他社で発生した不正引き出し事件のような被害が懸念されます。JR東日本は長年にわたりクレジットカード事業やSuica事業を運営してきた経験から、不正検知に関する豊富なノウハウを蓄積しています。
teppayではオープンなインターネット接続を前提とするコード決済という特性上、二要素認証の徹底やAIによるリアルタイムモニタリングなど、最高レベルのセキュリティ対策が求められます。具体的なセキュリティ施策の詳細は公表されていませんが、金融サービスとしての信頼性を担保するため、厳格な本人確認プロセスや不審な取引の自動検知システムなどが導入されることが予想されます。
teppayの収益モデルとビジネス戦略
teppayの収益源は主に加盟店から徴収する決済手数料です。Smart Code経由の決済では手数料の一部がJCBに分配されますが、JR東日本グループ内の商業施設や独自に開拓した加盟店での利用においては、手数料収入をグループ内で循環させることができます。駅ナカ施設での決済がteppayに集約されれば、グループ全体としての収益性向上につながります。
しかし、より大きな収益源として期待されているのはデータの活用です。Suicaの乗降データとteppayの購買データを紐付けることで、消費者の移動と購買行動を横断的に把握できるようになります。このデータを活用した広告配信や、提携企業への送客ビジネスこそが、teppayの本質的なビジネスモデルといえるでしょう。プライバシーへの配慮は必要ですが、適切に匿名化・集計されたデータは、小売業者や観光事業者にとって極めて価値の高いマーケティング資源となります。
将来展望と鉄道ペイの全国展開可能性
2027年のモバイルPASMO対応以降、teppayの影響力は首都圏全体に拡大します。さらに将来的には、JR東海やJR西日本など他のJR各社や、地方の私鉄各社との連携も視野に入ってくるでしょう。もし全国の交通系ICアプリがteppayまたはその互換システムを採用すれば、日本全国どこでも「いつもの鉄道アプリ」で買い物ができる時代が到来する可能性があります。
teppayの登場は、JR東日本が単なる鉄道会社から、利用者の生活全般を支える「ライフスタイルプラットフォーマー」へと変革するための重要な一歩です。2026年秋に私たちが手にするモバイルSuicaは、単なる定期券や電子マネーではなくなります。それは銀行口座とつながり、家族とつながり、地域の店舗とつながる、生活のオペレーティングシステムとも呼べる存在へと進化します。キャッシュレス決済の複雑化に疲れを感じている多くの消費者にとって、最も身近で信頼できるSuicaが進化することは、決済生活における一つの最適解となる可能性を秘めています。
teppayサービス開始までのスケジュール
teppayのサービス展開は段階的に進められます。2025年11月25日にサービスの発表が行われ、2026年夏頃には加盟店の募集が開始される予定です。そして2026年秋にはJR東日本のモバイルSuicaアプリ内でteppay機能の提供が始まります。続いて2027年春には株式会社パスモのモバイルPASMOアプリ内でもteppay機能が利用可能となります。
このスケジュールからは、JR東日本がまず自社サービスで先行してユーザーの反応を確認し、問題点を洗い出した上でPASMOへの展開を行うという慎重な姿勢が読み取れます。大規模な決済インフラの導入においては、システムの安定性確保が最優先事項であり、段階的なロールアウトは合理的な判断といえます。
まとめ teppayがもたらす決済体験の変革
teppayは、2026年秋の開始に向けて準備が進められている、JR東日本とPASMO陣営による新しいコード決済サービスです。従来の交通系電子マネーが抱えていた2万円のチャージ上限という制約を突破し、最大30万円までの決済に対応することで、日常の少額決済から高額な買い物まで幅広いシーンをカバーします。Smart Codeの採用により全国160万か所以上での利用が可能となり、後発サービスでありながら加盟店数の問題を解決しています。
既存のモバイルSuicaやモバイルPASMOアプリへの統合という設計により、ユーザーは新たなアプリのインストールや会員登録の手間なく、すぐにサービスを利用開始できます。ユーザー間送金やオンライン決済への対応、地域限定バリュー「バリチケ」による地方創生への貢献など、決済の枠を超えた総合的な金融サービスとしての展開が期待されます。PayPayをはじめとする先行サービスが市場を席巻する中、鉄道利用という日常の動線に深く根ざしたteppayが、どのように市場の勢力図を塗り替えていくのか、今後の展開から目が離せません。

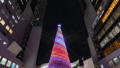

コメント