近年、ChatGPTやClaude、Geminiなどの生成AI技術が急速に普及し、ビジネスや日常生活のさまざまな場面で活用されるようになりました。しかし、その便利さの一方で、学習データに個人情報が含まれている可能性という重大な課題が浮上しています。2025年現在、個人情報保護委員会をはじめとする規制当局は、生成AIサービスの利用に関する注意喚起を強化し、適切な個人情報保護の重要性を訴えています。企業や個人が生成AIを安全に活用するためには、学習データにおける個人情報の存在を確認し、適切な対策を講じることが不可欠です。本記事では、生成AIの学習データに個人情報が含まれているかを確認する具体的な方法と、プライバシー保護のための実践的な対策について、最新の事例と法規制の動向を交えながら詳しく解説します。
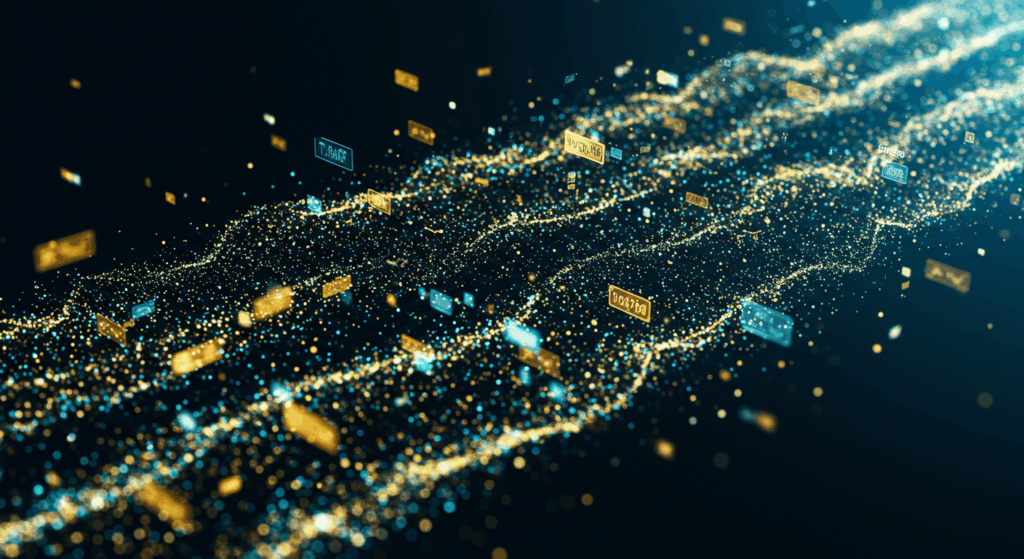
生成AIの学習データと個人情報リスクの現状
学習データに個人情報が含まれる仕組み
生成AIモデルは、インターネット上で公開されている膨大なテキストデータ、画像、動画などを学習データとして利用しています。これらのデータには、SNSの投稿、ブログ記事、ニュース記事、論文、企業の公開文書など、さまざまな情報源が含まれています。問題は、これらの公開データの中に、意図せず個人を特定できる情報が含まれている可能性があることです。
たとえば、ある人物の氏名とその経歴、住所の一部、電話番号、メールアドレスなどが、異なる情報源から収集され、AIモデルの学習過程で関連付けられる可能性があります。機械学習の過程で、これらの断片的な情報が統合され、特定の個人に関する詳細なプロファイルが形成されるリスクが存在するのです。
2024-2025年の最新動向と事例
2024年から2025年にかけて、生成AIによる個人情報漏洩事例が世界各地で報告されています。Samsung Electronicsでは、従業員が機密データをChatGPTにアップロードした事件を受けて、生成AIツールの使用を全面的に禁止する措置を取りました。エンジニアが内部のソースコードを入力したことで、そのデータが外部サーバーに保存され、他のユーザーに開示される可能性が生じたのです。
日本国内では、2024年3月に対話型AIサービス「Wrtn(리트ン)」において、ユーザーが入力したプロンプトや登録情報が第三者から閲覧・編集可能な状態になる脆弱性が発見されました。ニックネーム、入力したプロンプトとその結果、メールアドレス、LINE IDなどがアクセス可能な状態であったことが確認されています。
さらに、ダークウェブでは大手生成AIツールの2000万件のアカウント認証情報の販売に関する投稿も確認されており、セキュリティリスクは日々深刻化しています。
個人情報保護委員会による注意喚起と法的要件
2023年6月の重要な指針
個人情報保護委員会は2023年6月2日に「生成AIサービスの利用に関する注意喚起等」を公表し、個人情報取扱事業者が生成AIサービスを利用する際の法的要件を明確化しました。
主要な注意点として、以下の3つが強調されています:
- 学習データへの利用確認: 生成AIサービス提供事業者が、入力された個人データを機械学習に利用しないことを十分に確認する必要があります。
- 利用目的の範囲内での使用: 個人情報を含むプロンプトを入力する場合、特定された利用目的を達成するために必要な範囲内であることを確認しなければなりません。
- オプトアウト機能の活用: 入力データが学習データとして利用されないようにするオプトアウト機能を積極的に活用することが推奨されています。
2025年の法規制最新動向
2025年6月には、日本でAI新法(人工知能関連技術の研究開発及び利活用の推進に関する法律)が制定・公布されました。この法律により、内閣にAI戦略本部が設置され、AI基本計画の策定が義務付けられています。企業は、この新法に基づく政府の基本計画や指針に従い、適切なAIガバナンスを構築する必要があります。
また、個人情報保護法の改正も検討されており、個人の同意なしにデータ利活用が認められる場合の拡大や、行政罰金(課徴金)の導入などが議論されています。これらの法改正により、企業の責任はさらに重くなることが予想されます。
学習データの個人情報を確認する5つの実践的方法
1. サービス提供事業者への直接確認
生成AIサービスの学習データに個人情報が含まれているかを確認する最も確実な方法は、サービス提供事業者への直接的な問い合わせです。
確認すべき重要項目:
- データの利用目的: 入力データが学習用データセットに含まれるか
- 第三者提供の有無: データが他の企業や研究機関に提供されるか
- データの保存期間: 入力データがどの程度の期間保存されるか
- セキュリティ対策: 保存中のデータがどのように保護されているか
- 削除要求への対応: ユーザーからの削除要求にどのように対応するか
多くの大手AIサービス提供企業では、これらの情報をプライバシーポリシーや利用規約で公開していますが、不明な点がある場合は、カスタマーサポートに直接問い合わせることが重要です。
2. オプトアウト機能の設定と活用
ほとんどの主要な生成AIサービスでは、ユーザーが入力したデータを学習データとして使用しないオプトアウト機能を提供しています。
具体的な設定手順:
- アカウント設定画面にアクセス
- プライバシー設定またはデータ使用設定を選択
- 「学習に使用しない」または「オプトアウト」オプションを有効化
- 設定変更が正しく反映されていることを確認
重要な注意点: オプトアウト機能を設定する前に入力されたデータは、すでに学習データとして使用されている可能性があります。そのため、個人情報を含む可能性のあるデータを入力する前に、必ずオプトアウト機能を設定しておくことが不可欠です。
3. 利用規約とプライバシーポリシーの詳細確認
生成AIサービスを利用する前に、利用規約とプライバシーポリシーを詳細に確認することは基本中の基本です。
確認すべきポイント:
- データの収集範囲: どのような情報が収集されるのか
- データの使用目的: 収集されたデータがどのように使用されるか
- データの共有: 第三者とのデータ共有の有無と条件
- ユーザーの権利: データの削除要求やアクセス権の行使方法
- 準拠法と管轄: どの国の法律が適用され、紛争時の管轄はどこか
特に、GDPR(EU一般データ保護規則)に準拠しているサービスかどうかは、プライバシー保護のレベルを判断する重要な指標となります。
4. セキュリティ機能の確認と選択基準
個人情報を扱う可能性がある場合は、セキュリティ機能が充実したエンタープライズグレードのサービスを選択することが重要です。
必須のセキュリティ機能:
- 禁止ワード登録機能: 特定の個人情報や機密情報の入力を防ぐ
- 機密情報ロック機能: 重要な情報の外部流出を防止
- アクセスログの記録: 誰がいつどのような情報にアクセスしたかを追跡
- エンドツーエンド暗号化: データの送受信時の暗号化
- データの地理的所在の明確化: データがどの国で保存・処理されるか
5. 企業向けAIガバナンス体制の構築
組織レベルでの対応として、包括的なAIガバナンス体制の構築が不可欠です。
ガバナンス体制の主要要素:
- AIの利用に関するポリシー策定: 明確なルールとガイドラインの制定
- 従業員教育プログラム: リスクと対策に関する定期的な研修
- リスク評価の実施: 定期的な脆弱性診断とリスク分析
- インシデント対応手順: 情報漏洩発生時の迅速な対応体制
- 監査体制の確立: 内部監査と第三者評価の実施
最新のプライバシー保護技術と実装方法
連合学習(Federated Learning)の活用
連合学習は、各組織が保有するデータを直接共有することなく、AIモデルを協調的に学習させる革新的な技術です。2017年にGoogleが提唱したこの手法は、プライバシー保護とデータ活用の両立を実現します。
連合学習の仕組み:
- 各組織が自身のデータでローカルにモデルを学習
- 学習されたモデルのパラメータのみを中央サーバーに送信
- 中央サーバーでパラメータを統合し、グローバルモデルを更新
- 更新されたモデルを各組織に配布
実用例:
- Google: スマートフォンの予測変換履歴から連合学習でモデルを構築
- NVIDIA: 20の医療機関のデータを用いてCOVID-19患者の酸素投与判断モデルを開発
差分プライバシー(Differential Privacy)の実装
差分プライバシーは、統計的な解析を可能にしながら、個人情報を保護する数学的な枠組みです。データにランダムノイズを加えることで、個人の特定を防ぎながら、全体的な傾向を把握できます。
実装のポイント:
- ノイズの適切な調整: プライバシー保護とデータの有用性のバランス
- 感度の計算: 各データポイントがクエリ結果に与える影響の評価
- プライバシー予算の管理: 複数のクエリによる情報漏洩リスクの制御
秘密計算技術の併用
最新のアプローチでは、連合学習と秘密計算を組み合わせることで、より強固なプライバシー保護を実現しています。NECやNTTデータなどの日本企業も、これらの技術を活用した実用的なソリューションを開発しています。
具体的な対策チェックリスト
個人利用者向けチェックリスト
基本的な対策:
- [ ] オプトアウト機能を必ず有効化する
- [ ] 個人情報(氏名、住所、電話番号、メールアドレス等)を入力しない
- [ ] 機密情報や業務上の秘密を含むデータを入力しない
- [ ] 利用規約とプライバシーポリシーを確認する
- [ ] セキュリティ機能が充実したサービスを選択する
高度な対策:
- [ ] データの匿名化・仮名化を実施してから入力する
- [ ] VPNを使用してアクセスする
- [ ] 定期的にアカウント設定を見直す
- [ ] 不要になったデータの削除要求を行う
企業・組織向けチェックリスト
ガバナンス体制:
- [ ] AI利用ポリシーを策定し、全従業員に周知する
- [ ] リスク管理部門の責任範囲を明確化する
- [ ] 定期的な監査体制を確立する
- [ ] インシデント対応手順を文書化する
技術的対策:
- [ ] エンタープライズ向けAIサービスを採用する
- [ ] 禁止ワード登録機能を活用する
- [ ] アクセスログを定期的に監視する
- [ ] データ入力前の承認プロセスを導入する
教育・訓練:
- [ ] 全従業員向けのAIリテラシー研修を実施する
- [ ] 個人情報保護に関する定期的な教育を行う
- [ ] インシデント対応訓練を実施する
- [ ] 最新の脅威情報を共有する体制を構築する
GDPR対応と忘れられる権利の実務
忘れられる権利(削除権)の要件
GDPR第17条に基づく忘れられる権利は、個人がデータ管理者に対して自分の個人データの削除を要求できる権利です。生成AIの学習データにも適用される可能性があります。
削除要求が認められる主な条件:
- 個人データが収集された目的に照らして、もはや必要でない場合
- データ主体が同意を撤回し、他の法的根拠がない場合
- 個人データが違法に処理された場合
- 法的義務の遵守のために削除が必要な場合
削除要求への対応プロセス
企業が削除要求を受けた場合の標準的な対応手順:
- 要求の受付と内容確認: 削除要求の正当性を評価
- 法的根拠の検討: 削除の義務と例外事由の確認
- 技術的実現可能性の評価: システム上の削除可能性を検証
- 削除の実施: バックアップを含む全システムから削除
- 完了通知: 要求者への削除完了または拒否理由の説明
重要な課題: 大規模言語モデル(LLM)から特定の個人情報を「忘れさせる」ことは技術的に非常に困難です。一度学習されたデータを完全に除去するには、モデル全体の再学習が必要になる場合があります。
業界別の対策と事例
金融業界での取り組み
金融機関では、顧客の個人情報や取引データを扱うため、特に厳格な対策が求められています。
主な対策:
- 生成AI利用の全面的な制限または禁止
- 専用のプライベートAI環境の構築
- データの完全な匿名化処理後の利用
- 規制当局への定期的な報告体制
医療・ヘルスケア業界
医療データは特に機微な個人情報であるため、最高レベルの保護が必要です。
実施されている対策:
- 連合学習を活用した分散型AI開発
- 差分プライバシーによるデータの保護
- HIPAA(米国医療保険の相互運用性と説明責任に関する法律)準拠の確認
- 患者の明示的な同意取得プロセスの確立
教育機関での対応
教育現場では、学生の個人情報保護と教育効果の向上のバランスが重要です。
推奨される対策:
- 学生データの利用に関する明確なガイドライン策定
- 保護者への説明と同意取得
- 教職員向けの継続的な研修プログラム
- 学習支援AIツールの慎重な選定
今後の展望と準備すべきこと
2025-2026年の技術トレンド
今後予想される重要な技術動向:
- プライバシー保護技術の標準化: 連合学習や差分プライバシーの業界標準確立
- 説明可能AI(XAI)の進化: AIの判断根拠を明確化する技術の発展
- ブロックチェーン技術の活用: データの透明性と追跡可能性の向上
- 量子暗号技術の実用化: より強固なセキュリティの実現
法規制の進化への対応
予想される法規制の変化:
- 個人情報保護法のさらなる改正
- AI規制法の国際的な協調
- 業界別ガイドラインの策定
- 罰則の強化と課徴金制度の導入
企業は、これらの変化に柔軟に対応できる体制を今から構築しておく必要があります。
2025年の政府対応と最新規制動向
個人情報保護委員会による直接的な指導
2025年現在、個人情報保護委員会は生成AIサービスの普及を受けて、より具体的かつ厳格な指導を実施しています。特に注目すべきは、ChatGPTを開発・提供するOpenAIに対する直接的な注意喚起です。これは国際的なAIサービス提供企業に対する日本政府の積極的な対応姿勢を示すものです。
委員会は、個人情報取扱事業者があらかじめ本人の同意を得ることなく生成AIサービスに個人データを含むプロンプトを入力し、当該個人データがプロンプトに対する応答結果の出力以外の目的で取り扱われる場合、個人情報保護法の規定に違反する可能性が高いと明確に指摘しています。
企業のガバナンス体制強化の緊急性
現在、多くの企業で法務やコンプライアンス、DXなどの2線部門による早急な社内ガバナンス整備が求められています。特に重要なのは、従業員への明確なガイドラインの提供と周知・徹底です。
具体的な体制整備項目:
- 専門部署の設置: 生成AI利用を監督する専門チームの編成
- クロスファンクショナルな協力体制: 法務、IT、コンプライアンス部門の連携強化
- 定期的な見直し体制: ガイドラインと対策の継続的な更新メカニズム
- 従業員教育プログラム: 実践的な研修カリキュラムの開発と実施
最新の個人情報流出事例と教訓
国際的な大規模インシデント
2023年3月に発生した大手生成AIツールでの個人情報露呈事件では、システムの技術的な不具合により、一部ユーザーの重要な個人情報が短時間、他のユーザーに表示される事態が発生しました。流出した情報には以下が含まれます:
- 氏名と本人確認情報
- メールアドレスとアカウント情報
- 支払い先住所と請求情報
- クレジットカード情報の一部
この事件は、たとえ短時間であっても、システムの脆弱性が深刻な個人情報漏洩につながる可能性を示しています。
企業での情報流出実例
韓国サムスン電子での事例は、企業内でのAI利用リスクを如実に示しています。従業員がエラーとなったソースコードをChatGPTに入力し、バグ修正を依頼したところ、社外秘の機密情報が流出しました。この事例から学べる重要なポイント:
- 技術的な問題解決にAIを使用する誘惑: 開発者は効率的な解決策を求めがち
- 情報の機密性に対する認識不足: ソースコードに含まれる機密情報への配慮不足
- 組織的ガバナンスの重要性: 個人の判断に委ねることのリスク
実践的なリスク分類と対策フレームワーク
3層リスクモデルの理解
生成AIに関するリスクは以下の3つのカテゴリに分類されます:
1. 利用者としてのリスク:
- 個人情報や機密情報の意図しない流出
- 入力データの学習データへの取り込み
- プライバシー侵害と法的責任
2. 生成AIサービス提供者のリスク:
- 大規模なデータ漏洩インシデント
- 規制当局からの制裁措置
- 利用者からの集団訴訟リスク
3. 社会全体のリスク:
- 個人情報の大規模な悪用
- 社会的信頼の失墜
- 技術革新の阻害要因
高度なセキュリティ対策の実装
最新のセキュリティ対策として、以下の機能を備えたサービスの選択が重要です:
禁止ワード登録機能の高度化:
- 正規表現を活用した柔軟な検出パターン
- 文脈を考慮した動的な検出システム
- 多言語対応とローカライゼーション
機密情報ロック機能:
- リアルタイムでの情報検出と遮断
- 管理者への即座な通知機能
- 違反行為のログ記録と分析
GDPR完全準拠の確認:
- 第三者機関による定期的な監査結果の確認
- データポータビリティ機能の提供状況
- 削除要求への技術的対応能力
最新の法的動向と企業への影響
データ利活用法制の新展開
2025年のAI向け学習データ提供に関する新たな法的枠組みでは、一定の条件下で個人の同意なしにデータ利活用が認められる可能性について検討が進められています。しかし、これには厳格な条件が設定される予定です:
- 相手先の明確な公表: データ提供先の透明性確保
- 利用目的の詳細な明示: 具体的かつ限定的な目的の設定
- 適切な管理体制の証明: 第三者による管理体制の監査
- 技術的安全措置の実装: 最新のセキュリティ技術の採用
国際的な規制調和の動き
日本の規制は、EUのAI規制法や米国の連邦レベルでの取り組みとの調和を図りながら発展しています。これにより、グローバルに事業を展開する企業は、より統一されたコンプライアンス要件に対応する必要があります。
まとめ:安全な生成AI活用のために
生成AIの学習データに個人情報が含まれているかを確認し、適切に対処することは、現代のデジタル社会において避けて通れない課題です。本記事で解説した5つの確認方法と具体的な対策を実践することで、リスクを最小限に抑えながら、生成AIの恩恵を享受することが可能になります。
最も重要なのは、「個人情報や機密情報は原則として入力しない」という基本原則を徹底することです。やむを得ず使用する場合は、オプトアウト機能の活用、データの匿名化、セキュリティ機能の確認など、多層的な防御策を講じる必要があります。
2025年の政府による直接的な指導や最新の流出事例は、従来の対策だけでは不十分であることを示しています。企業は専門部署の設置、クロスファンクショナルな協力体制の構築、定期的なガイドラインの見直しなど、より組織的で包括的なアプローチを採用する必要があります。
2025年以降も、生成AI技術と法規制は急速に進化していくことが予想されます。企業や個人は、最新の動向を常に把握し、適切なガバナンス体制とセキュリティ対策を継続的に更新していくことが求められます。透明性の確保、技術的対策の実施、法的コンプライアンスの遵守という3つの柱を中心に、安全で信頼性の高い生成AI活用環境を構築していきましょう。

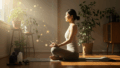
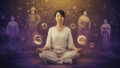
コメント