近年、日本各地でクマによる人身被害が深刻化しており、特に市街地や住宅地への出没が増加したことで、住民の安全が脅かされる事態が続いています。2023年度には統計開始以来最多となる人身事故が発生し、6人の命が失われました。こうした緊急事態に対応するため、2025年9月1日に緊急銃猟制度が全国で施行されました。この制度により、市街地においても一定の要件を満たせば猟友会などのハンターが発砲してクマを駆除できるようになったのです。しかし、制度が施行されたにもかかわらず、現場のハンターたちは深刻な不安を抱えており、実際に市街地で発砲することを躊躇する状況が生じています。その背景には、過去に正当な駆除活動を行ったハンターが法的責任を問われた「砂川事件」の影響や、ハンターの急速な減少と高齢化、法的保護や補償制度の不十分さなど、複雑な課題が絡み合っています。本記事では、緊急銃猟制度の詳細と、市街地での発砲をめぐる猟友会とハンターが直面する現実的な課題について、詳しく解説していきます。

緊急銃猟制度の施行と背景
2025年9月1日、改正鳥獣保護管理法に基づく緊急銃猟制度が日本全国で施行されました。この制度は、クマやイノシシなどの大型野生動物が市街地や住宅地に出没し、住民の生命に危険が及ぶ緊急事態において、市町村長の判断と指示のもと、猟友会などに委託されたハンターが銃器を使用して迅速に駆除できるようにするものです。
この制度が導入された最大の理由は、近年のクマによる人身被害の急増にあります。2023年度には、統計開始以来最多となる198件の人身事故が発生しました。被害者数は219人に達し、そのうち6人が命を落とすという過去最悪の事態となりました。秋田県では62件、岩手県では46件の人身被害が確認され、この2県だけで全国の半数以上を占める深刻な状況でした。さらに、農作物被害額も前年度の約4億700万円から約7億4700万円へと約1.8倍に急増し、捕獲頭数も9274頭と過去最多を記録しました。
2024年度も状況は改善せず、11月末時点で被害者数が81人となりました。4月から7月までの出没件数は1万704件と前年度を上回り、依然として深刻な状況が続いています。4月から8月までに56件の人的被害が発生し、2名が死亡、11月末現在で4971頭が捕獲されました。
従来は、市街地での発砲が原則として禁止されていました。そのため、住宅地にクマが出没した場合、行政や警察が猟友会に駆除を依頼しても、ハンターは発砲することができず、熊撃退スプレーなどの非銃器手段に頼らざるを得ませんでした。しかし、こうした手段では十分な効果が得られず、クマによる被害が拡大し続けたことから、緊急時には銃器の使用を認める法改正が行われることとなったのです。
緊急銃猟制度の適用要件
緊急銃猟制度が適用されるには、4つの厳格な要件をすべて満たす必要があります。これらの要件は、住民の安全を最優先にしながら、緊急時の迅速な対応を可能にするために定められています。
第一の要件は、クマやイノシシが住居や車両に侵入した、または侵入する恐れが高い状態であることです。単に市街地に出没したというだけでは不十分で、人の生活圏内に実際に侵入しているか、その危険性が切迫していることが求められます。この要件により、無秩序な駆除を防ぎ、真に危険な状況に限定して制度が適用されることになります。
第二の要件は、住民の危険を防止するために緊急の措置が必要であることです。時間的余裕がなく、直ちに対応しなければ人身被害が発生する可能性が高い状況を指します。この緊急性の判断は、市町村長が現場の状況を踏まえて行うことになりますが、住民の生命が脅かされる切迫した状況であることが前提となります。
第三の要件は、銃器を使用しなければ迅速かつ的確な捕獲が困難であることです。麻酔銃や罠、スプレーなどの他の手段では対応が難しく、銃器による駆除が最も効果的かつ安全な方法であると判断される場合に限定されます。この要件により、銃器の使用が最終手段として位置づけられ、他の方法が可能な場合には銃器を使用しないという原則が維持されます。
第四の要件は、銃弾が住民に当たる危険性がないことです。これは最も重要な要件で、発砲の際に流れ弾や跳弾が住民や建物に当たる可能性がないことを十分に確認する必要があります。交通規制や住民の避難などの安全措置が講じられていることが前提となります。この要件は、市街地での発砲という極めて危険な行為を行う際の絶対条件として、ハンターと行政の双方に重い責任を課しています。
これら4つの要件がすべて満たされた場合に限り、市町村長が緊急銃猟を指示でき、委託されたハンターが市街地で発砲することが法的に認められることになります。環境省は2025年7月8日に「緊急銃猟ガイドライン」を公表し、自治体がこの制度を適切に運用できるよう詳細な指針を示しました。
砂川事件が投げかけた影が
緊急銃猟制度が施行されたにもかかわらず、ハンターたちの間には深刻な不安が広がっています。その最大の原因となっているのが、2018年に発生した「砂川事件」です。この事件は、正当な駆除活動を行ったハンターが後から法的責任を問われるという、現場のハンターにとって悪夢のような事態を示すものでした。
2018年8月、北海道砂川市で体長約80センチのヒグマの子グマが市街地に出没しました。市の職員と警察官の立ち会いのもと、70歳のベテランハンターである池上晴雄氏が市からの依頼を受けてライフル銃で子グマを駆除しました。これは行政と警察の要請に応じた正当な駆除活動でした。
しかし、2019年2月、砂川警察署は通報を受けて「住宅の建物に向かって発砲した」として、池上氏を鳥獣保護法違反と銃刀法違反の疑いで捜査し、検察に送致しました。検察は不起訴処分としましたが、北海道公安委員会は2019年4月、「住宅の建物に向かって違法に発砲した」と判断し、池上氏の猟銃所持許可を取り消しました。
池上氏は処分の取り消しを求めて訴訟を起こし、2021年10月、札幌地方裁判所は池上氏の訴えを全面的に認め、公安委員会の処分を違法として取り消す判決を下しました。砂川市の農政部も「正当な行動が認められて良かった」とコメントし、3年以上にわたる不便をかけたことに遺憾の意を表明しました。
ところが、2024年10月18日、札幌高等裁判所は一審判決を覆し、「跳弾により弾道が変わり、5つの建物に到達する恐れがあった」として、公安委員会による銃所持許可取り消しを適法と認める逆転判決を下しました。池上氏は上告しましたが、行政と警察の要請に応じて駆除を行ったにもかかわらず、6年もの長期にわたる法廷闘争の末に敗訴し、銃の所持許可を失うという結果となりました。
この砂川事件は、猟友会や全国のハンターに大きな衝撃を与えました。「行政や警察の要請に応じて正当に駆除活動を行っても、後から刑事責任や行政処分を問われる可能性がある」という認識が広がり、ハンターたちの間に深刻な不安と不信感が生じました。函館支部などの一部の猟友会支部は、砂川事件を受けて「いつ許可が取り消されるか分からない」として、一時的に市町村からの駆除依頼への対応を拒否する事態も発生しました。
この事件は、緊急銃猟制度の導入後も、現場のハンターが発砲を躊躇する大きな要因となっています。法律で市街地での発砲が認められても、実際に引き金を引くハンターがいなければ、制度は機能しないのです。
北海道猟友会の発砲拒否容認という苦渋の判断
緊急銃猟制度が施行される直前の2025年8月28日、北海道猟友会は各支部に対して、市町村からの発砲要請があってもハンターが拒否できることを容認する通知を出すことを検討していると発表しました。この判断は、制度の実効性に疑問を投げかける重大な出来事となりました。
この判断の背景には、砂川事件のような事例が再発することへの強い懸念がありました。また、人身事故が発生した際のハンターに対する補償制度が不十分であることも大きな問題とされました。緊急銃猟制度では、市街地での発砲が認められるようになりましたが、万が一流れ弾や跳弾が住民に当たった場合、ハンターが刑事責任や民事責任を問われる可能性があり、その際の十分な補償や法的保護の仕組みが整備されていないという指摘がありました。
北海道猟友会は、「安全確保の状況によっては発砲しなくてもよい」という内容の支部通知を検討し、ハンターが自らの判断で発砲を拒否できることを明確にしました。これは、ハンター個人の責任とリスクがあまりにも大きく、命がけの作業に対する補償や法的保護が不十分であるという現場の実態を反映したものでした。
この発砲拒否容認の判断は、緊急銃猟制度の実効性に疑問を投げかけることとなりました。制度上は市街地での発砲が可能になっても、実際に発砲するハンターがいなければ、クマ駆除は実施できません。「撃てば処罰される」という認識が広がる中、ハンターたちは法的リスクと生命の危険の両方に直面することになり、現場での発砲判断が極めて困難な状況が続いています。
ハンター不足と高齢化という深刻な現実
緊急銃猟制度の導入を困難にしているもう一つの大きな問題が、ハンターの急速な減少と高齢化です。日本の野生動物管理において、猟友会は長年にわたって重要な役割を果たしてきましたが、その基盤が大きく揺らいでいます。
環境省の統計によれば、全国の狩猟者数はピーク時の4分の1以下にまで減少しており、猟友会会員の約60パーセントが60歳以上となっています。北海道千歳市の猟友会支部では、75歳の支部長が最前線で駆除活動に従事しているという状況もあります。2025年には、危険なクマ駆除を担える熟練ハンターの高齢化と引退により、人員が急速に減少しています。
ハンター数の減少は量的な問題だけでなく、質的な問題でもあります。クマ駆除、特に市街地での緊急銃猟は、高度な射撃技術と冷静な判断力、豊富な経験が求められる極めて危険な作業です。しかし、若手ハンターの育成が追いつかず、技術の継承が滞っているという指摘があります。
北海道猟友会が全支部に対して実施したアンケート調査では、熟練ハンターの減少により、ヒグマ駆除の対応が困難になっているという回答が多数寄せられました。ベテランハンターが引退しても、その技術や経験を受け継ぐ若手が不足しているため、駆除体制の空白地帯が生じる懸念が高まっています。
ハンター減少の背景には、複数の要因があります。第一に、駆除作業に対する報酬が、命がけの危険性に見合っていないという経済的な問題があります。第二に、砂川事件のような事例が示すように、正当な駆除活動を行っても後から行政処分や刑事責任を問われるリスクがあるという法的な不安があります。第三に、銃の所持許可を取得し維持するための手続きが煩雑で、費用もかかるという制度的なハードルがあります。第四に、若い世代が狩猟に興味を持ちにくく、新規参入者が少ないという社会的な課題があります。
これらの要因が複合的に作用し、猟友会頼みの駆除体制は限界に達しつつあります。2023年に219人の人身被害が発生し、2025年4月から7月までに55人の負傷者と3人の死者が出るという最悪ペースが続く中、ハンター不足はより深刻な問題となっています。
市街地での発砲が抱える現実的な困難
緊急銃猟制度が施行されても、実際に市街地で発砲することには多くの困難と課題が伴います。法律で認められたからといって、簡単に実行できるものではないのが現実です。
最大の問題は、流れ弾や跳弾のリスクです。市街地には建物や車両、電柱、道路標識などが密集しており、発砲した弾丸が意図しない方向に飛んだり、何かに当たって跳ね返ったりする可能性があります。ハンターは、クマを確実に仕留めることと同時に、周囲の住民や建物に一切被害を与えないという両立が困難な要求に応えなければなりません。
砂川事件の高裁判決では、「跳弾により弾道が変わり、建物に到達する恐れがあった」ことが処分の根拠とされました。この判決により、ハンターは「絶対に跳弾が発生しない」ことを証明しなければならないという、極めて高いハードルが課されることになりました。しかし、発砲の瞬間にすべての要素を完璧にコントロールすることは現実的に不可能であり、どれほど慎重に判断しても、後から「跳弾の恐れがあった」と指摘される可能性があります。
また、市街地では住民の避難や交通規制が必要となりますが、緊急事態において迅速にこれらの措置を講じることは容易ではありません。住民全員が避難したことを確認し、交通を完全に遮断し、発砲の安全を確保するまでには時間がかかります。しかし、クマはその間に移動してしまう可能性があり、迅速性と安全性の両立という矛盾に直面します。
さらに、発砲の判断はハンター個人に委ねられることが多く、その責任は極めて重大です。市町村長が緊急銃猟を指示したとしても、実際に発砲するかどうかの最終判断はハンターが行います。もし発砲して跳弾などが発生すれば、ハンターが刑事責任や民事責任を問われる可能性があります。一方、発砲せずにクマによる人身被害が発生すれば、ハンターは対応が不十分だったと批判される可能性があります。このジレンマの中で、ハンターは極めて困難な判断を迫られます。
緊急銃猟制度の施行から2週間以内に、現場での経験不足や、警察の指導があっても責任問題への懸念が解消されていないなどの課題が明らかになりました。制度は整備されても、現場のハンターが安心して発砲できる環境が整っていないという根本的な問題が残されています。
自治体と警察が果たすべき役割
緊急銃猟制度において、市町村と警察の役割は極めて重要です。しかし、現場での実施にはさまざまな課題があります。
市町村長は、緊急銃猟の要件が満たされているかを判断し、委託ハンターに発砲を指示する権限と責任を持ちます。しかし、多くの市町村には野生動物管理の専門知識を持つ職員が少なく、緊急事態において適切な判断を迅速に下すことは容易ではありません。また、発砲を指示した結果、万が一事故が発生した場合の行政責任も問われる可能性があり、市町村側も慎重にならざるを得ない状況があります。
警察は、発砲の安全性を確認し、交通規制や住民の避難などの安全措置を講じる役割を担います。しかし、砂川事件では、警察官が立ち会っていたにもかかわらず、後になって「建物に向かって発砲した」として捜査が行われました。このことは、警察が現場で発砲を容認しても、後から別の判断がなされる可能性があることを示しており、ハンターの不安を増大させる要因となっています。
また、警察と猟友会の連携も課題です。緊急事態において、警察がどの程度迅速に現場に到着し、安全措置を講じられるかは状況によって異なります。特に地方の過疎地域では、警察官が現場に到着するまでに時間がかかることもあり、その間にクマによる被害が拡大する恐れがあります。
自治体と警察、猟友会の三者が緊密に連携し、事前に明確な手順と責任分担を決めておくことが重要ですが、多くの地域ではそのような体制が十分に整備されていないのが現状です。市街地での発砲という前例のない事態に対応するためには、関係機関が日頃から連携を深め、合同訓練などを通じて実践的な準備を進める必要があります。
行政ハンター制度という新たな可能性
猟友会頼みの駆除体制の限界が明らかになる中、「行政ハンター」制度が注目を集めています。この制度は、従来の委託方式とは異なる新しいアプローチとして、持続可能な野生動物管理の実現に向けた可能性を秘めています。
行政ハンターとは、市町村が直接雇用する野生動物管理の専門職員のことです。猟友会への委託という従来の方式ではなく、自治体が専門の人材を職員として採用し、鳥獣被害対策や駆除活動を専門に担当させる仕組みです。
長野県小諸市や北海道占冠村などでは、すでに行政ハンター制度を導入し、一定の成果を上げています。行政ハンターは自治体の職員であるため、駆除活動が正式な職務となり、法的責任や補償の面でも明確になります。これは、砂川事件のような事例で問題となった法的保護の不明確さを解消する一つの解決策となる可能性があります。
また、専門職として継続的に技術を磨き、経験を蓄積できるため、高度な駆除技術を維持しやすいという利点があります。猟友会の会員の多くは本業を持ちながら駆除活動に従事していますが、行政ハンターは野生動物管理を専門とするため、より高度な技術と知識を持つことが期待できます。
さらに、行政ハンターは野生動物の生態調査や被害予防策の立案、住民への啓発活動なども担当でき、総合的な野生動物管理を実施できます。猟友会への依頼では、駆除そのものに焦点が当たりがちですが、行政ハンターは予防から駆除、事後の分析まで一貫して対応できるという強みがあります。
しかし、行政ハンター制度にも課題があります。第一に、自治体の財政負担が増加することです。職員として雇用するには、給与や福利厚生、装備品の購入などの費用がかかります。財政が厳しい自治体にとっては、導入のハードルが高くなります。
第二に、適切な人材の確保が難しいことです。高度な射撃技術と野生動物の知識を持ち、危険な駆除活動を担える人材は限られています。採用試験を実施しても、十分な応募者が集まらない可能性があります。
第三に、行政ハンターだけですべての駆除需要に対応することは困難です。クマの出没は広範囲かつ多発するため、行政ハンターの人数だけでは対応しきれず、結局は猟友会との連携が必要になります。
それでも、猟友会頼みの体制が限界に達している現状では、行政ハンターの導入は重要な選択肢の一つとなっています。自治体職員として明確な法的地位と補償を持つ専門家が駆除活動を担うことで、砂川事件のような問題を回避し、より安定した駆除体制を構築できる可能性があります。
環境省ガイドラインと実務の課題
環境省が2025年7月8日に公表した「緊急銃猟ガイドライン」は、市町村が緊急銃猟制度を適切に運用するための詳細な手引きとなっています。このガイドラインは、改正鳥獣保護管理法に基づく緊急銃猟制度の運用方法を丁寧に解説しており、図表や具体例を用いて実務的な指針を示しています。
ガイドラインの主な内容は、緊急銃猟の基本的な考え方と実施判断に関する事項、そして事前準備から捕獲後までの各段階で必要な措置、情報、注意事項などが含まれます。特に安全対策と捕獲方法については詳細に記載されており、市町村職員が現場で判断する際の具体的な基準が示されています。
緊急銃猟を実施できるのは、クマやイノシシが人の日常的な生活領域(農地や河川敷、建物内など)に出没した場合で、十分な安全措置が取られていることが前提となります。一方、緊急銃猟を実施できない場合として、人の日常的な生活領域でない場合や、銃弾が人に当たる危険性がある場合(例:繁華街や住宅密集地など)が明示されています。
事前準備として、市町村は対応マニュアルの作成、訓練の実施、装備品の購入、保険の加入などを行う必要があります。これらの準備には環境省の指定鳥獣管理対策事業交付金や特別交付税措置による財政支援が活用できます。環境省は、改正法の運用に関する自治体職員向けの説明会や研修会も開催する予定としています。
しかし、ガイドラインが詳細に策定されていても、実務上の課題は少なくありません。市町村の多くは野生動物管理の専門家を十分に擁していないため、ガイドラインに基づく適切な判断を緊急時に迅速に行うことは容易ではありません。また、訓練や装備品の整備には時間と費用がかかり、小規模な自治体では体制整備が遅れる可能性があります。
さらに、ガイドラインは安全措置の重要性を強調していますが、市街地で完璧な安全措置を講じることは現実的に困難な場合があります。住民の避難や交通規制を完全に実施するには時間がかかり、その間にクマが移動してしまう可能性があります。迅速な対応と完璧な安全措置の両立という矛盾が、現場での実施を難しくしています。
アーバンベア問題の深刻化
近年、市街地に出没するクマを指す「アーバンベア」という言葉が広く知られるようになりました。2023年には「アーバンベア」が流行語大賞に選出されるほど、クマの市街地出没は社会的関心が高い問題となっています。
2025年度のクマによる犠牲者は7人と過去最多を更新し、4月から9月末時点で重軽傷のけが人を含むクマの被害者は全国で計108人にも上っています。専門家は、2025年は東北地方で問題行動を起こしやすい2歳のクマの数が多いと推測しており、出没や事故がさらに増加すると予測しています。
アーバンベアの出没には、複数の要因が複合的に関係しています。第一に、気候変動と地球温暖化の影響です。地球温暖化により春の訪れが早まり、冬眠から目覚めたクマが自然界で十分な食料を見つけられない状況が生じています。また、温暖化の影響でクマの主要な食料であるどんぐりの生産量が不安定になり、凶作の年にはクマが人里に食料を求めて降りてくる傾向が強まっています。
第二に、クマの生息地の縮小と環境変化があります。戦後に進められたスギやヒノキの大規模植林により、広葉樹林が減少し、森林が単純化されました。また、ナラ枯れと呼ばれる病害により広葉樹が枯死する現象が広がり、クマの餌場がさらに減少しています。さらに、過疎化や高齢化による耕作放棄地の増加、放置された果樹園、適切に管理されない生ごみなどが、クマを人里に引き寄せる要因となっています。
第三に、クマの個体数の増加と分布拡大です。保護政策の進展により、ツキノワグマやヒグマの個体数は一時期の減少から回復傾向にあります。個体数が増加すると、生息域が拡大し、これまでクマが出没しなかった地域にも進出するようになります。
第四に、人を恐れない「新世代クマ」の増加があります。人里での食料入手を学習したクマは、人間を恐れずに住宅地や市街地に出没するようになります。こうしたクマが子育てをすると、その子グマも人里での採餌行動を学習し、世代を超えてアーバンベアが増加する悪循環が生じています。
アーバンベア問題への対策として、2025年2月に閣議決定された鳥獣保護管理法の改正により、緊急銃猟制度が導入されました。しかし、駆除だけでは根本的な解決にはならず、予防策も重要です。
特に被害が深刻化している地域では、「ゾーニング管理」の導入が進んでいます。秋田県では、市街地に近いなど特にリスクが高いエリアを「管理強化ゾーン」として区分し、対策を重点的に行うこととしています。このゾーニング管理では、クマの生息密度を把握し、リスクに応じて捕獲圧を調整することで、市街地への出没を抑制することを目指しています。
また、クマを市街地に引き寄せないための環境整備も重要です。生ごみの適切な管理、放置された果樹の撤去、耕作放棄地の管理、緩衝地帯の整備などにより、クマが人里に近づきにくい環境を作ることが求められます。住民への啓発活動も不可欠で、クマとの遭遇時の対処法や、クマを引き寄せない生活習慣の普及が必要です。
今後に向けた課題と展望
緊急銃猟制度の施行により、法制度上は市街地でのクマ駆除が可能になりましたが、実効性を高めるためには多くの課題を解決する必要があります。
第一に、ハンターの法的保護と補償制度の充実が急務です。正当な駆除活動を行ったハンターが後から処罰されることがないよう、明確な法的保護の仕組みを整備する必要があります。また、万が一事故が発生した場合の十分な補償制度を設け、ハンターが安心して活動できる環境を整えることが重要です。砂川事件のような事例が再発しないよう、行政や警察の要請に応じた駆除活動については、その正当性が法的に保護される仕組みが必要です。
第二に、駆除活動に対する適切な報酬体系の確立が必要です。命がけの危険な作業に見合った報酬を支払うことで、ハンターのモチベーションを維持し、新規参入者を増やすことができます。現状では、多くの地域で駆除活動の報酬が危険性に見合っていないという指摘があり、これがハンター減少の一因となっています。
第三に、若手ハンターの育成と技術継承の仕組みを強化する必要があります。ベテランハンターの知識と経験を体系的に若手に伝える研修制度や、安全な環境で実践的な訓練ができる施設の整備が求められます。市街地での発砲という高度な技術を要する作業を安全に実施できる人材を育成するためには、長期的な視点での人材育成プログラムが必要です。
第四に、行政ハンター制度の導入を含め、猟友会に依存しない多様な駆除体制を構築することが重要です。自治体の財政状況に応じて、行政ハンターの雇用や、広域連携による専門チームの設置などを検討すべきです。一つの方式に頼るのではなく、地域の実情に応じた柔軟な体制を構築することが求められます。
第五に、市町村と警察、猟友会の連携体制を強化し、緊急時の対応手順を明確化する必要があります。事前に合同訓練を実施し、実際の緊急事態において迅速かつ安全に駆除活動を行えるよう準備しておくことが重要です。三者間で責任分担を明確にし、誰がどのような判断をするのかを事前に決めておくことで、現場での混乱を避けることができます。
第六に、クマとの遭遇を未然に防ぐための予防策を強化することも必要です。市街地への侵入を防ぐための緩衝地帯の整備や、住民への啓発活動、ゴミ管理の徹底など、総合的な野生動物管理政策が求められます。駆除だけに頼るのではなく、クマが市街地に来ない環境を作ることが、長期的には最も重要な対策となります。
第七に、砂川事件のような事例の再発を防ぐため、司法機関や行政機関が現場の実態を十分に理解し、ハンターの正当な活動を適切に評価する必要があります。行政や警察の要請に応じた駆除活動が後から不当に処罰されることがないよう、法的な明確化と運用の改善が求められます。
緊急銃猟制度は、深刻化するクマ被害に対応するための重要な一歩ですが、制度の実効性を高めるためには、これらの課題に総合的に取り組む必要があります。法制度の整備だけでなく、現場のハンターが安心して活動できる環境を整え、持続可能な野生動物管理体制を構築することが、今後の大きな課題となっています。
クマ被害が過去最悪のペースで続く中、人命を守るための緊急銃猟制度が真に機能するかどうかは、これからの取り組みにかかっています。制度の理念を現場で実現するための課題は多く、行政、警察、猟友会、司法機関、そして社会全体が協力して解決していく必要があります。市街地での発砲という前例のない挑戦に、私たちの社会がどう向き合っていくかが問われています。

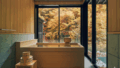

コメント