日本の自動車産業が世界に誇るジャパンモビリティショー2025が、東京ビッグサイトで10月30日から11月9日まで開催されています。モビリティの未来を体験できるこの大規模イベントには、500社を超える企業が参加し、次世代の移動手段やコンセプトカーが一堂に会しています。特に注目を集めているのが、日産とホンダが世界初公開する革新的なコンセプトカーと注目車種です。日産は16年ぶりのフルモデルチェンジとなる新型エルグランドを発表し、第3世代e-POWERという最新の電動化技術を搭載することで話題となっています。一方、ホンダはHonda 0シリーズの新型SUVプロトタイプをはじめ、薄い、軽い、賢いという独創的な開発思想に基づいた次世代電気自動車を披露しました。電動化が加速する自動車業界において、両メーカーがどのような未来像を描いているのか、そして私たちの生活にどのような変化をもたらすのか。本記事では、モビショー2025で発表された日産とホンダの注目車種とコンセプトカーについて、詳しく解説していきます。

ジャパンモビリティショー2025の全貌
ジャパンモビリティショー2025は、東京都江東区有明の東京ビッグサイトにて2025年10月30日から11月9日まで開催される、日本最大級のモビリティイベントです。一般公開は10月31日から11月9日までとなっており、自動車ファンだけでなく、未来のテクノロジーに興味を持つ幅広い層の来場者で賑わいを見せています。今回は500社以上という過去最多規模の企業が参加し、従来の東京モーターショーから進化した総合的なモビリティの祭典として位置づけられています。
このイベントの最大の特徴は、単なる自動車の展示にとどまらず、モビリティの未来全体を体験できる点にあります。136の出展者が乗用車、商用車、二輪車、車体、部品・機械、モビリティ関連という6つのカテゴリーに分かれて参加しており、自動車メーカーだけでなく、IT企業、エネルギー企業、スタートアップ企業など多様なプレイヤーが集結しています。電動化、自動運転、コネクテッド技術といった次世代のモビリティテクノロジーが一堂に会することで、10年後、20年後の移動の姿を垣間見ることができる貴重な機会となっています。
特に今年のショーでは、電動化技術が中心的なテーマとなっており、各メーカーが競って最新のEV技術やハイブリッドシステムを披露しています。脱炭素社会の実現に向けて、自動車産業は大きな変革期を迎えており、ジャパンモビリティショー2025はその最前線を体感できるイベントとして大きな注目を集めています。
日産の目玉:新型エルグランドの衝撃
日産自動車がジャパンモビリティショー2025で発表した新型エルグランドは、まさに今回のイベントにおける最大の目玉の一つといえるでしょう。10月29日のプレスデーで世界初公開されたこのプレミアムミニバンは、実に16年ぶりのフルモデルチェンジとなります。現行モデルが2010年に登場してから長い年月が経過しており、市場からは刷新を待ち望む声が高まっていました。
新型エルグランドの最大の特徴は、パワートレインの大胆な変革にあります。現行モデルが搭載していたV6エンジンを廃止し、1.5リッター直列4気筒VCRエンジンと第3世代e-POWERハイブリッドシステムの組み合わせが採用されています。この変更は、環境規制の強化と燃費性能向上の要求に応えるためのものであり、日産の電動化戦略を象徴する決断といえます。
VCRエンジンは、可変圧縮比技術を採用した革新的なエンジンで、走行状況に応じて圧縮比を最適化することで、パフォーマンスと燃費を高次元で両立します。これに第3世代e-POWERシステムを組み合わせることで、モーターによる力強い加速と優れた静粛性、そして高い燃費性能を実現しています。エンジンの排気量がダウンサイジングされることに懸念を持つ方もいるかもしれませんが、e-POWERシステムではエンジンは主に発電用として使用され、駆動は完全にモーターで行われるため、実際の走行フィーリングはむしろ向上しているというのが専門家の評価です。
予想されるボディサイズは、全長4965mm×全幅1850mm×全高1850mmとされています。これは現行モデルよりもわずかに拡大されたサイズであり、室内空間のさらなる充実が期待できます。プレミアムミニバンとしての存在感を保ちながら、日本の道路環境でも扱いやすいサイズ感を維持している点が評価されています。
デザイン面では、グリルとヘッドライトが一体化した近未来的な表情が特徴となっています。これは日産の最新デザイン言語を取り入れたものであり、アリアなどの電動車に見られる先進的なスタイリングを継承しています。フロントマスクは、日産車であることを一目で認識できる統一感を持ちながら、エルグランド独自のプレミアム感と存在感を表現しています。
新型エルグランドは新世代プラットフォームを採用することで、走行性能と安全性能を大幅に向上させています。現代の自動車に求められる高い衝突安全性能や、先進運転支援システムの搭載を前提とした設計により、家族を乗せて走るミニバンとしての信頼性が大きく高められています。新プラットフォームは、低重心化と高剛性化を実現し、ミニバンの弱点とされてきた操縦安定性を向上させており、特にe-POWERシステムとの組み合わせにより、バッテリーやモーターなどの重量物を最適に配置することで、理想的な前後重量配分を実現しています。
発売時期については2026年が予定されており、詳細なスペックや装備内容、そして価格については今後正式に発表される見込みです。プレミアムミニバン市場において、トヨタ・アルファードやヴェルファイアといった強力なライバルに対抗できる競争力のある価格設定が期待されています。
日産の電気自動車戦略
新型エルグランドに加えて、日産は軽自動車から大型SUVまで、国内外の多彩なモデルを展示しています。電気自動車については、既存のリーフやアリアに加えて、新たに2つのEVモデルが注目を集めています。
N7は2025年4月に中国市場で発売され、好調な販売実績を記録している電気自動車です。中国市場向けに開発されたこのモデルは、現地のニーズに合わせた仕様となっており、先進的なデザインと充実した装備が特徴です。日本での展示により、日産のグローバルEV戦略における重要なモデルであることが明確になります。
もう一つの注目モデルが、ヨーロッパ市場向けに開発された新型マイクラの電気自動車版です。マイクラは欧州で長年にわたり人気を博しているコンパクトカーですが、電動化により新たな魅力が加わることになります。欧州の厳しい環境規制に対応しながら、都市部での使い勝手の良さとスタイリッシュなデザインを兼ね備えたモデルとして期待されています。
日産はまた、新型リーフを展示し、78kWhの大容量バッテリーを搭載することで、WLTCモードで最大702kmという驚異的な航続距離を実現しています。これは従来のリーフから大幅に向上した数値であり、電気自動車に対する「航続距離への不安」という課題に対する明確な解答となっています。長距離移動が可能となることで、電気自動車の利用シーンが大きく広がることが期待されます。
さらに日産は、刷新されたアリア NEOと新しい軽量EVサクラ スポーツも展示しています。アリア NEOは、日産の最新電動化技術とインテリジェント技術を結集したモデルであり、より洗練されたデザインと先進的な機能を備えています。サクラ スポーツは、軽自動車サイズの電気自動車でありながらスポーティな走りを楽しめるモデルとして、新しいEVの可能性を示しています。
日産のモータースポーツとエネルギーマネジメント
日産はモータースポーツの分野でも電動化を推進しており、フォーミュラEに積極的に参戦しています。今回のショーでは、2024/2025シーズン(シーズン11)でドライバーズチャンピオンシップを獲得したオリバー・ローランド選手が駆ったマシンが展示されています。このマシンは、日産の電動化技術の粋を集めた高性能EVであり、レース活動を通じて培われた技術が市販車にもフィードバックされることで、より優れた電気自動車の開発につながっています。
日産はNISSAN ENERGYブースを設置し、EVを活用したエネルギーマネジメントサービスを提案しています。これは単に電気自動車を移動手段として使うだけでなく、家庭や地域のエネルギーシステムの一部として活用する、V2H(Vehicle to Home)やV2G(Vehicle to Grid)といった概念を具現化するものです。電気自動車は大容量のバッテリーを搭載しているため、災害時の非常用電源として、あるいは電力需給の調整に活用することができます。こうした新しい価値提案は、電気自動車の普及をさらに加速させる可能性を秘めています。
ホンダの革新:Honda 0シリーズSUVプロトタイプ
ホンダもまた、ジャパンモビリティショー2025において、革新的な技術と独創的なデザインを備えた複数のモデルを世界初公開しました。その中核となるのが、Honda 0(ゼロ)シリーズの新型SUVプロトタイプです。
Honda 0シリーズは、ホンダが推進する次世代EV戦略の中核を担うシリーズであり、このSUVプロトタイプは、ホンダが追求する走る喜びを電動化時代においても実現することを目指して開発されています。先進的なデザインと高い走行性能が特徴であり、専用設計により電気自動車としての性能を最大限に引き出すことを可能にしています。
Honda 0シリーズの開発コンセプトは、「薄い、軽い、賢い」という三つのキーワードに集約されています。この思想は、電気自動車の課題とされる重量増加やスペース効率の問題に対する、ホンダなりの解答を示すものです。
「薄い」とは、車体の無駄な部分を徹底的に削ぎ落とし、スリムで洗練されたデザインを実現することを意味します。電気自動車は大容量バッテリーを搭載する必要があるため、どうしても車高が高くなりがちですが、ホンダは独自の技術により、この課題を克服しようとしています。
「軽い」は、文字通り車両重量の軽量化を追求することです。電気自動車の航続距離を延ばし、エネルギー効率を高めるためには、軽量化が極めて重要です。ホンダは材料の選定から構造設計まで、あらゆる面で軽量化に取り組んでいます。
「賢い」とは、先進的な電子制御技術や人工知能を活用し、ドライバーの意図を的確に読み取って応答する、インテリジェントな車両を実現することを指します。単に電動化するだけでなく、デジタル技術を最大限に活用することで、新しい価値を創造しようとしています。
今回世界初公開されたSUVプロトタイプは、Honda 0シリーズの第一弾モデルとして、ミッドサイズSUVのセグメントに投入されます。SUVは世界的に人気の高いカテゴリーであり、特に北米市場や中国市場では高い需要があります。ホンダはこのセグメントに電気自動車を投入することで、グローバル市場での競争力強化を図ります。
薄い、軽い、賢いのアプローチをSUVに適用することで、従来のSUVが抱えていた課題を解決します。広々とした室内空間と開放的な視界を実現しながら、重量増加を抑え、優れた走行性能と高い自由度を提供します。バッテリーやモーターなどのEV専用コンポーネントを最適に配置することで、低重心化と理想的な重量配分を達成し、SUVでありながらスポーティな走りを楽しめる車両を目指しています。
Honda 0 SaloonとEV専用アーキテクチャー
Honda 0シリーズには、すでにフラッグシップセダンモデルであるHonda 0 Saloonが発表されており、今回のSUVプロトタイプはこのサルーンと並ぶ重要なモデルとして位置づけられています。サルーンが洗練された都市型のライフスタイルを提案するのに対し、SUVはより広範なユーザー層とさまざまな使用シーンに対応することを目指しています。
両モデルは同じEV専用アーキテクチャーを共有しながら、それぞれのボディタイプに最適化された設計が施されています。ホンダは0シリーズの価値をより多くの顧客に届けるため、複数のボディバリエーションを展開する計画であり、今回のSUVプロトタイプはその戦略の重要な一歩となります。
Honda 0シリーズは、新たに開発されたEV専用アーキテクチャーをベースとしています。従来のガソリン車をベースにした電動化ではなく、最初から電気自動車として設計することで、EVの持つポテンシャルを最大限に引き出すことができます。
EV専用設計により、フロアを低く平らにすることが可能となり、室内空間の広さと快適性が大幅に向上します。また、重量物であるバッテリーを車体の中心低い位置に配置することで、低重心化を実現し、優れた操縦安定性とハンドリング性能を実現します。さらに、エンジンやトランスミッションといった大型の機械部品が不要になることで、デザインの自由度が大きく高まります。ホンダはこの利点を活かし、従来の自動車の常識にとらわれない、革新的なデザインとパッケージングを実現しようとしています。
Honda 0シリーズのSUVプロトタイプについて、具体的な市場投入時期は現時点で明らかにされていませんが、ホンダは2030年までに電動車の販売比率を大幅に引き上げる計画を掲げており、0シリーズはその中核を担うモデルラインとなります。
ホンダの小型EVと電動バイク
ホンダは、小型EVプロトタイプも世界初公開しました。このモデルは、ホンダらしいFUN(楽しさ)を追求しながら、使いやすさとホンダ独自の走る喜びを高次元でバランスさせることをコンセプトとしています。
コンパクトなボディサイズながら、電気自動車ならではのクリーンでパワフルな走りを実現し、特に都市部での日常使いに適した設計となっています。環境性能と運転の楽しさを両立させることで、幅広いユーザー層にEVの魅力を伝えることを目指しています。小型EVは、特に若年層や都市居住者にとって、手頃な価格で電動モビリティを体験できる入門モデルとして重要な位置づけにあります。
ホンダは四輪車だけでなく、二輪車の分野でも電動化を推進しています。今回のショーでは、従来にない新しいアプローチによる電動バイクのコンセプトモデルが世界初公開されました。このモデルは、驚きや興奮、そして新しい体験を提供することを目指して開発されており、ホンダの二輪車開発における革新性を示すものとなっています。
電動バイクは、静粛性と瞬時のトルク発生という電動ならではの特性を活かしながら、バイク本来の走る楽しさを損なわないバランスが求められます。ホンダのコンセプトモデルは、こうした課題に対する一つの解答を示すものとして注目されています。
ホンダN-ONE e:と新型プレリュード
2025年9月12日に発売されたN-ONE e:も展示されています。このモデルは、日本市場のEVニーズに応えるために開発されたコンパクトな電気自動車で、小さなボディながら広々とした室内空間を実現しています。クリーンでパワフルなEV走行と、日常使いでの利便性を高いレベルで両立させたモデルとして、すでに市場で好評を得ています。
軽自動車規格をベースとしながら電動化を実現したN-ONE e:は、都市部での使い勝手の良さと環境性能を兼ね備えており、日本の交通事情に最適化されたEVとして位置づけられています。充電インフラが整備されつつある日本において、日常の買い物や通勤といった用途に最適なモデルとして人気を集めています。
ホンダの電動化戦略を象徴するもう一つのモデルが新型プレリュードです。このモデルは、進化したホンダのe:HEVハイブリッドシステムを搭載し、電動化時代における新しいスペシャルティスポーツカーとして開発されています。
プレリュードは、かつてホンダのスポーツカーラインナップの中核を担っていた名車であり、その名を冠した新型モデルの登場は多くのホンダファンから期待されています。e:HEVシステムの採用により、環境性能とスポーツ性能を高次元で両立させ、走る楽しさと社会的責任を同時に追求するモデルとなっています。電動化時代においても、ホンダらしいスポーティな走りを楽しめる車として、若者からベテランドライバーまで幅広い層にアピールするモデルとなることが期待されています。
その他の注目メーカーと技術展示
マツダもジャパンモビリティショー2025において、同社が描く世界観を具現化したビジョンモデルを世界初公開しました。マツダは人馬一体の走りを追求し続けるメーカーとして知られており、電動化時代においてもこの哲学を貫くモデルを提示することが期待されています。マツダ独自のアプローチは、単なる電動化ではなく、ドライバーと車との一体感を重視した設計思想にあり、電気自動車やハイブリッド車においても運転する楽しさを損なわないことを目指しています。
ジャパンモビリティショー2025では、自動運転技術も重要なテーマとなっています。完全自動運転の実現はまだ先のことですが、段階的に技術が進化しており、今回のショーでは実用化に近づいた技術が数多く展示されています。
日野自動車は、燃料電池大型トラック日野プロフィア Z FCVを展示しています。このトラックには、高速道路の幹線輸送を想定したレベル4自動運転コンセプト機器が搭載されています。レベル4自動運転とは、特定の条件下であれば人間の介入なしに完全に自動で運転できる技術です。長距離トラック輸送は運転者不足が深刻な問題となっており、自動運転技術の導入により、物流の効率化と運転者の負担軽減が期待されています。
日産は、AutoDJなどの自動運転技術を搭載した実験車両を体験できるエリアを設置しています。AutoDJは日産が開発している先進的な運転支援システムであり、将来的には完全自動運転につながる技術です。来場者が実際に体験することで、自動運転技術がどの程度進化しているのか、そして実用化までにどのような課題が残されているのかを肌で感じることができます。
Tokyo Future Tour 2035という展示では、2035年の東京の姿が描かれています。電動化と自動運転技術が普及した未来において、エネルギーインフラ、通信インフラ、都市計画がどのように進化するのかが提示されます。自動運転車両が一般化すれば、駐車場の必要性が減少し、都市空間の使い方が根本的に変わる可能性があります。
コネクテッド技術とモビリティの未来
自動車と通信、そしてAIを融合させたコネクテッド技術は、ジャパンモビリティショー2025における重要なテーマの一つです。5G/6Gといった次世代通信技術を基盤とした車車間通信、自動運転支援AI、遠隔監視技術などが披露されています。
コネクテッド技術により、車両は単独で動作するのではなく、他の車両やインフラと常に情報を交換しながら走行することが可能になります。例えば、前方で事故が発生した場合、その情報が瞬時に周辺の車両に伝達され、自動的に減速したり迂回ルートを選択したりすることができます。また、信号機や道路標識といったインフラとも連携し、より効率的で安全な交通流を実現することが可能になります。
AIを活用した運転支援技術も急速に進化しています。ドライバーの運転傾向を学習し、個々のドライバーに最適化された支援を提供することや、疲労や眠気を検知して警告を発することなど、安全性を高めるさまざまな機能が開発されています。これらの技術は、交通事故の削減に大きく貢献することが期待されており、特に高齢ドライバーや運転経験の浅いドライバーにとって心強い味方となります。
遠隔監視技術は、特に商用車や物流分野で重要性が高まっています。車両の状態をリアルタイムで監視し、故障の予兆を検知してメンテナンスを行うことで、ダウンタイムを最小化できます。また、運行管理の効率化や、燃費の向上にもつながります。物流業界は人手不足と効率化の要求が高まっており、こうしたテクノロジーの導入が業界の課題解決に貢献することが期待されています。
モビリティショーが示す未来の姿
ジャパンモビリティショー2025は、単なる自動車の展示会にとどまらず、モビリティの未来全体を体験できる総合的なイベントとなっています。500社を超える参加企業により、自動車メーカーだけでなく、関連技術やサービスを提供する企業も多数参加し、移動の未来がどのように変わっていくのかを包括的に示す場となっています。
電動化、自動運転、コネクテッド技術など、自動車産業を取り巻く技術革新は急速に進展しており、各メーカーはこうした変化に対応した新しいモビリティの形を提案しています。日産やホンダといった日本を代表する自動車メーカーが、それぞれの強みを活かした製品やコンセプトを披露することで、日本の自動車産業の技術力と創造性を世界に向けて発信する機会となります。
136の出展者が参加するこの多様性こそが、ジャパンモビリティショーの大きな特徴です。移動の未来は単独の企業や業界だけで実現できるものではなく、さまざまな分野の技術と知見を統合することで初めて達成されます。異なるバックグラウンドを持つ企業が一堂に会することで、新たなコラボレーションの可能性が生まれ、イノベーションが加速することが期待されています。
特に注目すべきは、従来の自動車メーカーだけでなく、IT企業やスタートアップ企業も多数参加していることです。自動車産業は今や、機械工学だけでなく、ソフトウェア、AI、通信技術など幅広い分野の知識が必要とされる総合産業へと変貌しつつあります。こうした異業種の参入により、これまでにない斬新なアイデアや技術が生まれることが期待されています。
電動化時代における日産とホンダの戦略
日産とホンダは、それぞれ異なるアプローチで電動化時代に挑んでいます。日産はe-POWERという独自のハイブリッドシステムを軸に、段階的に電動化を進めています。e-POWERは、エンジンを発電専用とし、駆動は完全にモーターで行うという独特のシステムであり、EVのような走行フィーリングとガソリン車の利便性を両立させています。新型エルグランドへの第3世代e-POWERの搭載は、この戦略の延長線上にあります。
一方、ホンダはEV専用プラットフォームによる本格的な電気自動車の開発に注力しています。Honda 0シリーズは、ホンダが描く電動化時代の理想を体現したモデルであり、薄い、軽い、賢いという明確なコンセプトのもとで開発されています。ホンダはまた、e:HEVハイブリッドシステムも並行して展開しており、市場のニーズに応じて最適なパワートレインを提供する戦略を取っています。
両社に共通するのは、電動化を単なる環境対応ではなく、新しい価値創造の機会と捉えていることです。モーターならではの力強い加速、静粛性、そして先進的なデジタル技術との融合により、これまでにない運転体験を提供しようとしています。同時に、日本の自動車メーカーとしての強みである品質の高さ、信頼性、細部へのこだわりを電動化時代においても維持し、グローバル市場での競争力を確保しようとしています。
まとめ:モビリティショー2025が示す未来への道
ジャパンモビリティショー2025で発表された日産とホンダのコンセプトカーや注目車種は、自動車産業の大きな転換期を象徴するものです。日産の新型エルグランドは、16年ぶりのフルモデルチェンジという節目に、第3世代e-POWERという最新技術を搭載することで、プレミアムミニバン市場に新風を吹き込もうとしています。一方、ホンダのHonda 0シリーズSUVプロトタイプは、薄い、軽い、賢いという独創的なコンセプトのもと、電動化時代における新しいSUVの姿を提示しています。
電動化、自動運転、コネクテッド技術という3つの大きな潮流の中で、各メーカーは独自の技術と哲学に基づいた製品を開発しています。日産は実用性と環境性能を重視したe-POWER戦略を、ホンダは走る楽しさを追求したEV専用プラットフォーム戦略を展開しており、それぞれのアプローチが市場でどのように評価されるのか、今後の動向が注目されます。
2025年10月31日から11月9日まで一般公開されるジャパンモビリティショー2025は、自動車ファンだけでなく、モビリティの未来に興味を持つすべての人々にとって見逃せないイベントとなっています。実際に展示車両を見て、触れて、体験することで、10年後、20年後の移動の姿を実感することができるでしょう。日産とホンダが描くモビリティの未来は、私たちの生活をより便利で、より快適で、より環境に優しいものへと変えていく可能性を秘めています。

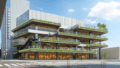

コメント