2025年の税制改正によって新しく導入された特定親族特別控除は、19歳から23歳未満の親族を扶養する方にとって非常に重要な制度です。この制度では対象年齢の判定が重要なポイントとなり、特に誕生日がいつなのかによって控除が受けられるかどうかが決まります。従来の103万円の壁が大幅に緩和され、大学生などのお子様がアルバイトをする際の収入制限が188万円まで拡大されたことで、多くのご家庭にとって家計の負担軽減につながる可能性があります。しかし、この制度を正しく活用するためには、年齢判定の特殊なルールを理解しておく必要があります。特に1月1日生まれの方は税法上の年齢計算において特別な扱いを受けるため、12月31日時点での年齢判定に注意が必要です。本記事では、特定親族特別控除における対象年齢の判定方法、19歳と23歳の境界線となる誕生日の取り扱い、そして具体的な控除額や手続きの方法について、わかりやすく詳しく解説していきます。

特定親族特別控除の基本的な仕組み
特定親族特別控除は、令和7年度の税制改正で新たに創設された所得控除の制度です。この制度が登場した背景には、深刻化する人手不足の問題と、学生などが収入を抑える「働き控え」の問題がありました。従来の扶養控除制度では、扶養される親族の年間所得が48万円を超える、つまり給与収入で103万円を超えると、扶養控除が一切受けられなくなっていました。そのため、大学生がアルバイトをする際に103万円を超えないように勤務時間を調整するケースが多く見られ、これが労働力の確保を困難にしていたのです。
2025年の改正によって、まず扶養親族の所得要件が48万円以下から58万円以下に引き上げられました。これは給与収入に換算すると103万円から123万円への変更を意味します。さらに画期的なのは、特定親族特別控除の創設により、扶養される親族の所得が58万円を超えても123万円以下、つまり給与収入で123万円超から188万円以下の範囲であれば、段階的に控除を受けられるようになった点です。
この制度の対象となるのは、その年の12月31日時点で19歳以上23歳未満の親族です。年齢範囲が限定されているのは、この年代が主に大学や専門学校に通う学生世代であり、アルバイト収入による働き控えが特に問題となっていたためです。ただし、実際に学生である必要はなく、年齢と所得要件さえ満たせば控除の対象となります。
控除額については、特定親族の所得金額によって変わります。所得が58万円以下の場合は従来通りの特定扶養親族控除が適用され、所得税で63万円、住民税で45万円の控除を受けることができます。所得が58万円を超えて123万円以下の場合には、新設された特定親族特別控除が適用され、所得金額に応じて段階的に控除額が減少していく仕組みとなっています。
対象年齢の判定における基本ルール
特定親族特別控除の適用を受けるためには、扶養する親族が対象年齢に該当することが必須条件です。この年齢判定には明確なルールがあり、それを理解することが制度を正しく活用する第一歩となります。
年齢の判定基準日は、その年の12月31日と定められています。つまり、2025年分の所得税について特定親族特別控除を適用する場合、2025年12月31日時点での年齢で判定することになります。この基準日方式により、年の途中で誕生日を迎えて年齢が変わった場合でも、12月31日時点の年齢のみが判定に使われます。
たとえば、年末調整の書類を提出する11月時点ではまだ18歳であっても、その年の12月31日までに19歳の誕生日を迎えるのであれば、その年は特定親族として認められます。逆に、12月31日時点で既に23歳になっている場合は、その年の1月から11月まではずっと22歳だったとしても、その年については特定親族の要件を満たさないことになります。
この年齢判定の考え方は、従来からある扶養親族の年齢判定と同じルールです。所得税法では、年齢に関する判定は全て12月31日の現況によって行うという原則があり、特定親族特別控除もこの原則に従っています。したがって、扶養控除の年齢判定に慣れている方であれば、同じ感覚で特定親族の年齢判定も行うことができます。
ただし、ここで注意が必要なのは、税法上の年齢計算には一般的な感覚とは異なる特殊なルールがあるという点です。このルールを理解していないと、特に誕生日が年の境目にある方について、誤った判定をしてしまう可能性があります。
誕生日と年齢計算の特殊ルール
税法における年齢計算では、年齢計算ニ関スル法律および民法第143条に基づいた特殊な方法が用いられます。この方法は「年齢計算の前日主義」と呼ばれ、多くの人にとって直感的ではない仕組みとなっています。
前日主義の基本的な考え方は、人は誕生日の前日が終了する時、つまり誕生日前日の午後12時、深夜0時の時点で満年齢に達するというものです。これは明治時代から続く日本の法律上の原則で、期間計算における初日不算入の原則から導かれています。
具体的な例で説明すると、1月2日生まれの方の場合、1月2日が誕生日ですが、税法上は1月1日の午後12時、つまり1月1日が終わって1月2日に日付が変わる瞬間に年を一つとることになります。この場合は一般的な感覚とほぼ同じなので、特に違和感はないでしょう。
しかし、1月1日生まれの方の場合は注意が必要です。1月1日が誕生日の方は、その前日である12月31日の午後12時、つまり12月31日が終わる瞬間に年を一つとることになります。これは非常に重要なポイントで、1月1日生まれの方は実質的に12月31日に年齢が加算されるのです。
この前日主義のルールが特定親族特別控除の年齢判定に与える影響は大きなものがあります。特に23歳の上限を判定する際には、1月1日生まれかそれ以外かで結果が変わってきます。
2003年1月1日生まれの方を例に考えてみましょう。この方は2025年12月31日時点での年齢判定において、前日主義により2025年12月31日の深夜0時に23歳に達することになります。したがって、2025年12月31日時点では既に23歳と判定され、19歳以上23歳未満という特定親族の年齢要件を満たさなくなります。
一方、2003年1月2日生まれの方の場合は、2026年1月1日の深夜0時に23歳に達することになるため、2025年12月31日時点ではまだ22歳であり、特定親族の年齢要件を満たします。このように、わずか1日の誕生日の違いが、税制上の取り扱いに決定的な影響を与える可能性があるのです。
同様に、19歳の下限についても前日主義が適用されます。2007年1月1日生まれの方は、2025年12月31日の深夜0時に19歳に達するため、2025年12月31日時点では19歳と判定され、特定親族の年齢要件を満たします。しかし、2007年1月2日生まれの方は、2025年12月31日時点ではまだ18歳であり、要件を満たしません。
2025年における対象生年月日の範囲
2025年度の所得税において特定親族特別控除の対象となるのは、前述の年齢計算ルールを適用すると、平成15年1月2日から平成19年1月1日までに生まれた方となります。この範囲について、上限と下限それぞれの判定根拠を詳しく見ていきましょう。
まず、年齢の上限となる23歳未満の判定についてです。平成15年、つまり2003年1月2日生まれの方は、前日主義により2026年1月1日に23歳に達します。そのため、2025年12月31日時点ではまだ22歳であり、23歳未満の要件を満たします。これが対象となる最年長の生年月日です。
これより1日でも早い、平成15年1月1日生まれの方はどうでしょうか。この方は前日主義により2025年12月31日に23歳に達してしまうため、2025年12月31日時点では既に23歳となり、23歳未満という要件を満たしません。したがって、平成15年1月1日生まれの方は2025年度の特定親族特別控除の対象外となります。
次に、年齢の下限となる19歳以上の判定についてです。平成19年、つまり2007年1月1日生まれの方は、前日主義により2025年12月31日に19歳に達します。税法上は12月31日の深夜0時に19歳に達するため、2025年12月31日時点では19歳と判定され、19歳以上の要件を満たします。これが対象となる最年少の生年月日です。
これより1日でも遅い、平成19年1月2日生まれの方の場合はどうなるでしょうか。この方は2026年1月1日に19歳に達するため、2025年12月31日時点ではまだ18歳であり、19歳以上という要件を満たしません。したがって、平成19年1月2日生まれの方は2025年度の特定親族特別控除の対象外となります。
このように、特定親族の対象年齢判定においては、1月1日生まれと1月2日生まれの違いが境界線を決める決定的な要素となっています。年末調整や確定申告の際には、扶養する親族の生年月日を正確に確認し、この境界線に該当しないかを慎重にチェックする必要があります。
具体的な年齢判定のケーススタディ
実際の年齢判定がどのように行われるのか、様々な生年月日のケースを見ながら理解を深めていきましょう。
まず、平成15年4月1日生まれの方のケースです。この方は2025年12月31日時点で22歳となります。23歳の誕生日は2026年3月31日ですが、前日主義により実際に23歳に達するのは2026年3月30日の深夜0時です。いずれにしても2025年12月31日時点では22歳であり、19歳以上23歳未満に該当するため、特定親族の対象となります。
平成18年10月15日生まれの方のケースを見てみましょう。この方は2025年10月14日の深夜0時に19歳に達し、2025年12月31日時点では19歳です。したがって19歳以上23歳未満に該当し、特定親族の対象となります。
平成14年12月31日生まれの方はどうでしょうか。この方は前日主義により2025年12月30日の深夜0時に23歳に達します。そのため2025年12月31日時点では既に23歳であり、23歳以上となってしまうため、特定親族の対象外となります。この例からも、12月生まれの方で23歳になる方は、特に注意が必要だとわかります。
早生まれの方のケースも重要です。平成18年3月15日生まれの方は、2025年3月14日の深夜0時に19歳に達し、2025年12月31日時点では19歳です。したがって19歳以上23歳未満に該当し、特定親族の対象となります。早生まれとは1月から3月生まれの方を指しますが、税法上の年齢判定では生まれた年のみが重要であり、早生まれかどうかは直接的には関係ありません。
ただし、早生まれの方の場合、学年と年齢が一致しないケースがあることに注意が必要です。たとえば大学1年生であっても、誕生日によっては19歳に達していない場合があります。そのような場合、特定扶養親族控除ではなく、一般の控除対象扶養親族の控除が適用されることになり、控除額が所得税で63万円から38万円に減少してしまいます。
平成16年7月20日生まれの方のケースも見てみましょう。この方は2025年12月31日時点で21歳であり、明確に19歳以上23歳未満の範囲内にあるため、特定親族の対象となります。このように、1月1日や1月2日といった境界線から離れた誕生日の方は、判定に迷うことは少ないでしょう。
特定親族特別控除の控除額の詳細
特定親族特別控除における控除額は、特定親族の合計所得金額に応じて段階的に設定されており、所得が増えても急激に控除がゼロになるのではなく、緩やかに減少していく仕組みとなっています。
特定親族の合計所得金額が58万円以下の場合は、特定親族特別控除ではなく、従来からある特定扶養親族控除が適用されます。この場合の控除額は所得税で63万円、住民税で45万円と非常に大きく、扶養控除の中でも最も控除額が大きい区分となっています。給与収入で考えると、123万円以下であればこの満額の控除を受けることができます。
特定親族の合計所得金額が58万円を超えて123万円以下の場合に、新設された特定親族特別控除が適用されます。この範囲では、所得金額が増えるにつれて控除額が段階的に減少していきます。給与収入で123万円を超えた場合でも、188万円までは何らかの控除が受けられるという点が、この制度の最大のメリットです。
具体的な控除額の目安を給与収入で見ていくと、給与収入が130万円程度の場合、所得税の控除額は約63万円とほぼ満額が維持されます。給与収入が150万円程度になると、控除額は約58万円程度に減少します。給与収入が160万円程度では控除額は約51万円、170万円程度では約31万円となり、徐々に控除額が減少していきます。そして給与収入が188万円を超えると、控除額は0円となり、控除を受けることができなくなります。
この段階的な控除の仕組みにより、扶養される親族のアルバイト収入が少し増えたからといって、急に控除が受けられなくなって税負担が急増するという事態を避けることができます。従来の制度では103万円を1円でも超えると控除がゼロになっていたため、年末に慌ててシフトを減らすといった働き控えが発生していましたが、特定親族特別控除ではそのような心配が大幅に軽減されます。
なお、所得税と住民税では控除額が異なる点にも注意が必要です。住民税の控除額は所得税よりも低く設定されており、特定扶養親族控除の場合でも所得税が63万円に対して住民税は45万円と、18万円の差があります。これは住民税が地域社会の会費的な性格を持つため、所得税よりも控除額を抑える考え方に基づいています。
年末調整での具体的な手続き方法
特定親族特別控除の適用を受けるためには、年末調整または確定申告で所定の手続きを行う必要があります。ここでは年末調整での手続きについて詳しく説明します。
2025年分の年末調整からは、新しい様式の申告書を使用します。正式な名称は非常に長く「給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 給与所得者の特定親族特別控除申告書 兼 所得金額調整控除申告書」となっており、特定親族特別控除申告書の欄が新たに追加されています。
記入方法について順を追って説明します。まず、特定親族の氏名を正確に記入します。続いて個人番号、いわゆるマイナンバーを記入しますが、既に会社に提出済みの場合は省略することができます。次に続柄を記入します。子、弟、妹といった続柄を正確に書きましょう。
そして重要なのが生年月日の記入です。和暦でも西暦でも構いませんが、年齢判定に直結する情報ですので、間違いのないように記入する必要があります。特に前述のように1月1日生まれと1月2日生まれでは判定が変わるケースがあるため、日付まで正確に記入しましょう。
最後に、特定親族の年間の合計所得金額を記入します。給与収入のみの場合は、年間の給与収入から給与所得控除65万円を差し引いた金額が合計所得金額となります。たとえば年間給与収入が150万円であれば、150万円から65万円を引いた85万円が合計所得金額です。
年末調整時点で正確な金額が分からない場合は、見込み額で記入することになります。12月の給与やボーナスがまだ支払われていない11月時点で年末調整書類を提出する場合、12月分は見込みで計算して記入します。後日、実際の金額が見込みと大きく異なることが判明した場合は、確定申告で調整することも可能です。
複数の特定親族がいる場合は、それぞれについて記入します。たとえば20歳の子と21歳の子がいる場合、両方とも要件を満たしていれば、両方について控除を受けることができます。
適用時期についても理解しておく必要があります。年末調整と確定申告は令和7年分、つまり2025年分から特定親族特別控除を適用できます。一方、給与や賞与などからの源泉徴収については令和8年分、つまり2026年分からの適用となります。2025年中の給与からの源泉徴収は従来の基準で行われ、年末調整で新しい基準に調整されることになります。
健康保険の被扶養者認定との重要な関係
税法上の特定親族特別控除の創設に伴い、健康保険の被扶養者認定の基準も変更されました。この変更は税制改正との整合性を図る観点から行われたもので、税制と社会保険制度の両面から働き控えの解消を目指しています。
2025年10月1日以降、健康保険の被扶養者認定において、19歳以上23歳未満の方、ただし配偶者を除く方の年間収入要件が、従来の130万円未満から150万円未満に緩和されました。この変更により、大学生などがアルバイトで月12万円程度稼いでも、健康保険の被扶養者として親の健康保険に加入し続けることができるようになりました。
対象者は被保険者の配偶者を除く19歳以上23歳未満の親族です。学生であるかどうかは問われず、年齢要件のみで判定されます。この点は税法の特定親族特別控除と同じ考え方です。
年齢判定の基準も税法と同様で、扶養認定日が属する年の12月31日時点の年齢で判定されます。たとえば2025年11月に19歳の誕生日を迎える方は、2025年は19歳以上として扱われ、年収150万円未満が基準になります。
既に扶養認定されている方の取り扱いについても確認しておきましょう。2025年9月30日以前から既に健康保険の被扶養者として認定されている19歳以上23歳未満の方についても、2025年10月1日以降は自動的に年収150万円未満が基準となります。特に手続きは不要で、自動的に新しい基準が適用されます。
この改正の背景には、税制改正において特定扶養控除の見直しが行われることになったことを踏まえ、税制改正の趣旨との整合性を図る必要があったという事情があります。税制では188万円まで段階的に控除が受けられるのに、健康保険では130万円で被扶養者から外れてしまうと、制度間で矛盾が生じてしまうためです。
ただし、いくつかの注意点があります。まず、この150万円の基準は配偶者には適用されません。配偶者の場合は従来通り130万円未満が基準となります。これは配偶者には別途配偶者控除という制度があるためです。また、収入要件以外の認定基準、たとえば生計維持関係や同居要件などには変更はありません。
そして重要なのは、19歳以上23歳未満の方が年収150万円以上になると、健康保険の被扶養者から外れ、自身で国民健康保険に加入するか、勤務先の健康保険に加入する必要があるという点です。税制では188万円まで控除が受けられますが、健康保険では150万円が上限ですので、この点は混同しないように注意しましょう。
よくある質問と実務上の注意点
特定親族特別控除について、実務上よく質問される事項や注意すべきポイントをまとめていきます。
年の途中で19歳または23歳になる場合について、いつから特定親族として扱われるのかという質問がよくあります。答えは、年齢の判定はその年の12月31日時点で行われるため、年の途中で19歳になった場合でも、その年の初めから特定親族として扱われるわけではなく、12月31日時点で19歳以上23歳未満であれば、その年全体について特定親族として扱われるということです。
学生であることは特定親族の要件かという質問もよくあります。答えは、学生であることは要件ではなく、19歳以上23歳未満であれば学生でなくても特定親族に該当する可能性があります。ただし所得要件は満たす必要があります。
アルバイト収入以外に奨学金がある場合はどうなるかという質問もあります。給付型奨学金で返還不要のものには、課税対象となるものと非課税のものがあります。貸与型奨学金で返還が必要なものは所得には含まれません。課税対象となる奨学金がある場合は、アルバイト収入と合算して所得を計算する必要があります。
複数のアルバイトをしている場合の収入計算についても注意が必要です。複数のアルバイト先がある場合は、すべてのアルバイト先からの給与収入を合算して計算します。各アルバイト先から受け取る源泉徴収票を基に、年間の合計給与収入を算出してください。
年の途中で就職した場合はどうなるでしょうか。年の途中で就職し給与収入が大幅に増加した場合、その年の合計所得金額が123万円を超える可能性があります。この場合、特定親族特別控除の対象外となるか、控除額が減少する可能性があります。就職が決まった時点で、その年の見込み所得を計算し、必要に応じて年末調整または確定申告で調整してください。
特定親族が複数いる場合はどうなるかという質問もあります。特定親族が複数いる場合、それぞれについて要件を満たしていれば、それぞれについて控除を受けることができます。年末調整の申告書には複数の特定親族を記入できる欄が設けられています。
途中で親族の収入が増えて所得要件を超えてしまった場合については、年末調整では見込み額で申告しますが、最終的には12月31日時点での実際の所得金額で判定されます。年末調整で申告した金額と実際の金額に差がある場合は、確定申告で調整する必要があります。所得要件を超えた場合、受けた控除を返還しなければならない可能性があります。
年末調整を忘れた場合や年末調整後に誤りに気づいた場合はどうすればよいでしょうか。年末調整で特定親族特別控除の申告を忘れた場合や、申告内容に誤りがあった場合は、翌年の確定申告期間、通常2月16日から3月15日に確定申告を行うことで控除を受けることができます。また、過去の年分についても原則として5年間は遡って確定申告、還付申告を行うことができます。
2025年税制改正の全体像と今後の展望
特定親族特別控除の創設は、令和7年度税制改正の一環として行われましたが、この税制改正では他にも多くの重要な変更が同時に実施されました。これらの改正を総合的に理解することで、特定親族特別控除の位置づけがより明確になります。
2025年の税制改正における主な内容としては、まず基礎控除の引き上げがあります。所得税の基礎控除が48万円から58万円に、住民税の基礎控除が43万円から53万円に引き上げられました。これによりすべての納税者が10万円分多く控除を受けられることになり、減税効果があります。
次に給与所得控除の最低額の引き上げも実施されました。給与所得控除の最低額が55万円から65万円に引き上げられたことで、給与収入のある方全員が10万円分多く控除を受けられることになりました。
そして扶養親族の所得要件の変更も重要です。扶養親族および同一生計配偶者の合計所得金額の要件が48万円以下から58万円以下に引き上げられ、給与収入で103万円以下だった基準が123万円以下に緩和されました。
さらに特定親族特別控除の創設により、扶養される親族の合計所得金額が58万円を超えても123万円以下であれば段階的に控除を受けることができるようになりました。
一方で、2024年に実施されていた定額減税は終了しました。2024年には1人あたり所得税3万円、住民税1万円の定額減税が実施されていましたが、2025年分からはこの定額減税はなくなり、代わりに上記のような恒久的な制度改正が行われました。
これらの改正は、いわゆる各種の壁の問題に対処し、就業調整を防止することを目的としています。特に人手不足が深刻化する中で、学生や主婦、主夫などが収入制限を気にせずに働けるようにすることが改正の主な狙いです。
施行時期については、原則として令和7年、2025年12月1日に施行され、令和7年分以後の所得税について適用されます。ただし源泉徴収については、令和8年、2026年1月1日以後に支払うべき給与等から新しい基準が適用されます。
今後の展望としては、この制度の効果や問題点が実際の運用を通じて明らかになっていくと考えられます。特に学生のアルバイト就労がどの程度増加するか、また企業の人手不足解消にどの程度貢献するかといった点が評価の対象となるでしょう。
将来的な所得要件の見直しの可能性もあります。現在の特定親族特別控除では合計所得金額123万円、給与収入188万円が上限とされていますが、今後の経済情勢や賃金水準の変化に応じて、この上限が見直される可能性があります。特に最低賃金の引き上げが継続的に行われている現状を考えると、将来的には更なる要件の緩和が検討される可能性もあります。
デジタル化への対応も進むでしょう。年末調整や確定申告の手続きについて、マイナンバーカードを活用した電子申告や、マイナポータルとの連携による自動入力などにより、特定親族特別控除の申告手続きも簡素化される可能性があります。
制度を最大限に活用するためのポイント
特定親族特別控除を最大限に活用するためには、いくつかの重要なポイントを押さえておく必要があります。
まず最も重要なのは、年齢判定を正確に行うことです。特定親族の生年月日を確認し、その年の12月31日時点で19歳以上23歳未満に該当するかを正確に判定しましょう。特に1月1日生まれの方や1月2日生まれの方は、前日主義により判定が変わる可能性があるため、慎重に確認する必要があります。
次に、所得金額を正確に把握することも重要です。特定親族の年間の合計所得金額が58万円以下か、58万円超123万円以下か、それとも123万円超かによって、適用される控除や控除額が変わります。複数のアルバイト先がある場合は、すべての収入を合算して計算することを忘れないようにしましょう。
年末調整の書類を確実に提出することも大切です。年末調整の申告書に特定親族の情報を正確に記入し、期限内に会社に提出しましょう。提出を忘れた場合は確定申告で対応できますが、手間がかかるため、年末調整で完結させる方が効率的です。
税制と健康保険の両面から考えることも重要なポイントです。税制では188万円まで段階的に控除が受けられますが、健康保険では150万円が被扶養者認定の上限です。特定親族の収入がこれらの金額を超える見込みがある場合は、税負担だけでなく健康保険の負担も含めて総合的に判断する必要があります。
制度の変更を継続的に確認することも大切です。税制は毎年のように改正が行われるため、最新の情報を国税庁のホームページや税務署、税理士などから入手するようにしましょう。特に控除額や所得要件が将来変更される可能性もあるため、定期的な確認が重要です。
これらのポイントを押さえて特定親族特別控除を適切に活用することで、扶養する側の納税者は税負担を軽減でき、扶養される側の親族は収入を気にせずに働くことができるようになります。この制度は多くの方々にメリットをもたらす重要な制度として、今後ますます活用されることが期待されています。


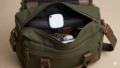
コメント