相続放棄は、故人の財産と債務を一切相続しないための重要な法的手続きです。多額の借金がある場合や相続トラブルを避けたい場合に有効な選択肢となりますが、家庭裁判所での正式な手続きが必要で、自己判断だけでは効力を持ちません。
近年、相続放棄の手続きを自分で行いたいと考える方が増えています。専門家に依頼すると数万円の費用がかかるため、費用を抑えたい方や、比較的シンプルなケースでは自分で手続きを進めることも可能です。
ただし、相続放棄には「自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内」という厳格な期限があり、一度受理されると原則として撤回できません。また、手続きに不備があると却下される可能性もあるため、事前の準備と正確な知識が不可欠です。
本記事では、相続放棄の手続きを自分で行う際の具体的な方法、必要書類、注意点、そして専門家に依頼すべきケースについて詳しく解説します。適切な判断をするための参考としてお役立てください。

Q1. 相続放棄の手続きを自分で行うことは可能?必要な条件と基本的な流れを教えて
はい、相続放棄の手続きは自分で行うことが可能です。ただし、家庭裁判所での正式な申述が必要で、いくつかの重要な条件と手順を守る必要があります。
相続放棄が可能な基本条件
相続放棄を行うためには、「自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内」という期限を守ることが最も重要です。この期間は「熟慮期間」と呼ばれ、被相続人が亡くなったことと自分が相続人であることの両方を知った時点から起算されます。
また、単純承認とみなされる行為を行っていないことも条件となります。預貯金の引き出しや不動産の売却、賃料の受け取りなど、相続財産を自分のために利用する行為を行った場合、相続放棄は認められません。
手続きの基本的な流れ
1. 相続財産の調査
まず、被相続人のプラス財産(預貯金、不動産、有価証券など)とマイナス財産(借金、ローン、未払い税金など)を正確に把握します。この調査結果に基づいて相続放棄の判断を行います。
2. 必要書類の準備
相続放棄申述書の作成と、戸籍謄本類などの必要書類を収集します。申述人と被相続人の関係により必要書類が異なるため、事前に家庭裁判所で確認することをお勧めします。
3. 家庭裁判所への申述
被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に、準備した書類一式を提出します。郵送での提出も可能ですが、書類に不備がないよう注意が必要です。
4. 家庭裁判所からの照会への回答
申述後、裁判所から「相続放棄照会書」が送られてきます。これは申述が本人の真意に基づくものか、法定単純承認に該当する行為がなかったかを確認するためのものです。指定期限内に適切に回答する必要があります。
5. 相続放棄申述受理通知書の受領
回答に問題がなければ、「相続放棄申述受理通知書」が郵送され、正式に相続放棄が認められます。この通知書は債権者への証明などで重要な書類となるため、大切に保管してください。
期間延長の可能性
財産調査に時間がかかる場合は、「相続の承認又は放棄の期間の伸長」の申立てにより、熟慮期間を延長できる場合があります。ただし、必ずしも認められるわけではないため、早めの対応が重要です。
Q2. 相続放棄を自分で手続きする場合の必要書類と費用はどのくらい?
相続放棄の手続きを自分で行う場合、相続人1人あたり約3,000円~5,000円程度の費用で済みます。専門家に依頼する場合と比べて大幅に費用を抑えることができます。
共通して必要な書類
すべての相続放棄で必要となる基本書類は以下の通りです。
相続放棄申述書は、家庭裁判所の窓口またはウェブサイトからダウンロードできます。申述人の情報、被相続人の情報、相続放棄の趣旨、放棄の理由などを正確に記載する必要があります。
被相続人の住民票除票または戸籍附票は、被相続人の最後の住所地を証明する書類です。住民票除票は住民票所在地の市区町村役場で、戸籍附票は本籍所在地の市区町村役場で取得します。
申述人の戸籍謄本は、申述人と被相続人の関係を示すために必要です。本籍地の市区町村役場で取得してください。
関係性別の追加必要書類
配偶者の場合は、被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本が必要です。同一戸籍に入っている場合は、申述人の戸籍謄本で兼ねることもあります。
子または孫(代襲相続人)の場合は、被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本に加え、代襲相続人の場合は被代襲者(本来の相続人)の死亡の記載のある戸籍謄本も必要です。
父母・祖父母(直系尊属)の場合は、被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本が必要になります。これは、被相続人に子や孫がいないことを証明するためです。
兄弟姉妹または甥・姪の場合は、最も多くの書類が必要となります。被相続人の出生から死亡までの全戸籍謄本、直系尊属の死亡の記載のある戸籍謄本など、収集が非常に大変になる傾向があります。
費用の詳細
実費として必要な費用は以下の通りです。
収入印紙代は申述人1人につき800円です。連絡用郵便切手代は約400円~500円(裁判所によって異なります)。
戸籍謄本類の取得費用は、住民票除票や戸籍附票が約300円、戸籍謄本が450円、除籍・改製原戸籍謄本が750円程度です。必要な戸籍の数により総額が変わりますが、一般的には1,000円~2,000円程度を見込んでおけば良いでしょう。
書類取得の注意点
戸籍謄本の取得には時間がかかる場合があります。特に「出生から死亡までの全戸籍謄本」が必要な場合、転居や転籍を繰り返していると複数の市区町村に請求する必要があり、数週間かかることもあります。
また、「戸籍抄本」や「一部事項証明書」は使用できません。必ず「戸籍謄本」または「全部事項証明書」を取得してください。
複数の相続人が相続放棄を申請する場合、共通する書類は1通で足りますが、申述書や収入印紙は各人分が必要です。
Q3. 相続放棄の3ヶ月期限を過ぎてしまった場合、自分で対処できる?
3ヶ月の期限を過ぎても、特別な事情があれば相続放棄が認められる可能性があります。ただし、期限後の相続放棄は非常に困難で、自分で対処するには相当な準備と法的知識が必要です。
期限後でも認められる可能性のあるケース
相続財産が全くないと信じていた場合や、借金の存在を後から知った場合など、相続財産の有無の調査が著しく困難な事情があった場合は、例外的に相続放棄が認められることがあります。
この場合、借金の存在を知った日から3ヶ月が新たな起算点となる可能性があります。ただし、単に「知らなかった」だけでは不十分で、「調査しても知り得なかった合理的な理由」が必要です。
上申書の重要性
期限後の相続放棄では、「上申書」の提出が実質的に必須となります。上申書は法律上の必須書類ではありませんが、裁判官に事情を説明し納得させるための重要な書類です。
上申書には、なぜ期限内に相続放棄できなかったのか、いつ借金の存在を知ったのか、どのような調査を行ったのかなどを具体的かつ詳細に記載する必要があります。
自分で対処する際の課題
法的な文書作成能力が必要です。上申書は説得力のある論理構成と法的根拠の提示が求められるため、法律知識がないと適切な書面を作成するのは困難です。
証拠の収集と整理も重要です。期限後の相続放棄が認められるためには、主張を裏付ける証拠が必要で、どのような証拠が有効かの判断も専門知識を要します。
却下のリスクが高いことも考慮すべき点です。一度却下されると再申請はより困難になるため、初回で確実に認めてもらう必要があります。
期間延長の申立てという選択肢
期限が迫っている場合は、期限前に「相続の承認又は放棄の期間の伸長」の申立てを行うことを検討してください。これにより最大3ヶ月程度の延長が認められる場合があります。
ただし、延長の申立て自体にも書類準備が必要で、必ずしも延長が認められるわけではありません。延長が認められなかった場合のことも考慮して、同時に相続放棄の準備も進めることが重要です。
専門家への相談を強く推奨
期限後の相続放棄は成功率が低く、高度な法的知識と経験が必要です。自分で対処することも不可能ではありませんが、失敗のリスクを考えると、相続問題に詳しい弁護士への相談を強くお勧めします。
多くの弁護士事務所で初回無料相談を実施しているため、まずは専門家の意見を聞いてから判断することが賢明です。
Q4. 自分で相続放棄手続きを行う際の注意点とリスクは何?
相続放棄の手続きを自分で行う場合、いくつかの重大なリスクと注意点があります。これらを理解せずに進めると、相続放棄が認められない可能性や、後々のトラブルにつながる恐れがあります。
単純承認とみなされる行為の回避
最も重要な注意点は、相続財産に一切手をつけないことです。以下の行為は「単純承認」とみなされ、相続放棄が無効になります。
預貯金の引き出しや利用、預金の解約・名義変更は典型的な単純承認行為です。たとえ葬儀費用のためであっても、故人の預金を使用すると相続放棄はできなくなります。
不動産関連では、賃料の自分の口座への振込み、管理していた不動産の売却、修繕工事の発注なども単純承認に該当します。
形見分けや遺品整理にも注意が必要です。衣類や日用品であっても、経済的価値のあるものを他人に譲渡したり、自分が受け取ったりすると単純承認とみなされる可能性があります。
適切な財産調査の難しさ
自分で行う財産調査には限界があります。金融機関への照会や不動産の権利関係の調査など、専門知識がないと見落としやすい財産があります。
隠れた債務の発見が困難な場合もあります。保証債務や損害賠償債務など、通常の調査では判明しにくい負債が後から発覚することがあります。
調査が不十分だと、相続放棄後に予想外の財産が見つかっても相続できません。逆に、調査で見落とした債務については、相続放棄により免れることができます。
書類作成と提出のリスク
申述書の記載内容に誤りがあると却下される可能性があります。特に放棄の理由や相続財産の概要について、事実と異なる記載をすると問題となります。
必要書類の不備や不足も却下の原因となります。戸籍謄本の取得漏れや、関係性に応じた追加書類の見落としなどが起こりやすいポイントです。
提出期限の管理も重要です。書類準備に手間取り、3ヶ月の期限に間に合わない可能性があります。
家庭裁判所からの照会への対応
申述後に送られてくる照会書の回答が不適切だと相続放棄が認められません。照会内容は事案によって異なり、法的な判断が必要な質問も含まれます。
回答の矛盾や不備があると、追加の説明を求められたり、最悪の場合は却下されたりする可能性があります。
次順位相続人への影響
相続放棄をすると相続権が次順位の相続人に移行しますが、家庭裁判所から次順位の相続人に連絡がいくわけではありません。
事前の連絡なしに相続放棄すると、突然借金の督促が次順位の相続人に届き、トラブルになる可能性があります。特に疎遠な親族の場合は大きな問題となることがあります。
管理責任の継続
相続放棄をしても、故人の財産を「現に占有している」場合は管理責任が継続します。2023年4月の民法改正により責任の範囲は明確化されましたが、最低限の保存義務は残ります。
特に不動産を管理していた場合、相続人または相続財産清算人に引き渡すまでの間は適切な管理を続ける必要があります。
却下後の再申請の困難さ
一度申述が却下されると、再度申請しても受理されにくい傾向があります。却下の理由を克服する追加的な証拠や説明が必要となり、自分で対応するのは非常に困難です。
これらのリスクを考慮すると、複雑なケースや高額な財産・債務が関わる場合は、専門家への依頼を検討することが賢明です。
Q5. 相続放棄を自分でやるか専門家に依頼するか、どう判断すべき?
相続放棄を自分で行うか専門家に依頼するかの判断は、事案の複雑さ、期限の余裕、ご自身の知識や時間的余裕などを総合的に考慮して決める必要があります。
自分で行うのに適したケース
相続人同士で揉め事がなく、今後もトラブルの可能性が低い場合は自分で手続きを進めることができます。明らかに債務超過で相続放棄の判断に迷いがない場合も、自分で対応しやすいケースです。
必要書類が比較的少ない場合、例えば配偶者や子が相続放棄する場合は、戸籍謄本の収集がそれほど複雑ではありません。
期限に十分な余裕があり、書類収集や手続きに時間をかけられる場合も自分で行うことが可能です。
費用を最優先で抑えたい場合は、専門家報酬3万円~10万円程度を節約できるため、自分で行うメリットがあります。
専門家に依頼すべきケース
相続財産に多額の借金があり、債権者との交渉が必要な場合は弁護士への依頼が必要です。特に、督促が来ている状況では専門家による対応が不可欠です。
相続人間でトラブルが発生している、または発生する可能性がある場合も専門家のサポートが重要です。相続放棄が他の相続人の利害に大きく影響する場合は特に注意が必要です。
期限が迫っており、迅速な対応が必要な場合は、専門家の経験とネットワークを活用することで確実に期限内に手続きを完了できます。
相続放棄の期限を過ぎてしまった場合は、上申書の作成など高度な法的知識が必要となるため、弁護士への依頼がほぼ必須です。
必要書類が多数にわたる場合、特に兄弟姉妹や甥・姪が相続放棄する場合は、戸籍収集だけでも非常に複雑になるため、司法書士などの専門家に依頼することをお勧めします。
弁護士と司法書士の選び分け
司法書士は書類作成の専門家で、相続放棄の申述書作成や戸籍収集を代行できます。費用は比較的抑えられ(3万円~5万円程度)、手続きがスムーズに進む場合に適しています。
弁護士は法的トラブル全般に対応でき、債権者との交渉、相続人間の調整、複雑な法的判断が必要な事案に対応できます。費用は高くなりますが(5万円~10万円程度)、包括的なサポートを受けられます。
判断のためのチェックポイント
以下の質問で「はい」が多い場合は専門家への依頼を検討してください。
相続開始から既に2ヶ月以上経過していますか?相続財産の調査が複雑で、隠れた債務がある可能性はありますか?債権者からの督促や連絡が来ていますか?
他の相続人との関係が悪化している、または悪化する可能性がありますか?必要な戸籍謄本が5通以上になりそうですか?
平日の日中に役所や裁判所とのやり取りをする時間が取れませんか?法的な書類作成に不安がありますか?
無料相談の活用
多くの弁護士事務所や司法書士事務所で初回無料相談を実施しています。自分で行うかどうか迷っている場合は、まず専門家に相談して事案の複雑さや必要な手続きの概要を把握することをお勧めします。
相談の結果、自分で行えると判断した場合は自分で進め、困難と判断した場合は依頼するという選択も可能です。
法テラスでは、収入要件を満たせば無料相談や費用の立て替え制度を利用できるため、経済的に余裕のない方は活用を検討してください。
最終的には、確実性と費用のバランスを考慮して判断することが重要です。失敗のリスクを考えると、迷った場合は専門家への依頼が安全な選択と言えるでしょう。

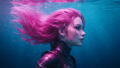

コメント