令和7年分の年末調整は、日本の税制史において極めて重要な転換期を迎えています。長年にわたり働く人々の働き方に大きな影響を与えてきた「103万円の壁」が見直され、基礎控除や給与所得控除が大幅に引き上げられることになりました。この改正により、所得税が課税されない給与収入の上限は160万円へと劇的に拡大します。同時に、行政手続きのデジタル化も加速しており、e-Taxを活用した電子申告の義務化範囲が拡大されるため、企業の人事・労務担当者は従来のルーチンワークを超えた対応が求められます。特に基礎控除額が最大95万円へと引き上げられたことで、所得階層に応じた細かな判定が必要となり、計算の複雑さは格段に増しています。さらに、19歳から22歳までの子どもを持つ家庭を支援する「特定親族特別控除」が新設され、大学生世代のアルバイト収入が増えても親の税負担が増えにくい仕組みが整備されました。本記事では、令和7年の年末調整における基礎控除の見直し、電子化の進展、e-Tax対応の必要性について、実務担当者が押さえるべきポイントを網羅的に解説します。

令和7年の年末調整で変わる基礎控除の仕組み
令和7年分の年末調整において最も大きな変更点が、基礎控除額の抜本的な見直しです。基礎控除とは、すべての納税者が一律に受けられる控除であり、これまでは合計所得金額が2,400万円以下であれば一律48万円が適用されていました。しかし、令和7年からはこの基礎控除額が所得階層によって細かく区分され、最大で95万円まで引き上げられることになりました。
この改正により、合計所得金額が132万円以下の方は基礎控除として95万円の控除を受けることができます。これは従来の48万円と比較して、実に47万円もの増額となります。一方で、合計所得金額が132万円を超えると控除額は段階的に減少し、132万円超336万円以下の場合は88万円、336万円超489万円以下の場合は68万円というように、所得が増えるにつれて控除額が減っていく仕組みが導入されました。
この新しい基礎控除の仕組みは、低所得者層への税負担軽減を主な目的としています。物価高騰が続く中で、生活費の負担が重い家計を支援するため、所得が少ない方ほど大きな控除を受けられる累進的な設計となっています。一方で、高所得者層については従来とほぼ同水準の控除額が維持されるため、税負担の公平性が保たれる形になっています。
実務上、この改正で特に注意すべき点は、従業員に「合計所得金額の見積り」を正確に申告してもらうことの重要性が増したことです。わずかな所得の違いで適用される基礎控除額が変わるため、副業収入や不動産所得がある従業員については、より慎重な確認が必要となります。年末調整の申告書には、給与所得以外の所得も含めた合計所得金額を記入する欄があり、ここでの記載ミスは最終的な税額に直接影響を与えることになります。
給与所得控除の改正と「160万円の壁」の誕生
基礎控除の引き上げと並行して、給与所得控除についても重要な改正が行われました。給与所得控除とは、会社員にとっての「概算経費」に相当するもので、給与収入から一定額を差し引くことができる制度です。令和7年からは、この給与所得控除の最低保障額が従来の55万円から65万円へと10万円引き上げられました。
給与収入が162万5,000円以下の方については、一律で65万円の給与所得控除が適用されます。これにより、給与所得を計算する際の基礎となる金額が変わり、結果として所得税の課税対象となる金額が減少します。この改正は、パートタイム労働者や新入社員など、比較的給与収入が少ない層に対して、直接的な減税効果をもたらすものとなります。
そして、この給与所得控除の引き上げと基礎控除の引き上げを合わせると、極めて重要な変化が生まれます。それが、いわゆる「非課税ライン」の大幅な引き上げです。従来、所得税が課税されない給与収入の上限は、給与所得控除55万円と基礎控除48万円を合わせた103万円でした。この「103万円の壁」は、パートタイム労働者が就業調整を行う主な理由の一つとされており、労働供給を抑制する要因として長年問題視されてきました。
令和7年からは、給与所得控除65万円と基礎控除95万円を合わせた160万円が新たな非課税ラインとなります。これは実に57万円もの引き上げであり、パートタイム労働者にとって就業時間を増やしやすい環境が整うことになります。企業にとっても、人手不足が深刻化する中で、11月や12月に「103万円を超えないように」とシフトを減らす従業員が減少することは、労働力の確保という観点から大きなメリットとなります。
ただし、注意すべき点として、所得税の非課税ラインが160万円に引き上げられても、社会保険の扶養範囲はこれとは別の基準で判定されることがあります。いわゆる「106万円の壁」や「130万円の壁」は社会保険料の負担が発生するボーダーラインであり、所得税とは異なる制度です。従業員に対しては、「所得税はかからないが、社会保険料は発生する可能性がある」という複雑な状況をわかりやすく説明する必要があります。
特定親族特別控除の新設で広がる教育費負担の軽減
令和7年の年末調整で新たに導入される制度として、特定親族特別控除があります。この制度は、大学生世代にあたる19歳から22歳の子どもを持つ家庭の税負担を軽減することを目的としています。教育費の負担が特に重い時期にある親を支援し、子どものアルバイト収入が増えても親の税負担が急増しないような配慮がなされています。
従来の制度では、扶養親族の所得要件は「合計所得金額48万円以下」とされており、給与収入のみの場合はおおむね103万円以下であることが条件でした。この基準を超えると、親は扶養控除を受けられなくなり、税負担が大きく増加することになっていました。そのため、大学生のアルバイトにおいても「103万円を超えないように調整する」という行動が一般的でした。
新設される特定親族特別控除では、19歳以上23歳未満の親族について、所得要件が段階的に設定されます。具体的には、特定親族の合計所得金額が58万円を超え85万円以下の場合、つまり給与収入でおおむね123万円を超え150万円以下の場合であっても、63万円の控除が適用されます。これは、従来の特定扶養控除と同等の控除額であり、実質的に子どもの年収が150万円まで増えても親の税負担が増えないことを意味します。
さらに、子どもの年収が150万円を超えた場合でも、188万円程度までは段階的に控除が適用される仕組みが導入されています。これにより、従来の「103万円の壁」が「150万円の壁」へと移行し、大学生が学業とアルバイトを両立しやすい環境が整備されることになります。
実務的には、この特定親族特別控除の適用を受けるためには、年末調整の申告書に特定親族の氏名、生年月日、所得金額などを詳細に記載する必要があります。新設された制度であるため、従業員にとっても記載方法が不慣れであり、記入ミスが多発する可能性があります。人事・労務担当者は、該当する年齢の子どもを持つ従業員を事前に把握し、個別に案内を送るなどの丁寧な対応が求められます。
扶養控除等の所得要件緩和と実務への影響
基礎控除の引き上げに伴い、扶養控除や配偶者控除に関する所得要件も連動して変更されます。従来、配偶者や子どもを扶養に入れるための要件は「合計所得金額48万円以下」でしたが、令和7年からは「合計所得金額58万円以下」へと引き上げられました。
この変更により、給与収入のみの場合で約123万円までの家族を扶養控除の対象とすることが可能になります。これは、給与所得控除65万円と合計所得金額58万円を合わせた金額です。実務上は、これまで「年収103万円を超えたため扶養から外す」という処理を行っていたケースでも、令和7年からは扶養の範囲内に留まる可能性が高まります。
担当者が注意すべきポイントは、前年のデータに基づいて機械的に扶養の可否を判定するのではなく、新しい基準値である「所得58万円」に基づいて再判定を行うことです。特に、令和6年分の年末調整で扶養から外れた従業員についても、令和7年の新基準では再び扶養対象となる可能性があります。このような変更があることを従業員に周知し、申告書への正確な記載を促すことが重要です。
また、勤労学生控除についても所得要件が見直され、従来の「合計所得金額75万円以下」から「合計所得金額85万円以下」へと引き上げられました。これにより、給与収入でおおむね150万円以下のアルバイト学生が勤労学生控除を受けられるようになり、学生の就業機会がさらに広がることになります。
ひとり親控除についても同様に、生計を一にする子の所得要件が「総所得等48万円以下」から「総所得等58万円以下」へと変更されています。これらの変更は、すべて基礎控除の引き上げと整合性を取るためのものであり、税制全体として低所得者層への配慮が強化される形となっています。
年末調整申告書の様式変更と「基・配・特・所」統合の複雑さ
令和7年分の年末調整では、申告書の様式にも大きな変更が加えられます。新たな控除制度の追加に伴い、これまで「基礎控除申告書 兼 配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書」と呼ばれていた様式に、「特定親族特別控除申告書」が統合されることになりました。
新しい様式は、正式には「給与所得者の基礎控除申告書 兼 配偶者控除等申告書 兼 特定親族特別控除申告書 兼 所得金額調整控除申告書」という非常に長い名称となります。通称として「基・配・特・所」申告書と呼ばれることが予想されます。この申告書には、基礎控除の判定に必要な所得見積り、配偶者の所得情報、新設された特定親族の詳細情報、所得金額調整控除の要件確認など、膨大な情報が一枚の用紙に詰め込まれることになります。
特に新設される特定親族特別控除の記入欄は、従業員にとって初めて目にする項目であり、記載方法に戸惑うケースが多発することが予想されます。親族の氏名や生年月日だけでなく、その親族の所得金額を細かく区分して記入する必要があるため、記入ミスのリスクが高まります。また、「特定扶養親族」という従来からの用語と「特定親族」という新しい用語が混在することで、用語の混同も懸念されます。
人事・労務担当者は、この複雑化した申告書を従業員に正しく記入してもらうため、わかりやすい記入例を作成し、事前に配布することが不可欠です。特に、所得の見積り方法については、給与収入から給与所得控除65万円を差し引いた金額が「所得」であることを明確に示した早見表を用意することで、記入ミスを減らすことができます。
また、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」、通称「マル扶」についても変更があります。従来の「控除対象扶養親族」欄が「源泉控除対象親族」欄へと名称変更され、さらにその親族が「特定親族」に該当するかをチェックする項目が追加されます。この申告書は、令和8年以降の月々の源泉徴収税額を計算する基礎となるため、ここでの記載漏れは翌年1年間の給与計算ミスに直結します。従業員には、慎重かつ正確な記入を求める必要があります。
通勤手当の非課税限度額改正と遡及対応の実務
年末調整に関連する実務として、通勤手当の非課税限度額の改正にも注意が必要です。令和7年度の税制改正により、通勤手当の非課税限度額が引き上げられましたが、その適用時期には特有の注意点があります。
この改正は、令和7年4月1日以後に支払われるべき通勤手当について適用されます。しかし、改正法の施行自体は令和7年11月頃に行われることが一般的であり、年の途中で基準が変更されることになります。このため、4月から10月頃までの期間については、旧基準で課税対象として処理していた通勤手当が、実際には新基準では非課税となる可能性があります。
年末調整においては、1月から12月までに支払われた給与・手当の総額を精算する作業が行われます。この際、4月以降に支払われた通勤手当について、新しい非課税限度額を適用して再計算し、課税対象額を減額調整する必要があります。この遡及的な調整作業は、給与計算システムが自動で対応できない場合、手動での計算と修正が必要となり、非常に煩雑な事務作業となります。
実務担当者は、自社の給与計算システムがこの遡及計算に対応しているかを事前に確認し、未対応の場合は対象者を洗い出して手動での調整を行う準備をしておく必要があります。特に、通勤距離が長い従業員や、新幹線通勤などで高額な通勤手当を受け取っている従業員については、調整額が大きくなる可能性があるため、優先的にチェックすることが推奨されます。
住宅ローン控除における「年末残高調書」方式の導入
住宅借入金等特別控除、いわゆる住宅ローン控除の手続きにおいても、デジタル化の波が押し寄せています。従来、従業員は金融機関から郵送される「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」を年末調整申告書に原本添付する必要がありました。しかし、令和7年分以降の年末調整からは、金融機関が税務署へ直接残高情報を提供する「調書方式」が本格的に導入されます。
この調書方式を選択した場合、従業員は残高証明書の原本を会社に提出する必要がなくなります。代わりに、税務署から提供される年末残高情報に基づいて控除を受けることになります。これにより、書類の紛失リスクが減少し、従業員の負担も軽減されるというメリットがあります。
一方で、実務担当者にとっては新たな確認作業が発生します。従業員が「調書方式」を選択しているのか、それとも従来の「証明書添付方式」を選択しているのかを見極め、それぞれに応じた添付書類の確認フローを構築する必要があります。制度の移行期においては、従業員自身がどちらの方式を選択しているのかを理解していないケースも想定されるため、事前のアンケート調査や個別の問い合わせ対応が必要となります。
また、調書方式を利用する場合でも、従業員が自身で税務署から提供される情報を確認し、それを申告書に正確に記入する必要があります。デジタル化によって手続きが簡素化される部分と、新たな確認作業が発生する部分の両方があることを理解し、従業員への丁寧な説明を心がけることが重要です。
e-Taxによる電子化と法定調書提出義務の拡大
令和7年の年末調整において、企業が最も注意すべき変更点の一つが、法定調書の電子提出義務化基準の引き下げです。従来、源泉徴収票などの法定調書をe-Taxや光ディスク等で提出することが義務付けられていたのは、前々年の提出枚数が「100枚以上」の事業者でした。しかし、令和7年度税制改正により、この基準が「30枚以上」へと大幅に引き下げられることになりました。
この変更により、中小企業であっても電子提出の義務化対象となるケースが大幅に増加します。従業員数が10名程度の小規模企業でも、退職者の源泉徴収票や弁護士・税理士への報酬支払調書などを含めると、年間30枚を超える法定調書を提出することは十分にあり得ます。
義務化の適用スケジュールについては、令和7年中に税務署へ提出した法定調書の合計枚数が30枚以上であるかを判定し、その基準を満たした場合、令和9年1月以降に提出する法定調書から電子提出が強制されます。つまり、令和7年の年末調整は、自社が将来的に電子提出義務の対象となるかどうかが確定する重要な分岐点となります。
電子提出義務の対象となった企業が紙で法定調書を提出した場合、その提出は法的に無効とみなされるリスクがあり、税務署からの指導対象となる可能性があります。また、年末調整を適切に行わず、あるいは虚偽の記載をして提出した場合、1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金などの罰則が規定されています。コンプライアンスリスクを回避するためにも、早期の電子化対応が求められます。
令和9年になってから慌ててシステムを導入するのではなく、令和7年の段階で電子提出の実績を作っておくことが、スムーズな移行への鍵となります。現時点で電子化未対応の企業は、令和7年の年末調整を機に、e-Taxの利用環境を整備することが強く推奨されます。
e-Tax導入のメリットとデジタル化による業務効率化
e-Taxによる電子申告の義務化は、一見すると新たな負担のように感じられるかもしれません。しかし、視点を変えれば、これは業務効率化と生産性向上の絶好の機会でもあります。年末調整のデジタル化には、以下のような多くのメリットがあります。
まず、マイナポータル連携により、生命保険料控除証明書や住宅ローンの年末残高証明書などのデータを自動取得できるようになります。従業員が紙の証明書を会社に提出する必要がなくなり、担当者も書類の受け取り・確認・保管という煩雑な作業から解放されます。データで取り込むことで入力ミスも根絶でき、計算の正確性が大幅に向上します。
次に、配布・回収コストの削減です。複雑化した「基・配・特・所」申告書を紙で印刷し、全従業員に配布し、回収し、チェックするという一連の作業は、時間とコストがかかります。Web年末調整システムを導入すれば、従業員はスマートフォンやパソコンからアンケート形式で必要事項を入力するだけで申告が完了します。リモートワークが普及した現代においても、郵送や直接手渡しの必要がなくなり、場所を問わず手続きを完了できる利便性があります。
さらに、法改正への自動対応も大きなメリットです。クラウド型の年末調整ソフトを利用すれば、令和7年の複雑な税率変更や控除額変更に対して、システム側が自動でアップデートを実施します。担当者が計算ロジックを手動で修正したり、エクセルの数式を書き換えたりする必要がなくなります。常に最新の税制に対応した計算が自動で行われるため、法令違反のリスクも軽減されます。
また、データの一元管理により、過去の申告内容や扶養親族の情報が蓄積され、翌年以降の年末調整業務がさらに効率化されます。従業員ごとの履歴を参照しながら、変更点のみを確認すればよくなるため、毎年ゼロから確認する手間が省けます。
電子化への移行には初期投資や従業員への教育コストがかかることは事実ですが、中長期的に見れば業務時間の大幅な削減と正確性の向上により、投資対効果は十分に見込めます。令和7年の年末調整を契機として、デジタル化による業務プロセスの再構築を検討することが、企業の競争力強化にもつながります。
定額減税の精算と不足額給付の仕組み
令和6年に実施された定額減税は、令和7年においても「精算」という形で実務に影響を与えます。定額減税とは、納税者本人と扶養親族1人あたり一定額を所得税額から直接差し引く制度であり、令和6年分の年末調整で既に適用されています。
しかし、所得税額が少ないために定額減税の金額を引ききれなかった場合、その残額は源泉徴収票の摘要欄に「控除外額」として記載されています。令和7年には、この引ききれなかった額に基づき、自治体から「不足額給付(調整給付)」が支給される予定です。
実務担当者が直接給付金を支払うわけではありませんが、従業員から「源泉徴収票に記載されているこの数字は何に使うのか」「給付金はいつ受け取れるのか」といった問い合わせを受ける可能性が高くなります。また、自治体が給付額を算定する際には、企業が提出した給与支払報告書の内容がデータソースとなります。給与支払報告書の内容は源泉徴収票と同じであるため、記載内容に誤りがあると従業員の給付金受給に支障をきたす恐れがあります。
正確な源泉徴収票の作成と適切な給与支払報告書の提出は、従業員の経済的利益を守るためにも極めて重要です。特に、控除外額の計算や記載については、給与システムが正しく対応しているかを確認し、必要に応じて手動での検証を行うことが推奨されます。
年末調整における誤りやすいポイントと対策
令和7年の年末調整は、制度の複雑化に伴い、従来以上にミスが発生しやすい環境にあります。実務担当者が特に注意すべき誤りやすいポイントと、その対策について整理します。
最も多発すると予想されるのが、所得見積額の計算ミスです。給与所得控除額が55万円から65万円に変更されたことを理解せず、従来の計算式で所得を算出してしまうケースが想定されます。従業員向けのマニュアルには、「給与収入から65万円を差し引いた金額が所得」であることを明記した簡易早見表を掲載し、視覚的にわかりやすく示すことが有効です。
次に、特定親族特別控除の適用漏れも懸念されます。「103万円を超えているから扶養外」という固定観念により、19歳から22歳の子どもを持つ従業員が申告を漏らす可能性があります。対策としては、社員名簿から該当年齢の子どもがいる従業員を抽出し、個別に案内メールを送るなどの能動的なアプローチが推奨されます。
また、保険料控除証明書の添付漏れもよく見られるミスです。電子データでの提出と紙での提出が混在することで、どの証明書を提出済みなのかが不明確になるケースがあります。提出物のチェックリストを配布し、従業員自身に添付書類の有無を自己チェックさせる仕組みを導入することで、ミスを減らすことができます。
さらに、配偶者の所得要件の誤認にも注意が必要です。配偶者控除の所得要件が58万円以下に変更されたことを知らずに、従来の48万円基準で判断してしまうミスが考えられます。申告書の記入欄には、新しい基準値を明記し、従業員が正しく判断できるようサポートすることが重要です。
これらのミスを防ぐためには、事前の周知徹底と、わかりやすいマニュアルの作成、そして従業員からの質問に丁寧に対応できる体制の構築が不可欠です。年末調整の時期が近づいたら、社内で説明会を開催し、改正内容のポイントを直接説明することも効果的です。
年末調整のスケジュール管理と準備の重要性
令和7年の年末調整を円滑に進めるためには、綿密なスケジュール管理と事前準備が欠かせません。以下に、推奨されるスケジュールとアクションプランを示します。
令和7年夏頃には、給与計算システムのベンダーから「令和7年改正対応プログラム」のリリース予定を確認します。システムのバージョンアップが必要な場合は、スケジュールを把握し、予算確保やテスト計画を立案します。
令和7年10月には、改正内容を反映した社内マニュアルを作成し、従業員への周知を開始します。特に基礎控除の多段階判定や特定親族特別控除については、具体例を用いた丁寧な説明資料を用意します。また、Web年末調整システムを導入している場合は、システム上の設問が新法令に正しく対応しているかをテスト入力で確認します。
令和7年11月には、年末調整申告書の配布を開始します。紙ベースの場合は印刷と配布、電子化している場合はシステムへのアクセス案内を行います。同時に、従業員向けの説明会や個別相談会を開催し、記入方法についての質問に対応します。
令和7年12月には、提出された申告書の内容確認と年末調整計算を実施します。通勤手当の遡及修正が必要な対象者がいないかを再確認し、必要に応じて手動調整を行います。計算結果に異常値がないかをサンプルチェックし、システムが正しく動作しているかを検証します。
令和8年1月には、源泉徴収票の交付と法定調書の提出を行います。この際、提出した法定調書の合計枚数が30枚を超えたかどうかを記録します。超えている場合は、令和9年から電子提出が義務化されることを踏まえ、次年度のシステム予算に「電子申告対応費用」を計上する準備を進めます。
このように、年末調整は年末の一時期だけの作業ではなく、夏頃からの長期的な準備が成功の鍵となります。特に令和7年は改正項目が多岐にわたるため、余裕を持ったスケジュールで進めることが重要です。
企業が取り組むべきデジタル化戦略と今後の展望
令和7年の年末調整は、単なる税制改正への対応にとどまらず、企業のバックオフィス業務全体をデジタル化する絶好の契機となります。紙ベースの手書き申告書や、表計算ソフトでの手動計算に頼った従来型の業務フローでは、今後ますます複雑化する税制に対処することが困難になります。
デジタル化の推進により、担当者は定型的な入力作業や計算作業から解放され、より付加価値の高い業務に集中できるようになります。たとえば、従業員への丁寧な説明や個別相談、税務リスクの分析や改善提案など、人間にしかできない判断業務に時間を割くことが可能になります。
また、デジタル化はコンプライアンス強化にも直結します。システムによる自動計算は人為的ミスを減らし、法令に基づいた正確な処理を保証します。電子データとして記録が残ることで、税務調査への対応もスムーズになり、過去のデータを迅速に参照できる体制が整います。
さらに、今後の税制改正においても、デジタル化の流れは加速すると予想されます。マイナンバーカードの普及やマイナポータルの機能拡充により、行政手続きの完全オンライン化が進められています。企業としても、この流れに早期に対応し、従業員にとって使いやすく、かつ法令遵守が確実なシステム環境を構築することが、人材確保や企業価値向上の観点からも重要となります。
令和7年の年末調整を成功させるためには、「160万円の壁」への対応や「特定親族」の判定といった高度な判断をシステムに任せ、人間は従業員とのコミュニケーションや例外対応に専念するという役割分担が理想的です。この難局を、デジタルトランスフォーメーションによる効率化とガバナンス強化の好機と捉え、戦略的に準備を進めることが、企業のバックオフィス部門に求められています。


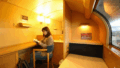
コメント