2025年は社会保険制度にとって大きな転換点となりました。国民健康保険料の上限額が前年度から3万円引き上げられて109万円となり、協会けんぽの健康保険料率も46都道府県で改定が実施されました。さらに2027年9月からは厚生年金保険料の標準報酬月額上限が段階的に引き上げられることが決定しており、高所得者層を中心に保険料負担の増加が避けられない状況です。こうした値上げの背景には、団塊の世代が全員75歳以上の後期高齢者となる2025年問題があり、医療費や介護費用の急増に対応するため、現役世代の負担が増え続けています。しかし一方で、介護保険料率や雇用保険料率は引き下げられるなど、制度全体としては複雑な動きを見せています。現役世代の家計にどのような影響が及ぶのか、企業はどのような対策を講じるべきか、そして私たち一人ひとりができる負担軽減策は何か、2025年における社会保険料値上げの全体像を詳しく見ていきましょう。

国民健康保険料の上限引き上げと高所得者への影響
2025年度における国民健康保険料の年間上限額は109万円となり、前年度の106万円から3万円の引き上げとなりました。介護保険料を納めない方については92万円が上限として設定されています。この上限引き上げによって直接的な影響を受けるのは、年収約1,170万円以上の高所得世帯です。高所得者層にとっては年間の保険料負担が増加することになり、可処分所得の減少につながります。
国民健康保険料の上限引き上げは、高齢化社会における医療費の増大に対応するための措置とされていますが、高所得者層の負担感は確実に増しています。すでに高額な税金や社会保険料を負担している層にとって、さらなる負担増は家計に大きな影響を与えます。特に住宅ローンの返済や子供の教育費など、支出が多い世代にとっては、年間3万円の増額でも決して小さな金額ではありません。
高所得者層への負担集中は、世代間の公平性を保ちながら社会保険制度の持続可能性を確保するための施策として位置づけられています。医療費が増大する中で、所得に応じた負担を求めることで、低所得者層への配慮を維持しつつ、制度全体の財源を確保する狙いがあります。しかし、負担増が続けば高所得者層の不公平感が高まり、制度への信頼が損なわれる可能性も指摘されています。
協会けんぽの保険料率改定と地域格差の実態
協会けんぽが管掌する健康保険においても、2025年度は大きな変更がありました。大分県を除く46都道府県で保険料率の改定が行われており、18都府県で引き下げ、28道県で引き上げとなっています。保険料率が引き上げられた主な都道府県を見てみると、北海道では10.21%から10.31%へ0.1ポイントの引き上げ、長野県では9.55%から9.69%へ0.14ポイント、長崎県では10.17%から10.41%へ0.24ポイントの引き上げとなりました。
一方で、保険料率が引き下げられた都道府県もあります。東京都では9.98%から9.91%へ0.07ポイントの引き下げ、大阪府では10.34%から10.24%へ0.1ポイントの引き下げとなりました。最も保険料率が高いのは長崎県の10.41%で、最も低いのは新潟県の9.43%です。この差は約1ポイントにも及び、同じ給与額でも都道府県によって年間数万円の保険料の違いが生じることになります。
協会けんぽの保険料率は都道府県ごとに異なっており、各地域の医療費水準や加入者の年齢構成などによって決定されます。都道府県単位保険料率は、都道府県ごとの年齢構成や所得水準の差を調整した上で、当該都道府県の加入者1人当たりの医療費に基づいて毎年算出され、改定されています。医療費が高い地域では保険料率も高くなる傾向があり、保険料水準には西高東低の傾向が見られます。
西日本、特に九州地方では医療費が高く、保険料率も高い傾向にあります。一方、東日本、特に関東地方では医療費が比較的低く、保険料率も低めです。この地域差が生じる要因としては、高齢化率の違い、医療機関の受診頻度の違い、生活習慣病の罹患率の違いなどが挙げられます。例えば、九州地方では糖尿病の罹患率が高い傾向があり、これが医療費の増加につながっています。また、医療機関へのアクセスが良い都市部では受診頻度が高くなる傾向もあります。
協会けんぽの保険料は労使折半で負担されます。つまり、従業員と事業主がそれぞれ半分ずつ負担する仕組みです。保険料率が引き上げられた地域では、従業員の給与からの天引き額が増加するとともに、事業主の人件費負担も増加することになります。企業にとっては、保険料率の改定が経営に与える影響を正確に把握し、適切な対応を取ることが求められています。
介護保険料率と雇用保険料率の引き下げ
社会保険料の値上げが続く中で、良いニュースもあります。2025年度の介護保険料率は1.59%となり、2024年度の1.6%から0.01ポイント引き下げられました。わずかな引き下げではありますが、40歳以上65歳未満の介護保険第2号被保険者にとっては負担軽減となります。介護保険料も健康保険料と同様に労使折半で負担されます。介護保険料率の引き下げは、介護給付費の見通しや介護保険財政の状況を踏まえて決定されたものです。
高齢化が進む中で介護保険料の引き下げは異例のことであり、今後の動向が注目されます。介護保険制度は2000年に導入されて以来、高齢化の進行とともに給付費が増大し、保険料率も上昇を続けてきました。今回の引き下げは一時的なものである可能性もあり、中長期的には再び上昇に転じることが予想されます。しかし、現時点での引き下げは、現役世代の負担感を少しでも和らげる効果があります。
2025年度は雇用保険料率も引き下げられました。0.1ポイント(被保険者負担分0.05%、事業主負担分0.05%)の引き下げが実施されており、労働者と事業主の双方にとって負担軽減となります。雇用保険料率の引き下げは、雇用保険財政の健全化を背景としています。失業給付の支給額が減少傾向にあることや、雇用情勢の改善により雇用保険財政に余裕が生まれたことが引き下げの理由とされています。
雇用保険は、失業した際の生活を支える重要なセーフティネットです。近年の雇用情勢の改善により、失業率は低水準で推移しており、失業給付の支給額も減少しています。また、雇用保険制度には育児休業給付や介護休業給付なども含まれており、働く人々の生活を多面的に支えています。雇用保険料率の引き下げは、制度の持続可能性を維持しながら、現役世代の負担を軽減する取り組みとして評価されています。
厚生年金保険料の上限引き上げとそのスケジュール
2025年は5年に1度の年金制度改革の年とされており、厚生年金保険料の上限引き上げなど、さまざまな改革が決定されています。厚生年金保険料の標準報酬月額の上限引き上げについて、具体的なスケジュールが決定されました。2027年9月から段階的に実施され、3段階で進められます。
第1段階として、2027年9月には現行の65万円から68万円へと引き上げられます。これに伴い、新たに第33級が新設されます。続いて第2段階では、2028年9月に68万円から71万円へと引き上げられ、第34級が新設されます。最終的な第3段階では、2029年9月に71万円から75万円へと引き上げられ、第35級が新設されます。この改正により、最終的には標準報酬月額の上限が現行の65万円から75万円へと10万円引き上げられることになります。
これは、賞与を除く年収で言えば約798万円以上の従業員が対象となります。厚生年金加入者全体の約6.2%に該当する高所得者層が、この上限引き上げの影響を受けることになります。厚生労働省の発表によれば、この基準に該当する厚生年金加入者は全体の約6.2%とされています。一見すると少数派に思えるかもしれませんが、実際には相当数の労働者が影響を受けることになります。厚生年金の加入者数は約4,500万人程度ですので、約280万人が対象となる計算になります。
対象となるのは、主に大企業の管理職、専門職、経営幹部などの高所得層です。また、医師や弁護士、公認会計士などの高収入の専門職も対象となります。これらの方々は、すでに高い社会保険料を負担していますが、今回の改正によってさらなる負担増となります。企業への影響も見逃せません。特に高度な専門人材を多く雇用している企業、大企業、IT企業、コンサルティング会社などでは、人件費の増加が経営に影響を与える可能性があります。
厚生年金保険料上限引き上げによる具体的な負担額
では、実際にどの程度の負担増になるのでしょうか。具体的な数字を見ていきましょう。賃金などが月75万円以上の方の場合、保険料の本人負担分は月9,100円の増加となります。社会保険料控除を考慮すると、実質的な負担増は月約6,100円程度になります。一見すると小さな金額に見えるかもしれませんが、年間で考えると約7万3,200円の負担増となり、決して無視できない金額です。
企業側の負担も同様に増加します。対象となる従業員1人あたり月額9,000円程度(労使折半後)の負担増加が見込まれます。高所得の従業員を多く抱える企業にとっては、人件費の大幅な増加につながる可能性があります。従業員一人当たりの負担増は月9,000円程度ですが、対象となる従業員が多ければ、年間で数千万円から数億円規模の人件費増加につながることもあります。
ただし、この負担増には将来の年金受給額の増加という側面もあります。標準報酬月額75万円の状態が10年間続いた場合、将来受け取る年金額は月約5,100円増加します。年金課税を考慮すると、実質的には月約4,300円の増額となります。これを一生涯受け取ることができるため、長期的に見れば必ずしも損とは言えない面もあります。
しかし、現役世代にとっては目の前の負担増が重くのしかかります。特に住宅ローンの返済や子供の教育費など、支出が多い世代にとっては、月々の手取り収入の減少は家計への影響が大きいでしょう。また、定年退職後に年金を受け取るまでの期間が長い若い世代ほど、将来の年金制度への不安から、負担増に対する抵抗感が強い傾向にあります。年金制度の持続可能性に対する不安が高まる中で、保険料の負担増だけが先行することへの不満は無視できません。
2025年問題と社会保険料負担増加の背景
なぜ社会保険料の値上げが続いているのでしょうか。その背景には、日本が直面する2025年問題と呼ばれる構造的な課題があります。2025年問題とは、団塊の世代(1947年から1949年生まれ)が全員75歳以上の後期高齢者となることで、社会保障給付費の増大が避けられない状況を指します。特に75歳以上の後期高齢者は医療や介護のニーズが高く、一人当たりの医療費は現役世代の約5倍とも言われています。
一方で、これを支える現役世代は減少を続けており、社会保険料の負担増加が深刻な問題となっています。第一に、少子高齢化の進行です。日本は世界でも類を見ない速さで高齢化が進んでおり、2025年には団塊の世代が全て75歳以上の後期高齢者となりました。これにより、医療費や介護費用が急増しています。実際、2025年には高齢化率(総人口に占める65歳以上の人口の割合)が30%を超えており、国民の約3人に1人が高齢者という超高齢社会が到来しています。
第二に、医療技術の高度化です。新しい治療法や医薬品の開発により、これまで治療が難しかった病気も治療できるようになりました。しかし、高度な医療には高額な費用がかかり、医療費全体の増加につながっています。例えば、がんの免疫療法や再生医療など、最先端の治療には年間数百万円から数千万円の費用がかかることもあります。
第三に、現役世代の減少です。少子化により労働人口が減少しており、社会保険料を負担する現役世代が減少しています。一方で、社会保険給付を受ける高齢者は増加しており、現役世代一人当たりの負担が増加する構造となっています。1990年には現役世代5.1人で高齢者1人を支える構造でしたが、2025年には現役世代1.8人で高齢者1人を支える構造になりました。これらの構造的な課題に対応するため、社会保険制度の持続可能性を確保する観点から、保険料の引き上げや給付の見直しが行われているのです。
現役世代への影響と負担の実態
2025年問題による社会保険料負担の増加は、現役世代の家計に大きな影響を与えています。社会保険制度(健康保険、年金保険、介護保険)は、企業と労働者が支払う保険料が財源となり、高齢者や医療・介護サービスを支える仕組みです。現役世代にとって、給与から天引きされる社会保険料は年々増加しています。
例えば、介護保険では、全国の介護給付費の27%が介護保険料として現役世代(40歳以上65歳未満の第2号被保険者)の給与から控除されています。健康保険料と合わせると、給与の15%前後が社会保険料として天引きされるケースも珍しくありません。さらに、所得税や住民税などの税金を含めると、可処分所得(手取り収入)は額面給与の7割から8割程度にまで減少します。
年収500万円の会社員の場合、社会保険料と税金で年間約120万円から150万円が控除され、手取りは350万円から380万円程度となります。この負担は今後も増え続けることが予想されています。厚生労働省の試算によれば、社会保障給付費は2025年には約140兆円、2040年には約190兆円に達すると見込まれています。これに伴い、社会保険料の負担も増加を続けることになります。
現役世代の負担感が高まる中で、世代間の公平性をどのように確保するかが重要な課題となっています。高齢者の医療費自己負担割合の見直しや、高所得高齢者への給付の適正化など、高齢者側の負担や給付の見直しも進められています。しかし、政治的な困難もあり、改革のスピードは十分とは言えない状況です。現役世代の声を政策に反映させる仕組みづくりが求められています。
高額療養費制度の見直しと患者負担の増加
社会保険料の値上げに加えて、2025年8月からは高額療養費制度の見直しも実施されました。この制度は、医療費の自己負担が高額になった場合に、一定の限度額を超えた部分が払い戻される制度です。2025年8月から2026年7月にかけて、自己負担限度額が段階的に引き上げられる予定です。これにより、高額な医療費がかかった際の患者負担が増加することになります。
特に慢性疾患を抱える方や高額な治療を受ける必要がある方にとっては、家計への影響が大きくなる可能性があります。例えば、がん治療や人工透析など、継続的に高額な医療費がかかる場合、毎月の自己負担限度額が引き上げられることで、年間の医療費負担が数万円から数十万円増加することもあります。高額療養費制度は、医療費の自己負担が家計を圧迫しないようにするためのセーフティネットとして重要な役割を果たしてきました。
しかし、医療費の増大により制度の財政が圧迫されており、自己負担限度額の引き上げが避けられない状況となっています。患者負担の増加は、必要な医療を受けることを躊躇させる可能性もあり、健康格差の拡大につながる懸念があります。低所得者への配慮を維持しながら、制度の持続可能性を確保するバランスが求められています。
2026年10月の社会保険適用拡大と短時間労働者への影響
2025年の変更だけでなく、今後予定されている改正についても把握しておくことが重要です。2026年10月には、社会保険の適用拡大が実施される予定です。現在、パート・アルバイトが社会保険に加入するためには「賃金が月額8万8,000円以上(年収106万円以上)」という要件があります。しかし、2026年10月にはこの要件が撤廃される予定です。これにより、週20時間以上働くパート・アルバイトは原則として社会保険に加入することになります。
この改正により、これまで社会保険に加入していなかった短時間労働者も、厚生年金保険料や健康保険料を負担することになります。労働者にとっては手取り収入が減少する一方で、将来受け取る年金額が増加し、健康保険の給付も充実するというメリットがあります。例えば、傷病手当金や出産手当金など、国民健康保険にはない給付を受けられるようになります。
事業主にとっては、社会保険料の事業主負担分が増加することになり、人件費の増加につながります。特に多くのパート・アルバイトを雇用している業種では、大きな影響が予想されます。飲食業、小売業、サービス業など、パート・アルバイトに大きく依存している業界では、人件費の増加が経営を圧迫する可能性があります。企業は、労働時間の調整や雇用形態の見直しなど、適切な対応策を検討する必要があります。
また、いわゆる年収の壁問題にも関連します。これまで年収106万円や130万円を超えないように労働時間を調整していたパート労働者が、社会保険の適用拡大によって手取り収入の減少を避けるために、さらに労働時間を増やすか、逆に減らすかという選択を迫られることになります。政府は、年収の壁を意識せずに働けるよう、配偶者控除の見直しなども検討していますが、実現には時間がかかる見通しです。
現役世代ができる具体的な負担軽減策
社会保険料の値上げが続く中、現役世代が家計の負担を軽減するためにできる対策があります。まず、月々の固定費を見直すことが重要です。通信費、光熱費、サブスクリプションサービスなど、定期的に支払っている費用を見直し、不要なものを削減することで、可処分所得を増やすことができます。例えば、スマートフォンの料金プランを格安SIMに変更するだけで、月々数千円の節約になります。
健康管理を徹底することも効果的です。定期的な運動、バランスの取れた食事、十分な睡眠など、基本的な健康習慣を維持することで、病気のリスクを減らし、医療費を抑制できます。また、健康診断を定期的に受けることで、病気の早期発見・早期治療につながり、結果として医療費を抑えることができます。生活習慣病は早期発見すれば、投薬や生活改善で管理できますが、進行してしまうと入院や手術が必要になり、医療費が大幅に増加します。
ジェネリック医薬品の利用も有効です。ジェネリック医薬品は先発医薬品と同じ効果を持ちながら、価格が約半分から7割程度で済みます。医師や薬剤師に相談してジェネリック医薬品に切り替えることで、薬代を大幅に節約できます。長期的に服薬が必要な慢性疾患の場合、ジェネリック医薬品への切り替えで年間数万円の節約になることもあります。
セルフメディケーション税制の活用も検討しましょう。対象となるOTC医薬品(市販薬)を年間1万2,000円以上購入した場合、所得控除を受けることができます。軽い症状であれば市販薬で対処し、医療機関の受診を減らすことで、医療費の削減につながります。ただし、医療費控除との併用はできないため、どちらが有利かを検討する必要があります。
個人事業主や小規模企業の経営者の場合、小規模企業共済やiDeCo(個人型確定拠出年金)などの制度を活用することで、所得控除を受けながら老後の資金準備ができます。ただし、社会保険料の算定基礎となる所得を抑えることと、将来受け取る年金額のバランスを考える必要があります。短期的な節約だけでなく、長期的な視点での資産形成が重要です。
企業ができる社会保険料負担への対策
企業側も、社会保険料負担の増加に対して対策を講じることができます。まず、福利厚生制度を充実させることで、従業員の実質的な収入を増やすことができます。例えば、食事補助や住宅補助、通勤手当などの非課税の福利厚生を活用すれば、社会保険料の対象とならずに従業員の満足度を高めることができます。福利厚生として提供される食事補助は、一定の要件を満たせば1食当たり3,500円まで非課税となります。
健康経営を推進することも重要です。従業員の健康を維持・増進することで、医療費の削減につながり、結果として健康保険料率の上昇を抑制することができます。定期的な健康診断の実施、運動習慣の促進、メンタルヘルス対策、禁煙支援プログラムなどが有効です。健康経営優良法人認定制度に申請し、認定を受けることで、企業のイメージアップにもつながります。
認定企業は、採用活動で有利になったり、金融機関からの優遇金利を受けられたりするメリットもあります。特に若い世代は、企業選びの際に福利厚生や働きやすさを重視する傾向が強く、健康経営への取り組みは採用力の向上につながります。また、従業員の健康維持は、欠勤率の低下や生産性の向上にもつながり、企業全体のパフォーマンス向上に貢献します。
また、労働時間の適正化も重要です。長時間労働は従業員の健康を損ない、医療費の増加につながります。働き方改革を推進し、労働時間を適正化することで、従業員の健康維持と生産性向上の両立を図ることができます。テレワークの導入やフレックスタイム制の活用など、柔軟な働き方を認めることで、従業員のワークライフバランスを改善できます。
社会保険料の計算方法を正確に理解し、適切な給与設計を行うことも大切です。例えば、賞与の配分を工夫することで、年間の社会保険料負担を最適化できる場合があります。ただし、従業員の将来の年金額にも影響するため、慎重な検討が必要です。短期的なコスト削減だけでなく、従業員の長期的な利益も考慮した人事制度の設計が求められています。
社会保険料の計算方法を理解する
社会保険料がどのように計算されているのかを理解することは、自分の負担額を把握し、将来の計画を立てる上で重要です。社会保険料は、標準報酬月額と標準賞与額をもとに計算されます。標準報酬月額とは、従業員が受け取る毎月の給料(基本給や各種手当などを含む)を、キリの良い金額で区分した等級ごとの金額のことです。実際の給与額ではなく、等級に応じた金額が保険料計算の基礎となります。
健康保険の標準報酬月額は、第1級の5万8,000円から第50級の139万円までの全50等級に区分されています。厚生年金保険は、第1級の8万8,000円から第32級の65万円までの32等級に区分されていますが、2027年9月以降は段階的に最高等級が引き上げられ、最終的には第35級の75万円まで拡大される予定です。
標準報酬月額は、入社時の給与額に基づいて決定され、その後は毎年1回、4月から6月の3ヶ月間の給与の平均額をもとに見直されます。これを定時決定といいます。また、給与が大幅に変動した場合には、随時改定により標準報酬月額が変更されることもあります。昇給や降給により2等級以上の変動があった場合、3ヶ月間の平均をもとに標準報酬月額が改定されます。
賞与(ボーナス)にも社会保険料がかかります。標準賞与額は、税引き前の賞与の支給総額から1,000円未満を切り捨てて算出します。ただし、年3回以下の回数で支給される賞与は、標準報酬月額の算定基礎には含まれません。標準賞与額には上限が設定されています。健康保険は年度の累計額573万円、厚生年金保険は1回の支給につき150万円が上限です。上限を超えた部分については、社会保険料はかかりません。
具体的な計算例で理解する2025年度の社会保険料
実際の数字を使って、2025年度の社会保険料を計算してみましょう。標準報酬月額30万円、東京都在住、45歳の従業員の場合を例に挙げます。まず、健康保険料です。東京都の2025年度の健康保険料率は9.92%です。これに介護保険料率1.59%を加えると、合計で11.51%となります。この料率を標準報酬月額に乗じて、労使折半で半分を従業員が負担します。計算式は、300,000円×11.51%÷2=17,265円となります。
次に、厚生年金保険料です。厚生年金保険料率は全国一律で18.3%です。計算式は、300,000円×18.3%÷2=27,450円となります。雇用保険料は、実際の給与額に保険料率を乗じて計算します。一般の事業の場合、2025年度の雇用保険料率は1.1%で、このうち従業員負担分は0.55%です。計算式は、300,000円×0.55%=1,650円となります。
これらを合計すると、月々の社会保険料は46,365円となります。年間では約55万6,380円の負担となります。これは、標準報酬月額30万円、年収360万円の従業員の場合の例ですが、収入の約15.5%が社会保険料として天引きされることになります。さらに所得税や住民税も加わるため、実際の手取り収入は額面給与の約75%から80%程度になります。
年収500万円の会社員の場合、社会保険料と税金で年間約120万円から150万円が控除され、手取りは350万円から380万円程度となるのが一般的です。給与が増えるほど社会保険料の負担額も増加しますが、将来受け取る年金額も増加するという側面があります。目の前の負担だけでなく、長期的な視点で社会保険制度を理解することが大切です。
政府の対策と負担軽減に向けた動き
現役世代の社会保険料負担が重くなる中、政府も対策を検討しています。2025年2月には、自由民主党、公明党、日本維新の会が共同で、現役世代の社会保険料負担軽減に向けた合意文書に署名しました。この合意では、医療費を年間少なくとも4兆円削減することで、一人当たりの年間保険料を6万円削減することが目標として掲げられています。
具体的には、医療の効率化、予防医療の推進、ジェネリック医薬品の使用促進などが検討されています。医療の効率化では、かかりつけ医制度の推進、病院と診療所の機能分化、ICTを活用した医療情報の共有などが進められています。予防医療では、特定健診・特定保健指導の充実、がん検診の受診率向上、生活習慣病予防プログラムの推進などが重点施策となっています。
また、後期高齢者の自己負担割合の見直しも進められています。2022年10月には、一定以上の所得がある後期高齢者の医療費自己負担割合が1割から2割に引き上げられました。これにより、現役世代の負担を抑制し、世代間の公平性を確保する狙いがあります。ただし、急激な負担増を避けるため、配慮措置も設けられています。
地域包括ケアシステムの構築も重要な施策の一つです。高齢者が住み慣れた地域で最期まで自分らしい生活を送れるよう、医療・介護・予防・住まい・生活支援が一体的に提供される体制を整備しています。これにより、施設介護から在宅介護へのシフトを進め、介護費用の抑制を図っています。在宅医療や訪問看護の充実、地域の見守り体制の強化などが進められています。
さらに、給付と負担の構造見直しも進められています。高所得者の保険料負担を増やす一方で、低所得者への配慮も行うなど、より公平な制度設計が模索されています。応能負担の原則を強化し、所得や資産に応じた負担を求める方向性が示されています。ただし、政治的な困難もあり、改革の実現には時間がかかる見通しです。
社会保険料の将来展望と長期的な視点
社会保険料は今後も増加を続けることが予想されています。厚生労働省の試算によれば、社会保障給付費は2025年には約140兆円、2040年には約190兆円に達すると見込まれています。これに伴い、社会保険料の負担も増加を続けることになります。特に2040年には団塊ジュニア世代が高齢者となり、再び高齢化のピークを迎えることが予想されています。
しかし、社会保険料の負担増加は、必ずしもマイナス面だけではありません。健康保険や介護保険は、病気や介護が必要になった際の経済的なセーフティネットとして機能します。また、厚生年金保険料の負担増は、将来受け取る年金額の増加にもつながります。特に厚生年金保険料の上限引き上げについては、高所得者の負担は増加しますが、その分、将来受け取る年金額も増加します。
また、社会保険制度は世代間扶養の仕組みです。現役世代が支払う保険料が、現在の高齢者を支えています。将来、自分自身が高齢者となったときには、次の世代が自分を支えてくれることになります。この相互扶助の仕組みを維持するためには、現役世代の一定の負担は避けられません。ただし、世代間の公平性を保つためには、高齢者側の負担や給付の見直しも並行して進める必要があります。
長期的な視点を持つことも重要です。社会保険料の負担増は、将来のセーフティネットの充実や年金受給額の増加につながる側面もあります。目の前の負担だけでなく、将来のベネフィットも考慮しながら、社会保険制度と向き合っていくことが求められています。ただし、制度への信頼を維持するためには、政府が制度の持続可能性を明確に示し、改革を着実に進めることが不可欠です。


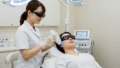
コメント