近年、健康と環境の両方を守る新しい食事法として注目を集めているプラネタリーヘルスダイエットですが、その効果、特に体重減少効果と変化が現れるまでの期間について気になる方も多いのではないでしょうか。2019年に世界16カ国の科学者37名からなるEAT-Lancet Commissionによって提唱されたこのダイエットは、単なる減量法ではなく、人間の健康と地球環境の持続可能性を同時に実現することを目的とした革新的なアプローチです。動物性食品を控えめにし、植物性食品を中心とした食事スタイルは、早期死亡リスクを30パーセント低減させるという科学的データも報告されており、長期的な健康効果が証明されています。しかし、多くの人が最も関心を持つのは「実際にどれくらいの期間で体重が減るのか」という点でしょう。本記事では、プラネタリーヘルスダイエットの体重減少効果とその期間について、最新の研究データと専門家の見解を基に詳しく解説していきます。
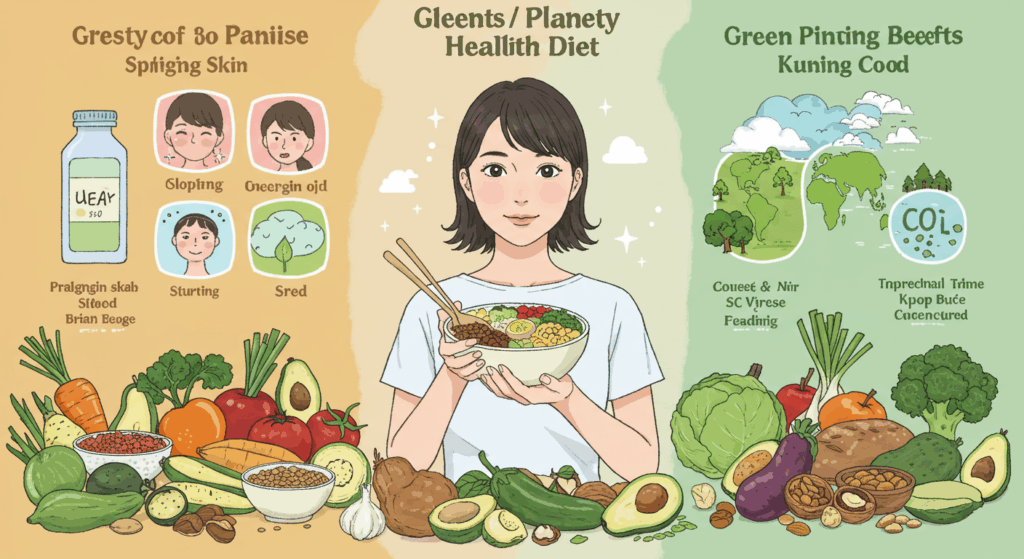
プラネタリーヘルスダイエットとは何か
プラネタリーヘルスダイエットは、EAT-Lancet Commissionが科学的根拠に基づいて作成した食事法であり、2050年までに世界人口が100億人に達する中で、すべての人に健康的な食事を提供しながら地球環境を守るという壮大な目標を持っています。従来のダイエット法が個人の体重減少や健康改善のみに焦点を当てていたのに対し、このダイエットは食料生産が環境に与える影響を最小限に抑えながら、栄養バランスの取れた食事を実現することを目指しています。
具体的には、肉や魚の消費量を抑え、砂糖や精製穀物などを削減した食事が推奨されており、持続可能な食糧システムの実現を目指しています。畜産業は温室効果ガスの主要な排出源の一つであり、動物性食品の消費を減らすことは環境負荷の軽減に直結します。個人が食生活を変えることは、自分自身の健康を守るだけでなく、気候変動対策に貢献する重要な行動となるのです。
一日の推奨摂取量とその意味
プラネタリーヘルスダイエットでは、1日の必要エネルギー量を約2500キロカロリーと想定し、各食品グループの具体的な摂取量が詳細に定められています。全粒穀物は232グラム、これは玄米であればお茶碗約2杯分に相当します。野菜は300グラムで、生野菜であれば両手に山盛り2杯分程度の量です。果物は200グラムで、りんご1個とバナナ1本程度の量に相当します。
植物性タンパク質としては、豆類が50グラム、大豆製品が25グラムとされており、納豆や豆腐などの和食でおなじみの食材が推奨されています。ナッツは50グラムで、手のひらに軽く一杯程度の量です。アーモンド、くるみ、カシューナッツなど、様々な種類を組み合わせることで、良質な脂肪、タンパク質、ビタミンE、マグネシウムなどを摂取できます。
動物性タンパク質については、牛肉・豚肉・羊肉がわずか14グラム、鶏肉が29グラム、魚が28グラムと、かなり控えめな量が推奨されています。これは従来の欧米型の食事と比較すると大幅に少ない量であり、週に一度程度、小さめのステーキを食べる程度の赤身肉摂取量となります。卵については週に約1個半程度、乳製品は牛乳コップ1杯程度が推奨量です。
この推奨量を見ると、体積比で約半分を野菜と果物が占め、残りの半分を全粒穀物、植物性タンパク質、不飽和植物油、少量の動物性タンパク質で構成するという構造になっています。お皿の半分を野菜と果物で埋め、4分の1を全粒穀物、残りの4分の1を植物性または動物性タンパク質にするという視覚的なガイドラインを使うと、バランスが取りやすくなります。
科学的に証明された健康効果
医学誌「アメリカン・ジャーナル・オブ・クリニカル・ニュートリション」に掲載されたハーバード大学T.H. Chan公衆衛生大学院の研究では、20万6千人以上の食事データと健康記録を分析した結果、プラネタリーヘルスダイエットを忠実に実践した人は、実践しなかった人に比べて、早期死亡のリスクが30パーセント低かったことが明らかになりました。
この研究の信頼性は非常に高く、参加者は最長34年間、4年ごとに食事に関するアンケートに回答しており、長期的な健康効果が確認されています。20万人以上という大規模なサンプルサイズと、34年間という長期にわたる追跡調査により、科学的に信頼できるデータが得られています。
具体的には、がん、心臓病、肺疾患による死亡リスクも低いという結果が報告されています。これは、プラネタリーヘルスダイエットが推奨する食事内容が、慢性疾患の予防に効果的であることを示しています。現代社会における主要な死因である慢性疾患のリスクを、食事によって低減できることは大きな意義があります。
さらに、腸内環境の改善効果も期待できます。植物性食品に豊富に含まれる食物繊維は、腸内細菌の餌となり、善玉菌を増やすことに寄与します。また、発酵食品である味噌、納豆、醤油などは、プロバイオティクスとして腸内環境を整える効果があります。腸内環境の改善は、免疫機能の向上、精神的健康の維持、栄養素の吸収促進など、様々な健康効果につながることが知られています。
大豆製品に含まれるイソフラボンの摂取による女性ホルモンのサポートも期待できるとされています。イソフラボンは女性ホルモンと似た構造を持つ植物性エストロゲンとして知られており、更年期障害の症状緩和や骨密度の維持に役立つ可能性があります。
体重減少効果はどのように現れるか
プラネタリーヘルスダイエットによる体重減少効果については、個人の食生活の変化度合いによって大きく異なることが専門家によって指摘されています。このダイエットを始める前に何を食べていたかが重要な要素となります。
それ以前に高カロリーで飽和脂肪酸の多い食品を多く食べ、食物繊維をあまり摂っていなかった場合、プラントベース食品や脂肪分の少ないタンパク質に切り替えることで体重が減る可能性が高くなります。例えば、毎日のようにステーキやハンバーガー、揚げ物などを食べていた人が、魚や豆製品中心の食事に切り替えれば、自然とカロリー摂取量が減少し、体重減少につながります。
自然食品や加工度の低い食品に重点を置くことは減量に役立ちます。こうした食品は、高度に加工された食品に比べて、一般的に低カロリーで食物繊繊維が豊富であり、満腹感を高めつつ、カロリー摂取量を自然に減らすことにつながる可能性があります。全粒穀物、野菜、果物、豆類などは、同じボリュームでもカロリーが低く、食物繊維が豊富なため、満足感を得やすいのです。
ただし、専門家は、このダイエットをしたからといって「自動的に」体重が減るわけではないと繰り返し指摘しています。体重減少は、総カロリー摂取量と消費量のバランスによって決まります。植物性食品中心の食事に切り替えても、高カロリーの食品を大量に摂取したり、運動不足であったりすれば、体重減少は期待できません。
特に注意が必要なのは、ナッツ類、シード類、油、市販の代替肉のような食品です。これらは植物性食品であっても非常に高カロリーになる場合があり、大量に食べると体重増加を招く可能性があります。ナッツ類は健康的な脂肪、タンパク質、ビタミン、ミネラルを含む優れた食品ですが、一日50グラムという推奨量を守ることが重要です。50グラムを超えて摂取すると、知らず知らずのうちにカロリー過多になってしまう恐れがあります。
体重減少が現れるまでの期間について
多くの人が最も知りたいのは「どれくらいの期間で体重が減るのか」という点でしょう。しかし、2025年時点での研究では、体重減少効果が現れるまでの具体的な期間については明確には示されていません。長期研究では34年間にわたる健康効果の追跡が行われていますが、体重変化の時系列データは公表されていないのが現状です。
一般的なダイエットと同様に、個人の体質、運動習慣、食事の遵守度によって効果が現れる時期は異なると考えられます。通常のダイエットでは、適切なカロリー制限と運動を組み合わせた場合、最初の1ヶ月で1から2キロ程度の体重減少が健康的とされています。プラネタリーヘルスダイエットでも、同様のペースで体重が減少する可能性があります。
重要なのは、急激な体重減少を目指すのではなく、長期的に持続可能な健康的な食習慣を身につけることです。短期間で大幅に体重を減らすダイエットは、リバウンドのリスクが高く、健康に悪影響を及ぼす可能性があります。プラネタリーヘルスダイエットは、生涯にわたって続けられる食事法として設計されており、ゆっくりとしたペースでも確実に健康的な体重に近づいていくことが期待できます。
また、体重の数値だけでなく、体組成の変化にも注目することが大切です。植物性タンパク質と適度な運動を組み合わせることで、筋肉量を維持しながら脂肪を減らすことができます。体重計の数字が大きく変わらなくても、体脂肪率が下がり、筋肉量が増えることで、より健康的な体になっている可能性があります。
日本人に最適な実践方法
日本人がプラネタリーヘルスダイエットを実践する場合、洋食から和食に切り替えればよいというシンプルな方法が専門家によって提案されています。いわゆる一汁三菜で、ご飯(玄米推奨)とみそ汁(味噌は発酵食品)、主菜一品に副菜二品という構成が理想的とされています。
日本の伝統的な食事は、プラネタリーヘルスダイエットの推奨内容と非常に親和性が高い特徴を持っています。和食は元来、米を中心に、魚、豆類、野菜、海藻などをバランスよく取り入れた食事スタイルであり、動物性脂肪の摂取が比較的少ない傾向にあります。玄米ご飯、味噌汁、焼き魚、野菜の煮物、納豆、豆腐といった昔ながらの和食メニューは、まさにプラネタリーヘルスダイエットの理想的な実践例と言えます。
朝食では、ベーコンエッグトーストから納豆ご飯とわかめの味噌汁へ切り替えることが推奨されています。納豆は植物性タンパク質が豊富で、ビタミンK2や納豆菌による腸内環境改善効果も期待できます。わかめなどの海藻類はミネラルや食物繊維が豊富で、低カロリーです。
昼食は、ステーキランチから一汁三菜の和定食へ切り替えることで、大幅なカロリー削減と栄養バランスの改善が期待できます。焼き魚定食は、良質なタンパク質とオメガ3脂肪酸を摂取でき、野菜の煮物や海藻サラダと組み合わせることで、食物繊維やミネラルも豊富に摂取できます。
夕食は、牛肉ハンバーグから大豆ミートハンバーグへと変更することが提案されています。大豆ミートは近年、味や食感が大幅に改善されており、肉料理の代替として違和感なく楽しめるようになっています。ただし、市販の植物性代替肉製品については、添加物や塩分が多く含まれている場合があるため、製品の栄養成分表示を確認し、できるだけシンプルな原材料のものを選ぶことが推奨されます。
おやつについても、乳製品由来のケーキから小豆を使ったあんこの和菓子へと変えることが勧められています。和菓子は洋菓子に比べて脂肪分が少なく、小豆には食物繊維やポリフェノールが豊富に含まれています。ただし、砂糖の摂取量には注意が必要で、一日の推奨量は31グラムまでとされています。
栄養バランスの注意点と対策
プラネタリーヘルスダイエットは多くの健康効果が期待できる一方で、栄養バランス上の注意点もあります。国際農林水産業研究センターによる栄養再評価では、プラネタリーヘルスダイエットは動物性食品が少ないため、ビタミンB12、カルシウム、鉄、亜鉛が十分に供給されない可能性があることが指摘されています。
ビタミンB12は主に動物性食品に含まれる栄養素であり、神経系の正常な機能や赤血球の生成に重要な役割を果たします。野菜類にはあまり含まれていないため、植物中心の食事では不足しやすい栄養素の一つです。ビタミンB12を補うためには、魚介類を積極的に摂取することが推奨されます。しじみやあさりなどの貝類、イワシやさばなどの魚介類に多く含まれており、味噌汁に入れるなど簡単に取り入れることができます。
カルシウムについては、小魚、海藻類、大豆製品、緑黄色野菜などから摂取することができます。骨ごと食べられる小魚やちりめんじゃこは優れたカルシウム源です。また、豆腐や納豆などの大豆製品にもカルシウムが含まれています。乳製品の摂取が少ない場合、特に注意が必要な栄養素となります。
鉄分については、肉類だけでなく豆類にも含まれています。小松菜、ほうれん草などの緑黄色野菜にも鉄分が含まれており、ビタミンCと一緒に摂取することで吸収率が高まります。魚もタンパク質と鉄分の良い供給源となるため、適度に取り入れることが重要です。特に女性は鉄分が不足しやすい傾向があるため、意識的に摂取する必要があります。
亜鉛は免疫機能、タンパク質合成、創傷治癒などに関与する重要なミネラルです。魚介類、特に牡蠣には豊富に含まれています。また、ナッツ類や種子類にも含まれているため、推奨量を守りながら摂取することが大切です。
重要な点として、プラネタリーヘルスダイエットは完全なベジタリアン食やビーガン食ではありません。適度な魚介類や少量の肉、乳製品を取り入れることが推奨されています。これにより、不足しがちな栄養素を補うことができます。特にビタミンB12が不足しやすい方は、貝類や魚介類を積極的に摂取することが重要です。
成長期の子どもや妊娠中の女性、高齢者など、特定の栄養素が必要な人は、医師や栄養士と相談しながら実践することが望ましいでしょう。高齢者の場合は、タンパク質の必要量が増えることがあるため、植物性タンパク質だけでなく、適度な魚や鶏肉を取り入れることが重要です。
継続のためのコツと段階的アプローチ
プラネタリーヘルスダイエットを継続するためには、急激な変化ではなく、徐々に食習慣を変えていくことが栄養士によって推奨されています。急激な食生活の変化は、体が慣れるまでに時間がかかるだけでなく、挫折の原因にもなりかねません。体が慣れるまで、十分な時間を取ることが大切です。
例えば、週に数回は肉料理を大豆ミートや魚に置き換える、白米を玄米に変える、間食を和菓子やナッツにするなど、できることから始めることが大切です。最初の一週間は朝食だけを変える、次の週は昼食も変えるといったように、段階的に移行することで、無理なく新しい食習慣を身につけることができます。
完璧を目指すのではなく、できる範囲で実践することが長続きの秘訣です。特別な日やお祝いの席では、柔軟に対応することも大切です。完璧を目指してストレスを感じるよりも、普段の食事で基本を守り、特別な機会には楽しむというバランスが、持続可能な食生活につながります。
家族や友人と一緒に取り組むことで、モチベーションを維持しやすくなります。昭和女子大学では、学生が考案したプラネタリーヘルスダイエットに基づくメニューが学食に登場するなど、教育機関でも取り組みが広がっています。若い世代が環境と健康の両方を考えた食事について学び、実践することは、将来の持続可能な社会の実現に向けて重要な意味を持ちます。
推奨量を守るためには、食事の記録をつけることが有効です。最初の一週間は、食べたものとその量を記録することで、自分がどの食品グループをどれくらい摂取しているかを把握できます。スマートフォンのアプリを使うと便利です。
また、計量カップや計量スプーン、キッチンスケールを使って、食品の量を正確に測ることも重要です。特に最初のうちは、推奨量がどれくらいの見た目なのかを覚えるために、計量することをお勧めします。慣れてくれば、目分量でも大体の量が分かるようになります。
食材選びと調理方法の工夫
全粒穀物を選ぶ際は、玄米、全粒粉のパン、オートミール、雑穀米などが推奨されます。これらは精製穀物に比べて食物繊維が豊富で、血糖値の上昇も緩やかです。ビタミンB群、マグネシウム、鉄などのミネラルも豊富に含まれています。白米や白パンではなく、未精製の穀物を選ぶことが重要なポイントとなります。
野菜は色とりどりのものを選ぶことで、様々な栄養素を摂取できます。緑黄色野菜、葉物野菜、根菜類など、様々な種類の野菜を組み合わせることで、ビタミン、ミネラル、食物繊維、抗酸化物質などを幅広く摂取できます。季節の野菜を選ぶことで、栄養価が高く、価格も手頃で、環境負荷も低い選択ができます。
果物も同様で、春はいちご、夏はスイカやメロン、秋は梨やぶどう、冬はみかんといった旬の果物を選ぶことで、美味しく栄養豊富な食事が楽しめます。果物にはビタミン、ミネラル、食物繊維が豊富に含まれていますが、果糖も含まれているため、一日200グラムという推奨量を守ることが大切です。
ナッツ類は無塩のものを選び、一日50グラムという推奨量を守ることが重要です。アーモンド、くるみ、カシューナッツ、ピスタチオ、マカダミアナッツなど、様々な種類を組み合わせることで、栄養バランスが向上します。ナッツはカロリーが高いため、推奨量を守ることが体重管理のために重要です。
動物性タンパク質の摂取量は控えめにしながらも、質の良いものを選ぶことが推奨されています。魚については、持続可能な漁業で獲られたものを選ぶことが理想的です。小型の青魚であるイワシ、サバ、アジなどは、環境負荷が比較的低く、栄養価も高いため推奨されています。これらの魚には、心臓血管の健康に有益なオメガ3脂肪酸が豊富に含まれています。
鶏肉は比較的環境負荷が低い動物性タンパク質源とされています。赤身肉は環境負荷が高く、過剰摂取は健康リスクも高まるため、週に一度程度、小さめのステーキを食べる程度に控えることが推奨されています。
調理方法を工夫することで、より健康的で美味しい食事を楽しむことができます。油を使った調理は控えめにし、蒸す、煮る、焼くといった調理法を中心にすることが推奨されます。野菜の旨みを引き出すために、だしをしっかりとることも和食の基本です。昆布や鰹節から取っただしは、化学調味料を使わなくても深い旨みを引き出すことができます。
味付けは、塩分を控えめにし、醤油、味噌、酢、レモン汁、ハーブ、スパイスなどを上手に使って風味をつけることが大切です。素材本来の味を楽しむことで、調味料の使用量を減らすことができます。
外食時の選択と柔軟性
外食する際も、プラネタリーヘルスダイエットの原則を意識することができます。和食レストランでは、定食を選び、白米を玄米に変更できるか尋ねてみましょう。魚定食や豆腐料理は理想的な選択です。一汁三菜のスタイルの定食であれば、自然とバランスの良い食事ができます。
洋食レストランでは、サラダを大盛りにし、メインディッシュは魚料理や野菜料理を選ぶと良いでしょう。パスタを選ぶ場合は、全粒粉パスタがあるか尋ね、野菜たっぷりのトマトソースベースのものを選ぶことが推奨されます。クリームソースやチーズたっぷりの料理は、高カロリーで飽和脂肪酸が多いため、控えめにすることが望ましいです。
ファストフードでは、サラダボウルや豆を使ったメニュー、植物性バーガーなどの選択肢があれば選びましょう。飲み物は砂糖入りのソーダではなく、水やお茶を選ぶことが重要です。加糖飲料は、気づかないうちに大量の砂糖を摂取してしまう原因となります。
完璧を目指す必要はありません。外食や特別な機会には柔軟に対応し、普段の食事で基本を守ることが大切です。持続可能性は、長く続けられることが何よりも重要です。プラネタリーヘルスダイエットは、厳格なルールではなく、ガイドラインとして理解することが重要です。毎日完璧に推奨量を守ることよりも、一週間単位でバランスを取ることを目指す方が、長続きしやすくなります。
環境への貢献という視点
プラネタリーヘルスダイエットが他のダイエット法と大きく異なるのは、環境への影響を明確に考慮している点です。畜産業は温室効果ガス排出の主要な源の一つであり、特に牛肉の生産は多くの環境負荷を伴います。動物性食品の消費を減らし、植物性食品を中心とした食事に切り替えることで、個人レベルでも気候変動対策に貢献できます。
また、地産地消を心がけることで、食品の輸送にかかるエネルギーやCO2排出を削減できます。地元で生産された食材を選ぶことは、地域経済の支援にもつながります。旬の野菜や果物を選ぶことは、季節外れの食材を栽培するために必要なエネルギーを節約することにもつながります。
食品ロスの削減も重要な視点です。プラネタリーヘルスダイエットでは、適切な量を摂取することが推奨されており、これは食品ロスの削減にもつながります。必要な量だけを購入し、調理し、食べることで、無駄を減らすことができます。計画的に買い物をし、食材を上手に保存し、残り物を活用することは、経済的にも環境的にも有益です。
プラネタリーヘルスダイエットは、2050年までに世界人口が100億人に達すると予測される中で、すべての人に健康的な食事を提供しながら、地球環境を守るために提案された食事法です。現在の食糧システムを続けていては、環境破壊が進み、将来世代に持続可能な地球を残すことができません。個人が食生活を変えることは、大きな社会変革の第一歩となります。
専門家による総合評価
栄養士による評価では、プラネタリーヘルスダイエットは全体的に健康的で、栄養のバランスが非常に良く、心臓血管疾患やガンの予防に非常に効果的とされています。ただし、微量栄養素の不足リスクを理解し、適切に補うことが重要であるとも指摘されています。
プラネタリーヘルスダイエットと地中海式ダイエットとの類似性も指摘されています。どちらも植物性食品を中心とし、全粒穀物、野菜、果物、豆類、ナッツを豊富に摂取し、魚を適度に取り入れ、赤身肉を控えめにするという特徴があります。地中海式ダイエットで推奨されるオリーブオイルの使用も、プラネタリーヘルスダイエットにおける不飽和脂肪酸を含む植物油の推奨と一致します。
ただし、プラネタリーヘルスダイエットは、環境への影響をより明確に考慮している点で、地中海式ダイエットとは異なります。個人の健康だけでなく、地球環境の持続可能性という視点を組み込んでいることが、このダイエットの最大の特徴と言えるでしょう。
まとめ
プラネタリーヘルスダイエットの体重減少効果については、個人の食生活の変化度合いによって大きく異なり、具体的な期間は明確には示されていません。しかし、高カロリーで飽和脂肪酸の多い食事から切り替えることで、自然な体重減少が期待できます。重要なのは、急激な体重減少を目指すのではなく、長期的に持続可能な健康的な食習慣を身につけることです。
早期死亡リスクを30パーセント低減させるという研究結果は、このダイエットの長期的な健康効果を示す重要な証拠となっています。がん、心臓病、肺疾患による死亡リスクの低減も確認されており、慢性疾患の予防という観点からも非常に重要な知見です。
日本人にとっては、伝統的な和食に回帰することがプラネタリーヘルスダイエットの実践につながります。玄米、味噌汁、焼き魚、納豆、豆腐、野菜の煮物といった昔ながらのメニューを現代に取り戻すことが、健康と環境の両方に貢献する道となります。一汁三菜という和食の基本形は、プラネタリーヘルスダイエットの推奨と完璧に一致します。
栄養バランス上の注意点として、ビタミンB12、カルシウム、鉄、亜鉛などの微量栄養素が不足する可能性があることを理解し、魚介類や適度な動物性食品を取り入れることで補うことが重要です。プラネタリーヘルスダイエットは完全なベジタリアン食ではなく、適度な魚介類や少量の肉、乳製品を取り入れることが推奨されています。
実践にあたっては、急激な変化ではなく段階的に取り組むこと、完璧を目指さず柔軟に対応すること、家族や友人と一緒に楽しみながら続けることが成功の鍵です。体が慣れるまで十分な時間をかけ、無理のない範囲で実践することが大切です。
環境への配慮と健康維持を両立させるプラネタリーヘルスダイエットは、気候変動や環境問題が深刻化する現代において、個人ができる重要な貢献の一つです。食を通じて持続可能な社会の実現に参加することは、未来の世代に健康な地球を残すための責任ある行動と言えるでしょう。
科学的根拠に基づいた食事法として、プラネタリーヘルスダイエットは今後ますます重要性を増していくと予想されます。体重減少の効果だけでなく、長期的な健康効果と環境保護という大きな視点を持つこのダイエットは、これからの時代に適した食事法として、多くの人々に支持されることでしょう。
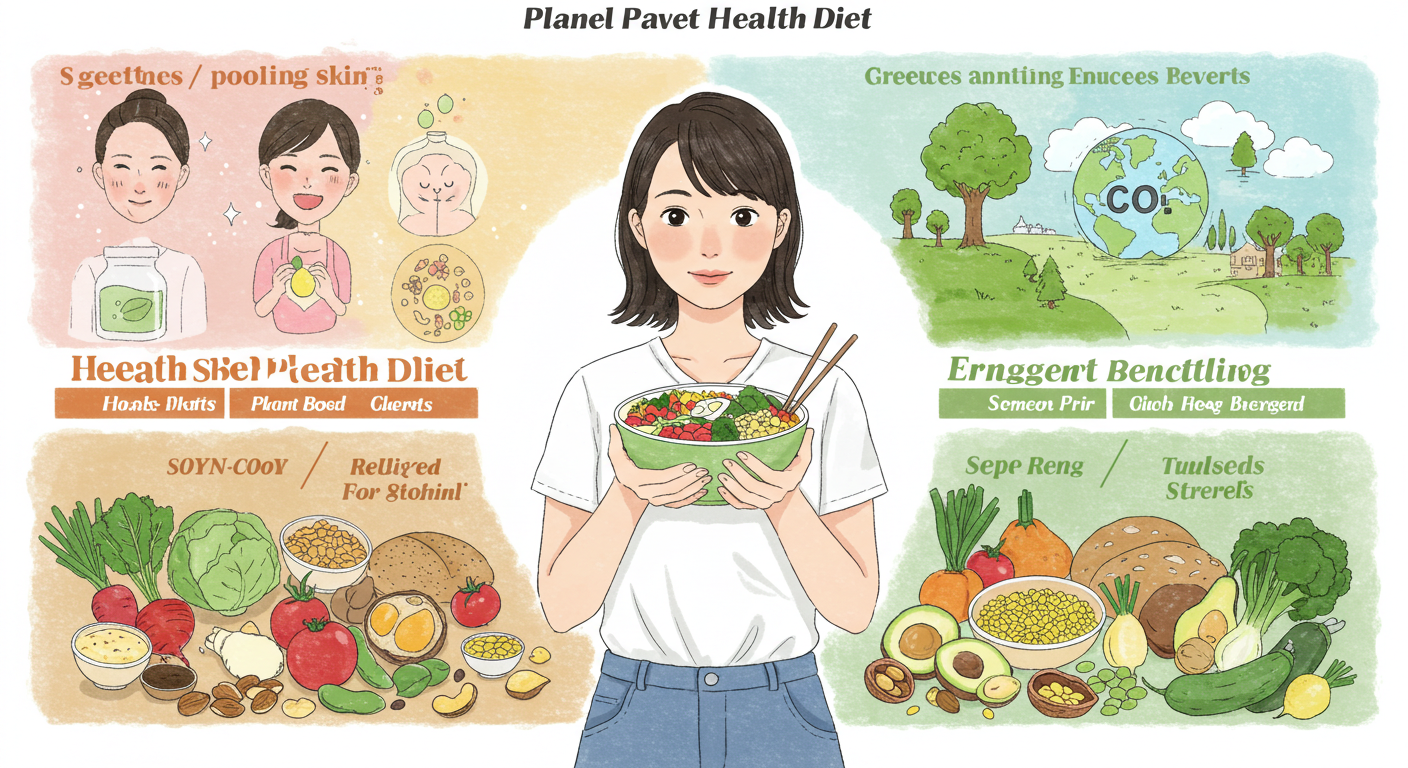


コメント