YouTubeには、アーティストの公式ミュージックビデオからユーザー作成の動画まで、膨大なコンテンツが存在します。その中で、CD音源やライブ音源などを無断でアップロードしたと思われる動画が散見されます。これらの行為は著作権法に違反する可能性が高いにもかかわらず、なぜ削除されずに残り続けているのでしょうか。本稿では、YouTubeにおける音楽の無断アップロードの違法性と、それらが削除されない背景の複雑な仕組み、権利者側の戦略、そして現代のクリエイターが取るべき具体的な生存戦略について、国際的な枠組みや最新技術の動向も交えながら、深く掘り下げて解説していきます。
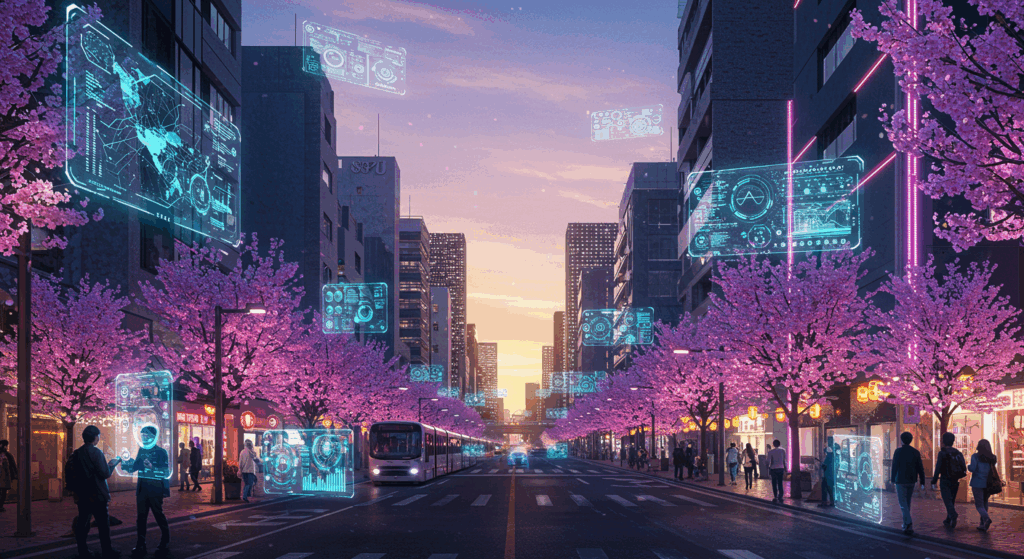
著作権の基本原則と国際的な枠組み
著作権とは、小説、音楽、絵画、映画、プログラムといった「著作物」を創作した者に法律上与えられる権利の束です。これには、作品を複製する権利(複製権)、インターネットを通じて公開する権利(公衆送信権)、作品を改変する権利(翻案権)などが含まれます。重要なのは、著作権が「思想又は感情を創作的に表現したもの」に与えられるという点です。単なる事実やデータ、アイデアそのものには著作権は発生しません。
音楽コンテンツが特に複雑なのは、「著作権」に加えて「著作隣接権」が絡むためです。著作隣接権とは、著作物を公衆に伝達する上で重要な役割を果たす実演家、レコード製作者、放送事業者に与えられる権利です。CD音源を例に取ると、作詞家・作曲家の「著作権」、歌手・演奏家の「著作隣接権」、そしてレコード製作者の「著作隣接権」が重層的に存在します。YouTubeにCD音源をアップロードする行為は、これらの権利を同時に侵害する可能性があり、権利関係が極めて複雑になるのです。
「海外の楽曲なら大丈夫だろう」という考えは通用しません。日本を含む世界180カ国以上が加盟する「ベルヌ条約」により、著作権は国境を越えて保護されます。この条約は、加盟国が他の加盟国の国民の著作物を自国民と同様に保護する「内国民待遇の原則」と、作品が創作された時点で自動的に権利が発生し、登録などの手続きが不要な「無方式主義」を定めています。これにより、日本のコンテンツは海外で、海外のコンテンツは日本で、相互に保護されるのです。
なぜ無断アップロード動画は削除されないのか?
違法であるにもかかわらず、多くの無断アップロード動画が存在する背景には、YouTubeの「Content ID」というシステムと、権利者の戦略的な判断が大きく関わっています。Content IDは、著作権者が自身のコンテンツの参照ファイルを登録し、アップロードされる全動画を自動スキャンして一致するものを照合する、いわば「デジタル指紋照合システム」です。ただし、このシステムは、相当量のオリジナルコンテンツの独占的権利を持つ大規模な権利者のみが利用を承認されています。
Content IDを利用できない一般クリエイター向けには、「Copyright Match Tool」が提供されています。これは、自身の動画と完全に、またはほぼ完全に一致する再アップロード動画を検出するツールです。検出された場合、クリエイターは動画の削除をリクエストできますが、Content IDのような収益化の選択肢はありません。
Content IDで一致が検出された場合、権利者には「ブロック(視聴不可にする)」「収益化(広告を掲載し収益を得る)」「追跡(統計情報を監視する)」という3つの選択肢が与えられます。多くの無断アップロード動画が削除されずに残っている最大の理由は、権利者が「ブロック」ではなく「収益化」を選択しているケースが多いからです。権利者が収益化を選ぶ背景には、UGC(ユーザー生成コンテンツ)を完全に撲滅するのは非現実的であるため、それを新たな収益源として活用する方が経済的に合理的という判断や、ファンによる動画が楽曲のプロモーションとして機能することへの期待があります。
権利者ごとの方針も様々です。例えば、ユニバーサルミュージックグループはContent IDを積極的に活用し、Mrs. GREEN APPLEの音源利用に関する詳細なガイドラインを公開しています。一方で、エイベックスは著作権管理に厳しい姿勢で知られ、原則として無断利用を認めていません。また、スクウェア・エニックスはゲームタイトルごとに詳細な利用許諾条件を提示しています。つまり、動画が削除されないのは、権利者が見逃しているのではなく、その管理下で戦略的に泳がされている状態と理解するのが適切です。
YouTube ShortsとAI生成音楽という新たな潮流
YouTube Shortsでは、長編動画とは異なる独自の音楽ライセンスと収益分配モデルが採用されています。クリエイターは公式の音源ライブラリから楽曲を手軽に使用できますが、その収益分配は複雑です。Shortsの広告収益は一度「クリエイタープール」にまとめられ、そこから音楽のライセンス費用が支払われます。驚くべきことに、動画に音楽を1曲使用した場合は収益の50%、2曲使用した場合は約66%がライセンス費用として差し引かれます。残った金額が再生回数に応じて分配され、最終的にその45%がクリエイターの収益となるため、手軽さの反面、取り分はかなり少なくなります。
SunoやUdioに代表される音楽生成AIの著作権の扱いも、新たな火種となっています。2025年現在、日本の著作権法では、AIが自律的に生成しただけの音楽に著作権は発生しないというのが一般的な見解です。しかし、最も大きな問題は、AIの学習データに既存の著作物が無断で使用されている疑惑です。2025年には米レコード協会がSunoなどを著作権侵害で提訴しており、この問題は今後さらに大きくなる可能性があります。
クリエイターが取るべき具体的な自衛策
安全な音源を確保するためには、ロイヤリティフリー音楽サイトの活用が有効です。例えば、Artlistは高品質なシネマティック音源、Epidemic Soundはボーカル曲の豊富さ、Audiostockは日本人向け楽曲の多さや単品購入が可能といった強みがあります。これらのサイトからライセンスを取得したにもかかわらず、Content IDの申し立てが来た場合は、「異議申し立て」をすることが重要です。その際、「この楽曲は『サイト名』から正当なライセンスを取得して使用しています」といったように、具体的な根拠を提示する必要があります。
また、著作物の利用において、「フェアユース」と「引用」の区別は厳密に行わなければなりません。フェアユースは米国の柔軟な規定ですが、音楽を単にBGMとして使うだけではまず認められません。日本の著作権法にはフェアユースはなく、より厳格な「引用」の要件(主従関係、明確な区分、出所の明示など)を全て満たす必要があります。安易な判断は極めて危険です。
権利管理と法的手続きの実際
日本には主にJASRACとNexToneという2つの音楽著作権管理団体が存在します。JASRACが信託契約で権利者として訴訟を行うのに対し、NexToneは委任契約で権利は著作者のままであるなど、契約形態や管理範囲に違いがあります。
万が一、著作権侵害で訴えられた場合、警告書の送付、発信者情報開示請求、そして損害賠償を求める民事訴訟や、悪質な場合は刑事告訴といった法的手続きが進みます。近年は「ファスト映画」問題を機に権利侵害への目が厳しくなっており、改正プロバイダ責任制限法によって侵害者の特定も容易になっています。軽い気持ちのアップロードが、深刻な法的トラブルに発展するリスクは、かつてなく高まっています。
著作権侵害の申し立てと異議申し立ての実例
YouTubeでの著作権侵害の申し立ては、主に「Content IDによる自動検出」と「著作権者からの手動申し立て」の2種類です。特に注意すべきは、ライセンスを購入したフリー音源や自作のクラシック演奏に対し、システムが誤って申し立てを行う「巻き込み」や、第三者が権利のない楽曲で収益を得ようとする「著作権詐欺」です。
不当な申し立てには、泣き寝入りせずに「異議申し立て」を行いましょう。申し立てから5日以内に異議申し立てをすれば、係争中の広告収益はYouTubeに保留され、最終的に権利者に支払われます。多くのクリエイターが、JASRACのデータベース情報やライセンス証明書を提示することで、不当な申し立ての撤回に成功しています。
著作権侵害をめぐる裁判事例
過去の裁判事例は重要な教訓となります。個人がカラオケで歌う姿をアップロードした行為が著作隣接権侵害とされた「カラオケ動画アップロード事件」や、人気YouTuberがBGMの無断使用で巨額の損害賠償を請求された「ミシェル・ファン事件」は、他者が制作した音源の無断利用が明確な権利侵害であり、極めて高額な賠償に繋がるリスクを示しています。これらの事例から、クリエイターは慎重に行動する必要性を学ぶべきです。
結論として、YouTubeで音楽の無断アップロード動画が削除されない背景には、Content IDを通じた権利者の戦略的な「収益化」があります。しかし、それは決して違法行為の容認ではありません。クリエイターは、著作権の知識を身につけ、ロイヤリティフリー音源の活用や適切なライセンス管理といった具体的な自衛策を講じなければ、淘汰される時代に来ています。安易なアップロードがチャンネルの存続そのものを脅かすリスクであることを、常に認識しておくべきでしょう。


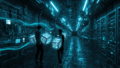
コメント