2025年10月30日から11月9日にかけて、東京ビッグサイトで開催されるJapan Mobility Show 2025は、日本の自動車産業が世界に向けて新たなビジョンを示す重要な舞台として注目を集めています。今回のイベントでは、単なる新型車の展示にとどまらず、電動化技術やソフトウェア技術の進化、そして社会課題の解決を目指すモビリティの姿が明らかになります。特に日本メーカーが推進するマルチパスウェイ戦略は、バッテリーEV一辺倒ではなく、水素エンジンや燃料電池車、合成燃料など多様な選択肢を提示するという点で、世界の潮流とは一線を画す独自のアプローチとして注目されています。本記事では、Japan Mobility Show 2025の見どころから注目展示、そして最新技術まで、包括的に解説していきます。これからモビリティの未来を占う上で欠かせない情報を、詳しくお届けしましょう。

- モビリティショーへの変革が示す新時代の到来
- トヨタとレクサスが示すマルチパスウェイの真髄
- 日産が追求する電動化と知能化の深化
- Hondaが描く陸海空を超えた夢の世界
- ヤマハが提案する人と機械の新たな関係性
- スズキとダイハツに見る生活密着型モビリティの価値
- マツダとスバルが守り抜く走る歓びの系譜
- 中国BYDの全方位攻勢が示す本気度
- ドイツプレミアムブランドが描く電動ラグジュアリーの未来
- 全固体電池が切り開く電動化の新章
- 水素と合成燃料が拓くもう一つの脱炭素化の道
- 自動運転技術の実用化が目前に迫る物流革命
- ソフトウェア・デファインド・ビークルを支える基盤技術
- 商用車分野に見る物流の未来像
- 社会課題解決に向けたモビリティの役割
- スタートアップとの共創が生み出す新たな価値
- マルチパスウェイ戦略の本質と意義
- ソフトウェアが価値を定義する時代の到来
- Japan Mobility Show 2025が示す未来への羅針盤
モビリティショーへの変革が示す新時代の到来
かつて東京モーターショーとして知られていたこのイベントは、Japan Mobility Showへと名称を変更し、その本質も大きく変化しました。この変更は単なるブランドイメージの刷新ではありません。自動車産業が直面する構造的な変化に対応するための、戦略的な再配置と言えるでしょう。従来の自動車メーカー主導の製品発表の場から、業界の垣根を越えた共創プラットフォームへと進化を遂げたのです。
出展者数の推移を見ても、その変化は明らかです。2019年の東京モーターショーでは192社だった出展者が、2023年のJapan Mobility Showでは475社へと倍増し、2025年にはさらなる記録更新が見込まれています。増加した出展者の多くは、従来の自動車メーカーや部品サプライヤーだけでなく、スタートアップ企業やIT企業、さらには異業種からの参入も目立ちます。これは未来のモビリティが自動車単体で完結するものではなく、エネルギーや通信、都市計画、各種サービスといった広範なエコシステムの中で創造されるという認識が深まっていることを示しています。
Japan Mobility Show 2025は、#FUTURE、#CULTURE、#CREATIONという3つの主要テーマを軸に展開されます。この三本柱の構造は、多様化する来場者の関心に応え、ショー全体の価値を最大化するための巧みな設計と言えるでしょう。FUTUREでは次世代技術や未来のコンセプトが提示され、CULTUREでは自動車やバイクが持つ根源的な魅力が伝えられ、CREATIONでは大企業とスタートアップが出会い新たなビジネスを創出する場が設けられています。
特に注目すべきは、没入型体験プログラムTokyo Future Tour 2035です。このプログラムでは、来場者が見て触れて乗って未来を体感できるよう設計されており、2023年開催時に高い評価を得た企画の第2弾となります。2035年という時間軸の設定は意図的で、SFのような遠い未来ではなく、しかし現在から確実に進化した変革を提示するのに絶妙な近未来を描いています。150社以上という前回を上回る企業や団体が参加し、未来の東京を会場内に再現します。空飛ぶモビリティによる移動体験やAIが日常に溶け込んだ生活、ユーザーのアイデアで自在に姿を変えるモビリティなどが具体的に提示され、専門家だけでなく幅広い層が未来への期待感を共有できる内容となっています。
トヨタとレクサスが示すマルチパスウェイの真髄
Japan Mobility Show 2025におけるトヨタとレクサスの展示は、同社が掲げるマルチパスウェイ戦略の具現化として大きな注目を集めています。これはカーボンニュートラル達成への道筋は一つではないという思想に基づき、バッテリーEVだけでなく多様な選択肢を追求する戦略です。
トヨタの最大の注目点は、次世代BEV技術の進化と全固体電池の実用化に向けた動きです。住友金属鉱山との共同開発契約の発表は、トヨタがこの分野でゲームチェンジを狙っていることを明確に示しています。全固体電池は充電時間の大幅短縮、航続距離の延伸、そして安全性の向上という点で、既存のリチウムイオン電池を大きく上回るポテンシャルを秘めています。この技術が実用化されれば、電気自動車の普及における最大のボトルネックの一つが解消され、市場の様相は一変するでしょう。
さらに注目すべきは、水素エンジンや合成燃料への取り組みです。燃料電池車に加えて、水素を直接燃焼させる水素エンジン技術は、既存の内燃機関技術やサプライチェーンを活用しつつCO2排出をゼロにできる現実的な選択肢として位置づけられています。また合成燃料に関する取り組みも、世界中に存在する膨大な数の既存エンジン車を脱炭素化する手段として重要性が高まっています。これらの技術は、一部の新車だけでなく既存の車両資産全体の脱炭素化を視野に入れた、極めて現実的なアプローチと言えます。
静岡県で建設が進む実証都市Woven Cityの進捗報告も見逃せません。この未来都市では、多様な技術が実際の生活環境でどのように統合され機能するのかをリアルに検証しており、その成果がJapan Mobility Show 2025で披露されることで、単なるコンセプトではなく実装可能な技術としての説得力が増すでしょう。
レクサスブランドにおいては、バッテリーEV専用モデル「RZ」や、2026年の導入が計画される次世代BEVコンセプト「LF-ZC」を通じて、電動化とブランドの核である高級感やパフォーマンスをいかに融合させるかが示されます。レクサスは単に環境性能を追求するだけでなく、ラグジュアリーブランドとしての価値をどのように電動化時代に引き継ぐかという課題に真正面から取り組んでいるのです。
日産が追求する電動化と知能化の深化
日産自動車は、Japan Mobility Show 2025において、自社のコアコンピタンスである電動化と知能化技術のさらなる深化を明確に打ち出します。日産の戦略は、技術的な先進性と実用性のバランスを重視した独自の道を歩んでいます。
新型エルグランドのワールドプレミアは、その中核に第3世代へと進化したe-POWERを搭載することが示唆されており、日産独自のシリーズハイブリッド技術への強いコミットメントを示しています。e-POWERは、エンジンを発電専用とし、駆動は完全にモーターで行うという独特のシステムで、電気自動車のような滑らかな走行感覚と、充電インフラに依存しない利便性を両立させています。この第3世代では、さらなる効率向上と静粛性の向上が期待されており、日産のハイブリッド戦略における重要なマイルストーンとなるでしょう。
バッテリー容量を78kWhに拡大し、航続距離702kmをWLTCモードで達成した新型リーフの展示も、BEVのパイオニアとしての地位を改めて主張する技術的な快挙です。初代リーフの登場から15年近くが経過した今、航続距離への不安という電気自動車普及の最大の障壁を克服しつつあることを示す象徴的なモデルと言えます。
さらに日産は、Mobility Servicesエリアにおいて、単なる車両販売から車内での体験やサービスの提供へと戦略をシフトしていることを明確に示します。車内エンターテインメントシステム「AutoDJ」のようなコンテンツや、ロボット「エポロ」による案内サービスは、ソフトウェア・デファインド・ビークル時代における新たな価値創造の方向性を示唆しています。また先進安全自動車の公道試乗会は、日産の先進運転支援システムの進化を来場者が直接体感できる貴重な機会となり、技術の実用性を肌で感じることができるでしょう。
Hondaが描く陸海空を超えた夢の世界
Hondaの展示は、同社が単なる自動車メーカーではなく、総合的なエンジニアリング企業であるという強力なブランドアイデンティティを体現するものとなります。Hondaの展示空間に足を踏み入れれば、陸上の乗り物だけでなく、空や宇宙にまで広がる技術の世界に触れることができます。
Honda 0シリーズの新たなプロトタイプのワールドプレミアは、HondaのEV戦略の核として位置づけられています。このシリーズは「ゼロからのEV創出」を掲げ、従来の自動車の制約から解放された空間価値、効率性、そして新たなデザイン言語を追求しています。電気自動車は内燃機関車と比べて機械的な制約が少ないため、車内空間の使い方や車両のプロポーションを根本から見直すことができます。Honda 0シリーズは、その可能性を最大限に引き出すことを目指しており、従来の自動車の常識を覆すような提案が期待されます。
Hondaの電動化への取り組みは四輪車だけにとどまりません。小型EVプロトタイプや二輪EVコンセプト、さらには電動アシストマウンテンバイクe-MTBまで、その展示は多岐にわたります。これはあらゆる人々の移動を電動化するというHondaの多角的なアプローチを示しており、モビリティの定義そのものを広く捉える同社の姿勢が表れています。
特に興味深いのは、自動車とは一見無関係に見える展示です。持続可能なロケットの実験機やHondaJetのインテリアモックアップの展示は、Hondaの高度な技術力と未来への壮大なビジョンを社会に印象付けるための戦略的な演出と言えます。これらは単なる技術のショーケースではなく、Hondaが目指す「地球圏を超えた移動の自由」というブランドメッセージを強烈に伝える役割を果たしています。
また往年の名車プレリュードをハイブリッドのスペシャリティスポーツとして復活させることは、電動化時代においても「操る喜び」を追求し続けるというブランドの意思表示に他なりません。環境性能と走行性能は決して対立するものではなく、むしろ電動化技術を活用することでより高次元の運転の楽しさを実現できるというメッセージが込められています。
ヤマハが提案する人と機械の新たな関係性
ヤマハ発動機のテーマ「感じて動きだす」は、同社がモビリティの体験的価値、すなわち感動をいかに重視しているかを端的に表しています。ヤマハの展示は、技術的なスペックや効率だけでは測れない、人と機械との情緒的な繋がりを追求する姿勢が際立っています。
MOTOROiD:Λ(ラムダ)のワールドプレミアは、Japan Mobility Show 2025全体の中でも特に注目すべき展示の一つです。このAIモーターサイクルは、乗り手を認識し、自らバランスを取り、そしてオーナーと共に成長するというコンセプトを掲げています。これは人と機械の関係性を根底から問い直す野心的な試みであり、単なる移動手段としてのバイクではなく、パートナーとしての新たな存在意義を探る実験的なモデルと言えるでしょう。AIが乗り手の癖や好みを学習し、より快適な乗り心地を提供していく様は、まるでペットや相棒のような関係性を想起させます。
3輪手動操舵を備えた3輪オープンEVコンセプトTRICERA protoも、ヤマハらしい独創性に満ちた提案です。この3輪操舵システムにより、従来の二輪車や四輪車とは全く異なる新たな次元の人機一体感と運転の楽しさを体験できます。効率や利便性だけでなく、操縦するプロセスそのものを楽しむという視点は、ヤマハのブランドDNAの中核にある感性に訴えかけるモノづくりを象徴しています。
さらにヤマハは、トヨタと共同開発した水素エンジン搭載バイクのコンセプトモデルH2 Buddy Porter Conceptや、HEV、PHEVのプロトタイプも展示します。これはヤマハもまた、日本の産業界が共有するマルチパスウェイという大きな潮流の中にいることを示しており、環境対応技術の開発においても多様なアプローチを探求していることが分かります。
スズキとダイハツに見る生活密着型モビリティの価値
スズキとダイハツは、Japan Mobility Show 2025において、人々の日常生活を支える実用的なモビリティを提案します。両社の展示は、華やかなコンセプトカーや最先端技術のデモンストレーションとは一線を画し、実際の生活シーンに根差した現実的なソリューションを提示しています。
スズキは「By Your Side」というテーマの下、軽乗用BEVコンセプトVision e-Sky、トヨタ・ダイハツと共同開発する商用軽バンEVe EVERY CONCEPT、そしてユニークな四脚モビリティMOQBA 2など、日本の市場環境とユーザーニーズに的確に応えるポートフォリオを展開します。特に軽自動車規格のEVは、日本の狭い道路事情や駐車スペースの制約、そして手頃な価格帯を求める市場ニーズに完璧にマッチする製品と言えます。また水素エンジンを搭載したスクーターバーグマンの展示も、マルチパスウェイへの取り組みを示すものであり、二輪車分野においても多様な脱炭素化の選択肢を模索しています。
ダイハツは、日本の高齢化社会という喫緊の課題に正面から向き合う展示が中心となります。福祉車両フレンドシップシリーズや、歩行領域をサポートするモビリティe-SNEAKERは、高齢者や移動に制約のある人々の自由な移動を確保するという社会的意義の大きい分野への注力を示しています。これは成長市場であるシルバーマーケットをターゲットとする明確な事業戦略でもあり、社会貢献とビジネスの両立を図る好例と言えるでしょう。超高齢社会においては、移動の自由を確保することが生活の質を維持する上で極めて重要であり、ダイハツの取り組みはその課題に対する具体的な回答となっています。
マツダとスバルが守り抜く走る歓びの系譜
マツダとスバルは、電動化の大きな波の中で、いかにしてブランドの核である「走る歓び」を維持し進化させるかという課題に取り組んでいます。両社の詳細なワールドプレミアは未発表ながら、その企業哲学と近年の動向から戦略は明確に読み取れます。
マツダは2023年のJapan Mobility Showでロータリーエンジン技術を活用したコンセプトICONIC SPを展示しており、その進化形や関連技術の展開が期待されています。マツダが長年培ってきたロータリーエンジン技術は、水素燃料との相性が良いとされており、この独自技術を活かした環境対応車の開発は、マツダならではのアプローチとして注目されています。また人馬一体の走行感覚を追求する同社の哲学は、電動化時代においても決して色褪せることなく、むしろ電動パワートレインの瞬時のレスポンスを活かした新たな走りの楽しさの創出に繋がる可能性を秘めています。
スバルは、STIパフォーマンスパーツを装着したモデルや、SUPER GT、ニュルブルクリンク24時間レースへの参戦車両を前面に押し出すことで、モータースポーツで培われた技術とパフォーマンスイメージをブランドアイデンティティの中核に据え続ける姿勢を鮮明にしています。スバルの特徴である水平対向エンジンやシンメトリカルAWDといった技術的な強みを、電動化時代にどのように進化させ継承していくかが、今後の大きなテーマとなるでしょう。
中国BYDの全方位攻勢が示す本気度
中国のBYDがJapan Mobility Show 2025で見せる存在感は、日本市場に対する彼らの本気度を物語っています。乗用車と商用車の両部門で大規模なブースを展開し、包括的な市場参入戦略を明確に示しています。
合計13台の車両展示、その中にはワールドプレミア3台、ジャパンプレミア4台が含まれるという計画は、単にグローバルモデルを輸出するのではなく、日本市場のニーズを意識した製品開発を行っていることの証です。「DOLPHIN」「SEAL」「SEALION 7」といった既存モデルでブランド認知を高めつつ、初公開モデルで市場に新たなインパクトを与える戦略が読み取れます。
BYDの技術的な中核となるのは、独自開発のブレードバッテリーです。このバッテリーは高い安全性と優れたエネルギー密度、そして構造体としての役割も果たすことによるスペース効率の良さを特徴としています。特に大型EVバスK8では、この技術によりフラットな床面と十分な航続距離を両立させており、BYDの技術的優位性をアピールする上で重要な要素となっています。
彼らのスローガン「eモビリティを、みんなのものに。」は、その戦略がプレミアムセグメントだけでなくマスマーケット全体をターゲットにしていることを示唆しています。価格競争力と技術力を武器に、日本市場においても確実にシェアを拡大しようとするBYDの野心的な姿勢が、Japan Mobility Show 2025では如実に表れることでしょう。
ドイツプレミアムブランドが描く電動ラグジュアリーの未来
ドイツのプレミアムブランドであるメルセデス・ベンツとBMWは、電動化こそがラグジュアリーの未来であるという明確なメッセージを発信します。両社の展示は、環境性能と高級車としての価値を両立させる道筋を示すものとして注目されています。
メルセデス・ベンツは「Feel the Mercedes」をテーマに、4車種ものジャパンプレミアを予定しています。その筆頭が、AMGブランド初の完全電気自動車CONCEPT AMG GT XXです。これは電動化がパフォーマンスを犠牲にするものではなく、むしろ新たな次元へと引き上げるものであることを示す象徴的なモデルと言えます。AMGが長年培ってきた高性能車づくりのノウハウを電動化時代にどう継承し進化させるかが、このコンセプトカーに凝縮されています。
新型の電動CLAとGLCは、それぞれ新開発のEV専用プラットフォーム(MMAおよびMB.EA)をベースとしている点が極めて重要です。これは既存の内燃機関用プラットフォームを改良する段階から、EVに最適化された設計へと完全に移行したことを意味し、800Vアーキテクチャの採用による急速充電性能の向上など、技術的な飛躍を伴っています。高電圧システムにより充電時間が大幅に短縮され、長距離ドライブにおける利便性が格段に向上することが期待されます。
BMWもまた、最新のEVコンセプトNeue Klasse(ノイエ・クラッセ)シリーズを中心に、ソフトウェアとユーザーエクスペリエンスを重視した展示を行うと予想されます。「OK, BMW」で起動するインテリジェント・パーソナル・アシスタントや、スマートフォンで駐車を操作するリモート・コントロール・パーキングといった機能は、車が単なる移動機械からインテリジェントなデジタルデバイスへと進化していることを示しています。
全固体電池が切り開く電動化の新章
Japan Mobility Show 2025で示される電動化技術の中でも、特に注目すべきは全固体電池の商用化に向けた動きです。トヨタと住友金属鉱山の共同開発発表は、日本がこの分野で再び技術的優位性を確立するための切り札として全固体電池を位置づけていることを示唆しています。
全固体電池は、従来のリチウムイオン電池が液体の電解質を使用しているのに対し、固体の電解質を用いることで多くの利点を実現します。充電時間の大幅な短縮、航続距離の延長、そして液漏れや発火のリスクが極めて低い安全性の飛躍的向上という三つの特徴は、バッテリーEV普及における最大のボトルネックを解消する可能性を秘めています。
現在の電気自動車において、充電時間の長さと航続距離への不安は、ガソリン車からの乗り換えを躊躇させる大きな要因となっています。全固体電池が実用化されれば、わずか数分の充電で数百キロメートルの走行が可能となり、ガソリン車と遜色ない利便性を実現できるでしょう。この技術革新は、電気自動車市場の様相を一変させるゲームチェンジャーとなる可能性を持っています。
一方で、メルセデス・ベンツが示すMMAやMB.EAといったEV専用プラットフォームは、バッテリーEVの設計思想が成熟期に入ったことを示しています。内燃機関車の構造的制約から完全に解放されることで、より長いホイールベース、短いオーバーハング、そして広大な室内空間を実現し、バッテリーEVならではの価値を最大化できます。バッテリーを床下に配置することで低重心化が図られ、走行安定性も向上します。
水素と合成燃料が拓くもう一つの脱炭素化の道
バッテリーEV以外のカーボンニュートラル技術もまた、Japan Mobility Show 2025の重要な焦点です。これらは日本の産業界が持つ強みを活かし、多様なエネルギー事情やユーザーニーズに対応するための現実的な選択肢として提示されます。
水素燃焼エンジンは、ヤマハがトヨタと共同開発した「H2 Buddy Porter Concept」やスズキの「バーグマン」などで展示されます。水素を直接燃やすこの技術は、既存の内燃機関の製造基盤や技術者のスキルを活用できるという大きな利点を持っています。CO2を排出せず、かつエンジンならではの音や振動といった感覚的な魅力を残せるため、特にモーターサイクルやパフォーマンスカーの分野で魅力的な選択肢となります。
燃料電池車(FCV)の主戦場は、乗用車から大型商用車へとシフトしています。長距離走行や短い充填時間、そしてバッテリー式に比べて積載重量への影響が少ないといった利点から、特にトラック輸送に適しています。日野のプロフィア Z FCVはその代表例であり、物流業界における脱炭素化の有力な選択肢として位置づけられています。水素ステーションのインフラ整備が課題ではありますが、特定の幹線ルートに集中的にインフラを整備することで、実用化への道筋は現実的なものとなっています。
いすゞが世界初公開するマルチフューエルエンジンは、画期的なコンセプトです。軽油、天然ガス、水素、合成燃料といった複数の燃料に一つの基本設計で対応できるこのエンジンは、インフラの移行期において究極の柔軟性を運送事業者に提供します。各地域のエネルギー事情やインフラの整備状況に応じて最適な燃料を選択できるため、グローバルに展開する物流事業者にとって極めて実用的なソリューションとなるでしょう。
合成燃料(e-fuel)の開発も進んでいます。これは再生可能エネルギーを使って水素とCO2から合成される液体燃料で、既存のガソリンエンジンやディーゼルエンジンにそのまま使用できるドロップイン燃料として期待されています。世界中に存在する何億台もの既存車両を、一夜にして電動化することは不可能ですが、合成燃料を使用することで、これらの車両も脱炭素化の枠組みに組み込むことができます。
自動運転技術の実用化が目前に迫る物流革命
自動運転に関する議論は、かつての完全自動運転という壮大な夢から、より現実的で事業化可能な領域へとシフトしています。Japan Mobility Show 2025では、その実用化が目前に迫った具体的なソリューションが数多く展示されます。
商用車におけるレベル4自動運転の実現は、物流業界にとって革命的な意味を持ちます。日野のプロフィア Z FCV L4コンセプトは、高速道路の特定区間を無人で走行するコンセプトを提示しています。これは技術的にも法的にも実現可能性が高く、深刻なドライバー不足に悩む物流業界にとって即効性のある解決策となりうるでしょう。
具体的には、物流ハブから別の物流ハブまでの高速道路区間を自動運転トラックが走行し、一般道や市街地での配送は人間のドライバーが担当するというハブ・トゥ・ハブ方式が有力視されています。この方式であれば、走行環境が比較的単純な高速道路に限定されるため、技術的なハードルが下がり、早期の実用化が期待できます。また夜間の長距離輸送を自動運転に任せることで、24時間稼働が可能となり、輸送効率は劇的に向上します。
イノベーションの核心はソフトウェアにあります。ジェイテクトが展示するPairdriver®は、自動運転中の目標軌道への追従性を高めると同時に、ドライバーによる自然な操舵介入を可能にするソフトウェアソリューションです。これはシステムと人間の協調という、実世界における自動運転の重要な課題に取り組むものであり、Tier 1サプライヤーがシステムの頭脳を提供する時代が到来したことを示しています。
ソフトウェア・デファインド・ビークルを支える基盤技術
Japan Mobility Show 2025で展示される未来的なコンセプトカーの多くは、その根底にある基盤技術なしには成立しません。その主役が、ソフトウェア・デファインド・ビークル(SDV)を可能にする見えざるイノベーションです。
バイワイヤ技術は、機械的な結合を電気信号に置き換える技術の総称です。ジェイテクトのステア・バイ・ワイヤは、すでにレクサス「RZ」に搭載され市販化されています。ハンドルと車輪の間の機械的な結合をなくすことで、可変ギアレシオによる運転支援や、全く新しいコックピットデザインが可能になります。例えば低速時にはハンドルを少し回すだけで大きく曲がり、高速時には安定性を重視した設定にするといった、状況に応じた最適な操舵特性を実現できます。これは高度な自動運転システムにとって必須の技術でもあります。
同じくジェイテクトの転舵・駆動統合ユニットは、操舵、駆動、制動、後退の機能を一つのモジュールに集約する革新的な技術です。これにより車両設計の自由度は飛躍的に向上し、完全なフラットフロアを持つ広大な室内空間や、都市内を走行する自動運転シャトルのような特定目的車両の実現を容易にします。従来の車両では、エンジンやトランスミッション、プロペラシャフトといった駆動系部品が室内空間を圧迫していましたが、これらを四隅のホイール部分に集約することで、設計の自由度が格段に高まります。
格納式ステアリングコラムも注目の技術です。自動運転中にステアリングホイールがダッシュボード内に完全に格納されることで、車内は運転席から移動するリビング空間へとその意味を根本的に変えることができます。長距離移動中に仕事をしたり、家族と向かい合って会話したり、あるいは休息を取ったりといった、これまでにない車内での過ごし方が可能になります。
これらの技術は、自動車産業における価値の源泉が、従来のエンジンや車体といったハードウェアから、それを制御するソフトウェアやシステムへと移行していることを明確に示しています。そしてその変革を主導しているのは、完成車メーカーだけでなく、高度な技術を持つTier 1サプライヤーであることにも注目すべきでしょう。
商用車分野に見る物流の未来像
Japan Mobility Show 2025で示される最もラディカルかつ短期的に実現可能なイノベーションは、乗用車ではなく商用車のセクターに見られます。ここでの技術革新は、深刻化する社会課題への直接的な回答であり、明確な経済合理性に基づいています。
いすゞのVertical Core Cycle Concept(VCCC)は、ショー全体でも屈指の先進的コンセプトと言えます。トラックの基本骨格であるシャシーを水平から垂直に配置するという発想の転換により、荷台の多様性を飛躍的に高めます。従来のトラックは水平方向のフレームに荷台を載せる構造でしたが、垂直方向の中央フレームにすることで、荷台の形状や機能を用途に応じて柔軟に変更できるようになります。
さらに主要部品をモジュール化し、循環利用することを前提とした設計は、車両のライフサイクル全体での効率化とサステナビリティを追求するものです。特定の部品が故障したり性能が低下したりした場合、その部品だけを交換して再利用するサーキュラーエコノミーの考え方を、トラックという大型車両に適用した先進的な取り組みと言えます。これは未来の物流システムのあり方を根本から問い直すコンセプトです。
三菱ふそうのCOBODI(Connected Load Body)は、電気小型トラック「eCanter」に搭載されるスマート化された荷台とAIによる配送計画システムを連携させた統合ソリューションです。これはドライバー不足とEC市場の拡大という二つの課題が交差するラストワンマイル配送の効率化に焦点を当てた、極めて実践的な提案です。荷台がIoT化され、荷物の積載状況や配送ルートの最適化がリアルタイムで行われることで、配送効率が大幅に向上します。
これらの展示が示すのは、商用車がもはや単なる荷物を運ぶ道具ではなく、データとAIで最適化された高度な物流システムの一部へと進化しつつあるという事実です。物流業界のデジタルトランスフォーメーションは、Japan Mobility Show 2025において最も具体的で実用的な形で示されることでしょう。
社会課題解決に向けたモビリティの役割
自動車産業は、Japan Mobility Show 2025を通じて、社会が直面する課題に積極的に関与する姿勢を鮮明にしています。モビリティは単なる移動手段ではなく、社会問題を解決するためのツールとしての役割を担い始めています。
日野のポンチョドットは、過疎化が進む地方における移動手段の確保という、日本特有の深刻な問題に対する直接的な処方箋です。このコンセプトカーは、乗客輸送と荷物配送の機能を一台に集約し、将来的には自動運転技術を組み合わせることで、持続可能な地域交通のモデルを提示しています。地方では公共交通機関の路線廃止が相次ぎ、高齢者を中心に移動困難者が増加しています。人口密度が低い地域では、従来型の路線バスやタクシーサービスを維持することは経済的に困難ですが、人とモノの輸送を統合することで事業の採算性を向上させることができます。
ダイハツの福祉への注力も見逃せません。車いすのまま乗降できる車両や、歩行を補助するe-SNEAKERといった製品群は、高齢者や移動に制約のある人々の自由な移動を確保するという、社会的意義の大きい分野への取り組みを示しています。これは超高齢社会において全ての人が移動の自由を享受できる社会を目指すという、企業の社会的責任と事業戦略が融合した好例です。移動の自由を確保することは、生活の質を維持し、社会参加を促進する上で極めて重要です。
次世代へのエンゲージメントも重要な戦略です。子供向けの職業体験プログラムOut of KidZania in JMS 2025や、家族で楽しめるコンテンツの充実は、単なる集客策ではありません。これは次世代の消費者、そして将来のエンジニアやデザイナーとなる子供たちにモビリティへの関心を持たせ、産業の長期的な文化的基盤を育むための戦略的投資と言えます。子供たちがクルマやモビリティに興味を持つことは、産業の持続的な発展にとって不可欠な要素です。
スタートアップとの共創が生み出す新たな価値
Startup Future Factoryは、巨大な伝統産業が外部のイノベーションを取り込み、自己変革を加速させるための重要なメカニズムです。ブース出展、ピッチコンテスト、アワードといったプログラムを通じて、完成車メーカーや大手サプライヤーが、AI、IoT、新たなビジネスモデルといった分野で最先端のアイデアを持つスタートアップと協業する機会を創出します。
大企業は豊富な資金力や製造能力、販売ネットワークを持つ一方で、組織の硬直化や意思決定の遅さといった課題を抱えがちです。一方スタートアップは、柔軟な発想と迅速な行動力を持ちますが、事業の拡大に必要なリソースが不足しています。この両者が出会い、互いの強みを活かすことで、単独では実現できなかったイノベーションが生まれる可能性があります。
変化の激しい時代において、組織の俊敏性を維持し、破壊的イノベーションの波に乗り遅れないための取り組みは不可欠です。自動車産業は100年以上の歴史を持つ成熟産業ですが、電動化やデジタル化といった変革の波は、異業種からの新規参入を容易にしています。伝統的な自動車メーカーが競争力を維持するためには、外部の新しい技術やアイデアを積極的に取り込むオープンイノベーションの姿勢が欠かせません。
マルチパスウェイ戦略の本質と意義
Japan Mobility Show 2025を総括すると、マルチパスウェイは単なる技術的選択肢の提示ではなく、日本の自動車産業全体が共有する国家的な産業戦略であることが明確になります。これは単一の技術に未来を賭けることのリスクを回避し、エンジンやハイブリッド技術といった自国が持つ既存の産業基盤と技術的優位性を最大限に活用するための、計算された戦略的ヘッジと言えます。
世界のエネルギー事情を見渡せば、その多様性は明らかです。再生可能エネルギーが豊富な地域もあれば、化石燃料に依存せざるを得ない地域もあります。また充電インフラの整備状況も国や地域によって大きく異なります。このような状況下で、バッテリーEV一本に絞ることは、特定の市場や用途では最適解とならない可能性があります。
日本の自動車メーカーは、ハイブリッド車の開発で世界をリードしてきた実績があり、内燃機関の高効率化においても高い技術力を持っています。これらの技術資産を活用しながら、水素や合成燃料といった新たなカーボンニュートラル燃料への対応を進めることで、多様な市場ニーズに応えることができます。マルチパスウェイ戦略は、技術的な柔軟性を保ちながら、各地域の事情に最適なソリューションを提供するという、極めて実践的なアプローチなのです。
中国や欧米の多くのプレイヤーが推進するバッテリーEVへの一本化戦略とは明確な対照をなし、今後10年間のグローバルな競争において、この思想的対立が主要なテーマとなることは間違いありません。どちらのアプローチが正しいかは、時間が証明することになるでしょう。
ソフトウェアが価値を定義する時代の到来
Japan Mobility Show 2025は、ソフトウェア・デファインド・ビークル(SDV)が未来のコンセプトから現在の技術的現実へと移行する転換点として記憶されるイベントになると考えられます。ステア・バイ・ワイヤのような基盤技術の市販化は、その象徴です。
このパラダイムシフトは、自動車産業のバリューチェーンを根底から覆します。価値の源泉はハードウェアの製造から、ソフトウェア開発、データ管理、そしてユーザーエクスペリエンスのデザインへと移行しています。スマートフォンが単なる通話機器からアプリケーションプラットフォームへと進化したように、自動車もまた、ソフトウェアによって機能や性能が定義される時代に突入しています。
この変化は、従来の自動車産業の競争ルールを大きく変える可能性があります。ハードウェアの製造技術や品質管理において圧倒的な優位性を持っていた日本の自動車メーカーが、ソフトウェア開発のスピードや柔軟性において、IT企業やテスラのような新興メーカーに対抗できるかが、今後の盛衰を分ける最大の課題となるでしょう。
ソフトウェアの世界では、継続的なアップデートによって製品の価値を高め続けることが可能です。購入後もOTA(Over-The-Air)アップデートにより新機能が追加されたり、性能が向上したりするという体験は、従来の自動車にはなかったものです。この新しい価値提供の形に、日本の自動車産業がどう適応していくかが注目されます。
Japan Mobility Show 2025が示す未来への羅針盤
Japan Mobility Show 2025は、日本の自動車産業が未来に向けて自信に満ちた意思表示を行う場です。その強みは、長年培ってきた高度なエンジニアリング能力、圧倒的な製造品質、そして社会課題の解決を視野に入れた独自のモビリティ哲学にあります。
数多くのワールドプレミアが予定され、日本の産業界が一致して戦略的方向性を示す場として、Japan Mobility Show 2025は世界のモビリティ業界に大きな影響を与えることでしょう。ここで発表される技術ロードマップ、特に全固体電池や水素技術の進捗は、各国の投資判断やエネルギー政策、そして脱炭素化へのアプローチに関する国際的な議論の方向性を左右する可能性があります。
もはやJapan Mobility Showは、単なる国内の見本市ではなく、世界のモビリティの未来を形作るグローバルなプラットフォームとしての役割を担っています。トヨタ、日産、Honda、ヤマハといった日本を代表するメーカーから、BYDやメルセデス・ベンツといった海外勢まで、世界中の主要プレイヤーが東京に集結し、それぞれのビジョンを提示します。
一方で、日本の自動車産業が直面する挑戦も明確です。それはソフトウェア開発のスピードと文化にいかに適応していくかという課題に集約されます。ハードウェアの開発サイクルとソフトウェアの開発サイクルは根本的に異なり、組織文化や人材育成の面でも大きな転換が求められています。
マルチパスウェイという独自の航路を選択した日本のモビリティ産業。その航海の先にどのような未来が待っているのか、Japan Mobility Show 2025はその一端を明らかにしてくれるでしょう。電動化、自動運転、コネクティビティ、そしてシェアリングというCASEの潮流の中で、日本メーカーがどのような独自性を発揮し、グローバル競争を勝ち抜いていくのか。世界が固唾をのんで見守る中、モビリティの未来をめぐる競争の火蓋は、まさに切られようとしています。

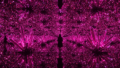

コメント