2025年10月、東京ビッグサイトで開催されるJapan Mobility Show 2025は、日本における電気自動車の未来を体感できる最大級のイベントとして世界中から注目を集めています。今回のモビリティショーでは、国内外の主要自動車メーカーが次々と新型EVを発表し、充電時間の劇的な短縮や航続距離の大幅な延長など、これまでの課題を解決する革新的な技術が披露されました。電動化の波は、スーパースポーツカーから軽自動車、商用車に至るまで、あらゆるセグメントに広がっており、2025年は電気自動車元年とも呼べる転換点を迎えています。全固体電池をはじめとする次世代バッテリー技術の実用化が視野に入り、自動運転やAI技術との融合により、モビリティの概念そのものが大きく変わろうとしています。さらに、カーボンニュートラルという世界的な目標達成に向けて、電気自動車が果たす役割はますます重要性を増しており、Japan Mobility Show 2025で発表された数々の新型EVは、持続可能な社会への道筋を具体的に示すものとなっています。

- Japan Mobility Show 2025の開催概要と注目ポイント
- 日産自動車が発表した新型EV・新型エルグランドとアリアの進化
- ホンダの次世代EV・Honda 0シリーズと多様なモビリティ展示
- トヨタの革新的次世代バッテリーEVと充電技術の飛躍
- BYDの大規模展示・スーパースポーツから軽EVまで
- スバルの電動化戦略・STIとWildernessブランドの展開
- 三菱・ヒョンデ・ダイハツの電動化への挑戦
- 電気自動車技術の進化・充電・航続距離・V2L技術
- プラグインハイブリッド技術・e-POWERとDM-iシステム
- 充電インフラの整備状況と2025年の展望
- 全固体電池の最新動向と実用化への道筋
- 自動運転とAI技術の進化・協調運転ネットワークの構築
- カーボンニュートラルと電気自動車の役割
- 軽自動車のEV化と日本市場の特殊性
- 商用車の電動化と物流業界の変革
- グローバル市場への展開と各地域の戦略
- Japan Mobility Show 2025が示す未来のモビリティ社会
Japan Mobility Show 2025の開催概要と注目ポイント
Japan Mobility Show 2025は、2025年10月30日から11月9日までの11日間、東京ビッグサイト(東京国際展示場)で開催される日本最大級のモビリティイベントです。プレス向けには10月29日から30日に先行公開され、業界関係者や報道陣に向けて最新の電気自動車や次世代モビリティ技術が披露されました。今年のテーマである「ワクワクする未来を、探しに行こう!」には、単なる移動手段としての自動車を超えて、新しいライフスタイルや社会の在り方を提案するという強い意志が込められています。
前回の東京モーターショーから名称が変更されたJapan Mobility Showは、自動車だけでなく、二輪車、電動バイク、ドローン、さらには宇宙ロケットまで、あらゆるモビリティを包括的に展示する場として進化しました。この変化は、モビリティ産業全体が電動化とデジタル化によって大きく変革していることを象徴しています。特に電気自動車分野では、技術革新のスピードが加速しており、各メーカーが競って次世代技術を投入する舞台となっています。
会場では、国内外の主要自動車メーカーが最新の電気自動車を展示し、トヨタ、ホンダ、日産、スバル、三菱といった国内メーカーから、BYD、ヒョンデ(Hyundai)などの海外メーカーまで、多彩なラインナップが揃いました。それぞれのメーカーが独自の電動化戦略を打ち出し、コンセプトカーから市販予定モデルまで、幅広い展示が行われています。
日産自動車が発表した新型EV・新型エルグランドとアリアの進化
日産自動車は、Japan Mobility Show 2025において、複数の新型車両と先進技術を披露し、大きな注目を集めました。最大の目玉は、10月29日のプレス公開日に世界初公開された新型「エルグランド」です。この新型エルグランドは、2026年度に発売が予定されており、第3世代となるe-POWERシステムを搭載することが発表されました。
e-POWERは、エンジンで発電した電力でモーターを駆動する日産独自のハイブリッドシステムで、電気自動車のような静粛性とスムーズな走行性能を実現しながら、充電インフラの心配がないという大きなメリットを持っています。新型エルグランドは、威風堂々としたデザインが特徴で、日産のフラッグシップミニバンとしての存在感を際立たせています。ファミリー層を中心に高い人気を誇るミニバン市場において、電動化技術を取り入れた新型エルグランドは、環境性能と実用性を両立させた重要なモデルとなります。
また、電気自動車「アリア」のマイナーチェンジモデルも展示されました。2025年度に発売予定のこのモデルでは、フロントデザインが一新され、より洗練された外観となっています。さらに、Google連携のインフォテインメントシステムが搭載され、スマートフォンとのシームレスな連携が可能になります。音声操作やナビゲーション機能の向上により、運転中の利便性が大幅に向上することが期待されています。
特筆すべきは、V2L(Vehicle to Load)機能が追加された点です。この機能により、車両から外部機器への電力供給が可能になり、災害時の非常用電源としての活用や、アウトドアでの電力利用など、電気自動車の新たな価値が提供されます。日本は地震や台風などの自然災害が多い国であるため、V2L機能を持つ電気自動車は、単なる移動手段を超えて、防災設備としての役割も果たすことになります。
さらに、日産はグローバル市場向けの電気自動車も展示しました。中国市場向けのEV「N7」や、欧州市場向けの新型電気自動車「Micra」は、日産のグローバルな電動化戦略を示す重要なモデルです。各地域の規制やニーズに合わせた電動化戦略を展開することで、世界市場での競争力を高めようとしています。
ホンダの次世代EV・Honda 0シリーズと多様なモビリティ展示
ホンダは、Japan Mobility Show 2025において、陸海空のモビリティから宇宙ロケットまで、幅広い展示で来場者を驚かせました。特に注目されたのは、次世代EV「Honda 0(ゼロ)」シリーズの進化版です。0シリーズサルーンプロトタイプと0 SUVプロトタイプが展示され、これらのモデルにはAI駆動支援機能や自動駐車機能が搭載されています。
都市型EVとしての利便性が大幅に向上したHonda 0シリーズは、ホンダの電動化戦略の中核を担う重要なプロジェクトです。特に、AIを活用した運転支援機能は、駐車スペースが限られた都市部において大きなメリットをもたらします。自動駐車機能により、狭いスペースでもストレスなく駐車できるため、運転に不慣れな方や高齢者にとっても使いやすい電気自動車となっています。
さらに、日本、イギリス、アジア市場向けに開発された小型四輪EVプロトタイプも世界初公開されました。このモデルは、都市部での使い勝手を重視した設計となっており、コンパクトなボディサイズと十分な航続距離を両立させています。狭い日本の道路事情に適したサイズ感でありながら、実用的な航続距離を確保することで、日常使いに最適な電気自動車を目指しています。
軽自動車規格のEV「N-ONE e:」も展示されました。軽自動車のEV化は、日本国内市場において非常に重要なテーマです。軽自動車は日本の新車販売の約4割を占める重要なセグメントであり、このセグメントでの電気自動車普及が、日本全体のEV普及率向上の鍵となります。普及価格帯での電気自動車の実現が期待されており、補助金制度などと組み合わせることで、多くのユーザーが電気自動車を選択できる環境が整いつつあります。
二輪EV分野でも、ホンダは意欲的な展示を行いました。二輪EVコンセプトモデルとe-MTB(電動マウンテンバイク)プロトタイプが世界初公開され、ホンダが陸上モビリティ全般における電動化を推進していることを示しています。二輪車の電動化は、都市部での短距離移動や配送業務において、騒音や排ガスの削減に大きく貢献します。
さらに驚くべきことに、ホンダは自動車だけでなく、宇宙ロケットまで展示し、モビリティの可能性を宇宙にまで広げる姿勢を示しました。この展示は、ホンダが単なる自動車メーカーではなく、あらゆる移動手段を追求する総合モビリティ企業へと進化していることを象徴しています。
トヨタの革新的次世代バッテリーEVと充電技術の飛躍
トヨタ自動車は、Japan Mobility Show 2025において、次世代バッテリー技術を搭載したコンセプトカーを中心に展示を行い、電気自動車の未来を大きく変える可能性のある技術を披露しました。最大の注目は、「次世代バッテリーEV Concept-α」です。
このコンセプトカーには、わずか10分の充電で800キロメートルの航続距離を実現する次世代セルが搭載されています。現在の電気自動車の課題である充電時間と航続距離を大幅に改善する技術として、業界からも大きな注目を集めています。従来の電気自動車では、満充電まで30分から1時間程度かかることが一般的でしたが、10分という短時間で800キロメートルもの走行が可能になれば、ガソリン車の給油とほぼ同等の利便性が実現します。
この技術が実用化されれば、電気自動車の利便性は大幅に向上し、ガソリン車からの乗り換えが加速すると期待されています。長距離ドライブでも充電の心配がなくなり、高速道路のサービスエリアでの短い休憩時間に充電を完了できるようになります。これは、電気自動車普及における最大のボトルネックを解消する画期的な技術革新といえるでしょう。
トヨタは、全固体電池の研究開発においても世界をリードしており、2027年から2028年にかけて、年間5万台から6万台分の規模で全固体電池の製造を始める計画を立てています。出光興産との共同開発により、硫化リチウムの大型製造装置の建設も進められており、量産化に向けた準備が着々と進んでいます。
また、都市部での移動に特化した小型EV「Compact e-Mover」も披露されました。コンパクトなサイズと優れた取り回し性能により、都市部での日常使用に最適化されています。狭い路地や限られた駐車スペースでも快適に使用できる設計となっており、都市型ライフスタイルに適した電気自動車として注目されています。
BYDの大規模展示・スーパースポーツから軽EVまで
中国の電気自動車メーカーBYDは、Japan Mobility Show 2025に大規模な展示を行い、日本市場への本格参入の意気込みを示しました。乗用車部門では、ワールドプレミア1台とジャパンプレミア3台を含む計8台を展示し、圧倒的な存在感を見せつけました。
最大の注目は、BYDのプレミアムブランド「仰望(YANGWANG)」から発表されたスーパースポーツカー「YANGWANG U9」の日本初公開です。このモデルは、電気自動車世界最速となる時速496.22キロメートルを記録しており、電気自動車の性能の高さを示す象徴的なモデルとなっています。電気モーターの瞬時のトルク発生特性を最大限に活かした加速性能は、従来のガソリンスーパーカーをも凌駕するものです。
プラグインハイブリッド(PHEV)モデル「SEALION 6 DM-i」もジャパンプレミアとなりました。このモデルには、BYDが2008年から量産してきた技術が投入されており、1.5リッターの自然吸気エンジンと高効率バッテリー、電気モーターを組み合わせたDM-iシステムが搭載されています。このシステムは、エンジンとモーターを最適に組み合わせることで、優れた燃費性能と走行性能を両立させています。
上海モーターショーで公開された改良版「BYD ATTO 3」も、国内販売に先駆けてデビューしました。現行モデルは日本国内で既に2500台以上の販売実績があり、BYDの日本市場での存在感を示しています。手頃な価格設定と十分な性能により、電気自動車初心者にも選ばれやすいモデルとなっています。
特筆すべきは、BYDが日本市場向けの軽規格EVを初披露したことです。これは、日本の独自規格である軽自動車市場への本格参入を示すもので、国内メーカーにとっても大きな競合となる可能性があります。BYDの技術力と価格競争力が軽自動車市場に投入されることで、市場全体の活性化と電気自動車の普及促進が期待されます。
商用車部門でも、BYDは意欲的な展示を行いました。ワールドプレミア2台とジャパンプレミア1台を含む計5台を展示し、「T35」シリーズとして、アルミバン仕様と平ボディ仕様が世界初公開されました。配送トラックやバンの電動化は、都市部の大気汚染削減や騒音低減に大きく貢献するとともに、運用コストの削減にもつながるため、事業者にとってもメリットが大きいです。
スバルの電動化戦略・STIとWildernessブランドの展開
スバルは、Japan Mobility Show 2025において、「Stand out the brand」をテーマに、パフォーマンスとアドベンチャーの両面を強調した展示を行いました。計6台のモデルが展示され、スバルブランドの多様性と電動化への取り組みが示されました。
トヨタと共同開発した2台目のEV「トレイルシーカー(Trailseeker EV)」の日本仕様が初公開されました。このモデルは、スバルらしいSUVスタイルと電動化技術を融合させたもので、アドベンチャー志向のユーザーをターゲットとしています。スバルの特徴である水平対向エンジンやシンメトリカルAWDの技術思想を、電気自動車にどのように継承していくかという挑戦の成果が示されています。
最大の注目は、STIブランドから発表された「Performance-E STI Concept」の世界初公開です。これは、スバルのパフォーマンスセグメントの将来を体現する電動モデルで、スバリストと呼ばれる熱狂的なファンにとって大きな注目点となっています。STIブランドから2台の高性能コンセプトモデルが出展されることも発表されており、電動化時代におけるスポーツドライビングの新しい形が提案されています。
電気モーターの瞬時のトルク発生特性を活かした、新しいスポーツドライビング体験が期待されています。従来のエンジン車では得られなかった、滑らかで力強い加速感と、低重心による優れたハンドリング性能の組み合わせは、電気自動車ならではの魅力となります。
アドベンチャー志向の「Wilderness」モデルとして、「Forester Wilderness」プロトタイプと「Outback Wilderness」プロトタイプが展示されました。これらは、オフロード性能を強化したモデルで、スバルのSUVラインナップの多様性を示しています。電動化技術とオフロード性能の組み合わせにより、環境に配慮しながら自然を楽しむライフスタイルを提案します。
Wildernessシリーズは、より高い最低地上高、専用のサスペンションセッティング、オフロード走行に適したタイヤなどを装備し、本格的なアウトドアアクティビティに対応します。電気自動車の静粛性は、自然の中での移動において、野生動物への影響を最小限に抑えるというメリットもあります。
三菱・ヒョンデ・ダイハツの電動化への挑戦
三菱自動車は、10月15日に出展概要を公開し、世界初披露となる電動クロスオーバーSUVのコンセプトカーが最大の注目点となりました。三菱は、アウトランダーPHEVなどでプラグインハイブリッド技術を磨いてきましたが、今回のコンセプトカーでは純粋な電気自動車としてのビジョンを示すと見られています。SUVセグメントでの電動化は、三菱の戦略の中核を成すものであり、今後の市販モデルにつながる重要な方向性が示されています。
韓国のヒョンデ(Hyundai)は、Japan Mobility Show 2025に初出展しました。水素燃料電池車「The all-new NEXO」が日本初公開され、水素エネルギーを活用した次世代環境車の可能性が示されました。NEXOは、水素を燃料とする燃料電池車で、充填時間が短く航続距離が長いという特徴を持ちます。水素社会の実現に向けた重要なモデルとして位置づけられています。
電気自動車「IONIQ 5」も展示されました。IONIQ 5は、ヒョンデのEV専用プラットフォーム「E-GMP」を採用したモデルで、優れた航続距離と急速充電性能を誇ります。800V高電圧システムにより、わずか18分で10%から80%までの充電が可能という、業界トップクラスの充電性能を実現しています。
コンパクトEV「INSTER Cross」も展示され、INSTERのデザインコンセプトカーも公開されました。ヒョンデは、3つのテーマで未来のモビリティを紹介し、電気自動車から水素燃料電池車まで、幅広い電動化ソリューションを提案しています。
ダイハツは、モノづくりとコトづくりの原点に回帰したコンセプトを提示しました。コンセプトカー「ミゼットX」が初披露され、大きな注目を集めました。ミゼットは、ダイハツの歴史的な小型商用車で、その名を冠した四輪の小型モビリティとなります。エンジンルームがないことから、電気自動車である可能性が高いと見られています。レトロモダンなデザインと実用性を兼ね備えたモデルとして注目されており、都市部での配送業務や個人事業主の足として活躍することが期待されています。
電気自動車技術の進化・充電・航続距離・V2L技術
Japan Mobility Show 2025では、電気自動車の技術的進化が顕著に表れています。特に、充電技術の革新、航続距離の延長、V2L・V2H技術の普及という3つの分野で、大きな進歩が見られました。
充電技術に関しては、トヨタの次世代バッテリーに代表されるように、充電時間の大幅な短縮が実現されつつあります。10分で800キロメートルという性能は、従来のガソリン車の給油時間と遜色なく、電気自動車の最大のネックとされていた充電時間の問題を解決する可能性があります。また、高速道路のサービスエリアでは、90キロワット以上の高出力充電器の設置が進められており、一部では150キロワットの充電器も導入されています。
航続距離に関しても、バッテリー技術の進化により、1回の充電での走行距離が大幅に伸びています。800キロメートル以上の航続距離があれば、東京から広島までの距離を充電なしで走行できる計算となり、長距離ドライブでも安心して利用できます。冬場のバッテリー性能低下やエアコン使用による航続距離の減少を考慮しても、実用上十分な性能が確保されています。
V2L(Vehicle to Load)・V2H(Vehicle to Home)技術の普及も注目されています。日産アリアに搭載されるV2L機能のように、車両から外部への電力供給機能が標準装備されつつあります。これにより、電気自動車は単なる移動手段ではなく、災害時の非常用電源やアウトドアでの電源として活用できます。
日本は地震、台風、豪雨などの自然災害が多い国であり、停電時の電源確保は重要な課題です。電気自動車のバッテリー容量は一般的に40kWhから80kWh程度あり、これは一般家庭の数日分の電力使用量に相当します。V2H機能により、停電時でも家庭の電力をまかなうことができ、冷蔵庫や照明、スマートフォンの充電などを継続できます。
さらに、V2G(Vehicle to Grid)技術により、電気自動車が電力系統の調整役を担うことで、再生可能エネルギーの効率的な利用が可能になります。太陽光発電の余剰電力を電気自動車に蓄え、需要の高い時間帯に放出することで、電力系統全体の安定化に貢献します。
プラグインハイブリッド技術・e-POWERとDM-iシステム
純粋な電気自動車だけでなく、プラグインハイブリッド(PHEV)やe-POWERのような電動化技術も、Japan Mobility Show 2025で注目されました。これらの技術は、完全な電気自動車への移行期における重要な選択肢として位置づけられています。
日産のe-POWERシステムは、新型エルグランドに搭載予定の第3世代へと進化しています。e-POWERは、エンジンは発電のみに使用し、駆動は完全に電気モーターで行うという独特のシステムです。これにより、電気自動車のような静粛性と滑らかな加速を実現しながら、充電インフラの心配がないという利点があります。
従来のハイブリッドシステムでは、エンジンとモーターの両方が駆動に使用されるため、どうしてもエンジンの振動や騒音が伝わってしまいます。しかし、e-POWERではエンジンは発電機を回すだけなので、最も効率の良い回転数で運転でき、振動も最小限に抑えられます。運転感覚は完全に電気自動車と同じでありながら、ガソリンを給油すればすぐに走行を続けられるという利便性が魅力です。
BYDのDM-iシステムも、高い注目を集めています。SEALION 6 DM-iに搭載されるこのシステムは、高効率なエンジンとバッテリー、モーターを最適に組み合わせることで、優れた燃費性能と走行性能を両立させています。BYDは2008年からプラグインハイブリッド技術の量産を開始しており、長年の技術蓄積が結実しています。
DM-iシステムの特徴は、1.5リッターの自然吸気エンジンを採用し、アトキンソンサイクルで運転することで、極めて高い熱効率を実現している点です。バッテリー容量も大きく、EV走行距離が100キロメートル以上あるモデルもあり、日常使いでは完全に電気自動車として使用できます。長距離移動時にはエンジンが稼働し、航続距離の心配がなくなります。
充電インフラの整備状況と2025年の展望
電気自動車の普及において、充電インフラの整備は極めて重要な要素です。2024年度末(2025年3月)時点で、日本国内には約68,000基の充電ポートが設置されています。その内訳は、急速充電ポートが約12,000基、普通充電ポートが約56,000基となっています。
2023年度末と比較すると、わずか1年間で約28,000基もの増加があり、急速なインフラ整備が進んでいることがわかります。この増加ペースが継続すれば、日本政府が掲げる2030年までに30万基の充電ポートを設置する目標も、決して夢物語ではありません。この目標は、従来の15万基という目標から倍増したもので、政府の電気自動車普及への強い意志が表れています。
急速充電設備については、高速道路での90キロワット以上への高出力化が進められており、一部では150キロワットの充電器も設置されています。平均出力を現在の40キロワットから80キロワットへ倍増させることを目指しており、これにより充電時間が大幅に短縮され、長距離ドライブでの利便性が向上します。
例えば、40キロワット充電器で30分充電した場合、約20kWh程度の電力が充電され、航続距離は約100キロメートル程度です。これが80キロワット充電器になれば、同じ30分で約40kWh、航続距離約200キロメートルの充電が可能になります。さらに、150キロワット充電器であれば、わずか15分程度で同等の充電が完了します。
一方で、充電インフラには課題も存在します。急速充電設備の設置には多額の初期投資が必要であり、採算性の問題から一部の民間事業者が撤退しているケースもあります。1基の急速充電器を設置するには、機器代、工事費、電力契約の基本料金などを含めると、数百万円から1千万円以上のコストがかかります。
また、2012年頃に設置された充電設備が耐用年数(8~10年)を迎えており、老朽化に伴う不具合が発生しています。これらの設備の更新も重要な課題となっており、単なる新規設置だけでなく、既存設備のリプレースも必要です。
こうした課題に対応するため、政府は大規模な予算を確保しています。2024年度補正予算で3,600億円、2025年度当初予算で1,000億円、合計4,600億円が充電・充填インフラ補助金として確保されています。この予算により、民間事業者の設置費用負担が軽減され、インフラ整備が加速することが期待されています。
さらに、東京都では、新築建築物へのEV充電設備設置を義務付ける全国初の条例が制定され、2025年4月から施行されます。これにより、マンションやオフィスビルなど、これまで充電設備の設置が進みにくかった場所でもインフラが整備されていくことが期待されます。集合住宅での充電環境整備は、電気自動車普及の鍵を握る重要な要素です。
全固体電池の最新動向と実用化への道筋
全固体電池は、次世代のバッテリー技術として大きな期待を集めており、2025年はその実用化に向けた重要な年となっています。全固体電池には、従来のリチウムイオン電池と比較して、大きく4つのメリットがあります。
第一に、液漏れがないため安全性が比較的高いという点です。従来のリチウムイオン電池は液体電解質を使用しているため、破損時に液漏れや発火のリスクがありましたが、全固体電池ではそのリスクが大幅に低減されます。固体電解質を使用することで、バッテリーセルが破損しても危険な液体が漏れ出すことがなく、安全性が大幅に向上します。
第二に、動作温度範囲が広く、特に高温に強いという特徴があります。これにより、過酷な環境下でも安定した性能を発揮できます。真夏の車内は高温になりますが、全固体電池はそのような環境でも性能劣化が少なく、長期間にわたって安定した性能を維持できます。
第三に、充放電が速く、それでいて損失、つまり発熱が少ないという点です。充放電の速さは、5分前後で電気自動車を満充電にできることにつながるため、電気自動車の使い勝手がガソリン車に大きく近づくことが期待されています。ガソリン車の給油時間は通常5分程度ですから、これと同等の時間で充電が完了すれば、ユーザーにとってストレスのない使用が可能になります。
第四に、電極材料の選択自由度が高く、将来的に大幅な高エネルギー密度化を狙えるという点です。これにより、同じバッテリーサイズでより長い航続距離を実現できる可能性があります。現在のリチウムイオン電池では、エネルギー密度の向上が頭打ちになりつつありますが、全固体電池では理論的にさらに高いエネルギー密度が実現可能とされています。
量産化のスケジュールも具体化してきました。トヨタ自動車と出光興産は、2027年から2028年にかけて、EV年間5万台から6万台分の規模で全固体電池の製造を始める計画を立てています。また、2026年の量産を計画するメーカーも複数社出てきており、実用化が着実に近づいています。
2025年2月、出光興産は全固体電池の材料量産に向け、千葉県市原市に中間材料である硫化リチウムの大型製造装置の建設を決定しました。2027年6月までに年産1,000トンの設備を完成する見込みで、これは量産化に向けた大きな一歩となります。硫化リチウムは、固体電解質の主要材料であり、この製造能力の確保が全固体電池の量産化の鍵を握っています。
2025年4月には、ステランティス社がファクトリアル社との共同開発に目途がついたことを発表しました。2026年までに実車への組み込み作業および検証作業を終了させ、同年中に公道での実走テストを開始する予定としています。欧米メーカーも全固体電池の開発を加速させており、世界的な競争が激化しています。
中国でも積極的な動きが見られます。2024年1月には、全固体電池の開発を目的として、電池メーカーのFinDreams Battery、CATL、Gotion High-tech、Svolt Energy Technology、CALB、EVE Energyと、自動車メーカーのBYD、Nioなどが参画するコンソーシアム「中国全固体電池協同創新(CASIP)」が発足しました。
中国メーカーの積極的な参入により、開発競争が激化しており、技術革新のスピードが加速することが期待される一方、日本メーカーにとっては競争が厳しくなっています。日本は全固体電池の基礎研究において世界をリードしてきましたが、量産化では中国や韓国のメーカーに追い上げられており、技術的優位性を保つための努力が必要です。
2025年は、量産化に向けて重要な一歩を踏み出す可能性が出てきた年とされています。2027年から2030年にかけて、さまざまな応用分野で実用化が始まる見込みとなっています。全固体電池が実用化されれば、充電時間が5分程度に短縮され、航続距離も大幅に延長されるため、電気自動車の普及が一気に加速すると予想されます。
自動運転とAI技術の進化・協調運転ネットワークの構築
Japan Mobility Show 2025では、電気自動車と並んで、自動運転技術とAI技術の展示も大きな注目点となっています。自動車業界は現在、100年に一度の大変革期を迎えており、CASE(Connected、Autonomous、Shared、Electric)という概念が、その変革の中心にあります。
KDDIは、遠隔監視システムを備えた自動運転モビリティとAIドローンを展示しました。これらの技術は、コンビニエンスストアを中心とした地域課題の解決を目指しています。過疎地域での買い物支援や、高齢者の移動手段確保など、社会的課題に対するソリューションとして期待されています。
遠隔監視により、完全な無人運転が難しい現段階でも、少人数のオペレーターで複数の車両を管理できるため、運用コストの削減が可能です。1人のオペレーターが同時に5台から10台の車両を監視できれば、人件費を大幅に削減でき、過疎地域でも採算の取れるモビリティサービスが実現できます。
ヤマハ発動機は、AI強化学習技術を活用した「MOTOROiD:Λ(ラムダ)」の第3弾を開発しました。このモデルは、仮想環境で学習し、「Sim2Real」技術により実世界での動作を実現します。AIが独自に思考することで、人間とともに成長・発展していくモビリティシステムを目指しています。
これは、従来の単なる乗り物という概念を超えて、パートナーとしてのモビリティという新しい価値観を提示するものです。AIが乗り手の癖や好みを学習し、最適なサポートを提供することで、人とモビリティの新しい関係性が生まれます。
日産は、AI技術を活用した「AutoDJ」を搭載した実証車両を展示しました。これは、自動運転を基盤とした新しいモビリティサービスで、社会課題の解決を目指しています。AIが運転だけでなく、利用者のニーズや交通状況を判断して最適なルートやサービスを提供することで、より便利で快適な移動体験を実現します。
コネクテッド技術により、車両同士や車両とインフラが5G・6G通信で連携し、自動運転支援AIが実現されています。これらの技術により、事故防止、交通最適化、渋滞緩和を同時に実現する「協調運転ネットワーク」が構築されつつあります。
協調運転ネットワークでは、個々の車両が独立して判断するだけでなく、周囲の車両やインフラと情報を共有することで、より安全で効率的な交通が実現します。例えば、前方で事故が発生した場合、その情報が瞬時に周囲の車両に伝わり、自動的に速度を落としたり、ルートを変更したりすることで、二次災害を防ぐことができます。
AIは単なる運転支援にとどまらず、車両、人、都市を結びつける存在へと進化しています。スマートシティ構想の中で、電気自動車と自動運転技術は、都市全体のエネルギー管理や交通最適化の重要な要素となっています。
カーボンニュートラルと電気自動車の役割
Japan Mobility Show 2025の背景には、カーボンニュートラルという大きな目標があります。日本政府は2050年までにカーボンニュートラルを実現するという目標を掲げており、運輸部門での脱炭素化は重要な柱の一つです。
自動車からのCO2排出量は日本全体の約17パーセントを占めており、この分野での電動化は避けて通れない課題となっています。ガソリン車やディーゼル車を電気自動車に置き換えることで、走行時のCO2排出をゼロにすることができます。
電気自動車は走行時にCO2を排出しないため、再生可能エネルギーで発電された電力を使用すれば、完全なゼロエミッション車両となります。太陽光発電や風力発電の拡大とともに、電気自動車の環境貢献度はさらに高まっていきます。
現在、日本の電力構成では火力発電の割合が高いため、電気自動車を充電する電力も一定のCO2を排出しています。しかし、再生可能エネルギーの比率が高まれば、電気自動車の環境性能はさらに向上します。日本政府は、2030年までに再生可能エネルギーの比率を36%から38%に引き上げる目標を掲げており、この目標が達成されれば、電気自動車のCO2削減効果はより大きくなります。
また、V2G(Vehicle to Grid)技術により、電気自動車が電力系統の調整役を担うことで、再生可能エネルギーの効率的な利用が可能になります。太陽光発電の余剰電力を電気自動車に蓄え、需要の高い時間帯に放出することで、電力系統全体の安定化に貢献します。
再生可能エネルギーは、天候によって発電量が変動するという課題があります。太陽光発電は夜間や曇天時には発電できず、風力発電も風が弱いときには発電量が低下します。電気自動車のバッテリーを蓄電池として活用することで、この変動を吸収し、電力系統全体の安定性を高めることができます。
さらに、電気自動車の製造過程でのCO2排出も減少しつつあります。バッテリー製造工場で再生可能エネルギーを使用したり、リサイクル材料を活用したりすることで、ライフサイクル全体でのCO2排出を削減する取り組みが進められています。
軽自動車のEV化と日本市場の特殊性
日本独自の規格である軽自動車のEV化も、Japan Mobility Show 2025における大きなトレンドです。軽自動車は日本の新車販売の約4割を占める重要なセグメントであり、このセグメントでの電気自動車普及が、日本全体のEV普及率向上の鍵となります。
ホンダの「N-ONE e:」は、軽自動車規格の電気自動車として、日常の足として使いやすい価格帯と性能を目指しています。軽自動車は、通勤や買い物など、短距離移動が主な用途であるため、航続距離が比較的短くても実用上問題ありません。むしろ、バッテリー容量を抑えることで、価格を手頃に設定できるという利点があります。
軽自動車の電気自動車化には、いくつかの利点があります。第一に、軽自動車は市街地での使用が中心であるため、航続距離100キロメートルから150キロメートル程度でも十分に実用的です。第二に、軽自動車ユーザーの多くは自宅に駐車スペースがあるため、自宅充電が可能です。第三に、小型で軽量であるため、バッテリー容量が少なくて済み、コストを抑えられます。
BYDの軽EVの投入も、市場に大きなインパクトを与えると予想されます。海外メーカーであるBYDが軽EV市場に参入することで、競争が激化し、価格低下や性能向上が期待されます。BYDは、中国市場で培った大量生産技術とコスト競争力を武器に、日本市場でも攻勢をかけています。
ダイハツの「ミゼットX」のような小型モビリティも、都市部での移動手段として注目されています。特に、配送業務やラストワンマイル配送において、小型の電気自動車は大きなメリットをもたらします。狭い路地でも取り回しやすく、駐車スペースも小さくて済むため、都市部での物流効率化に貢献します。
軽自動車の電気自動車化を促進するため、政府は補助金制度を整備しています。環境性能に優れた軽自動車の購入に対して、国や自治体から補助金が支給されるため、ユーザーの負担が軽減されます。また、電気自動車は自動車税が優遇されており、ランニングコストも安く抑えられます。
商用車の電動化と物流業界の変革
BYDのT35シリーズに代表されるように、商用車の電動化も着実に進んでいます。配送トラックやバンの電動化は、都市部の大気汚染削減や騒音低減に大きく貢献します。また、運用コストの削減にもつながるため、事業者にとってもメリットが大きいです。
商用車の電動化には、いくつかの重要なメリットがあります。第一に、燃料費の削減です。ガソリンや軽油と比較して、電気料金は大幅に安いため、走行距離が長い商用車では燃料費削減効果が大きくなります。年間数万キロメートルを走行する配送車両では、燃料費だけで年間数十万円から百万円以上の削減が可能です。
第二に、メンテナンスコストの削減です。電気自動車はエンジンがないため、オイル交換やエンジン部品の交換が不要です。ブレーキも回生ブレーキを主に使用するため、ブレーキパッドの摩耗も少なく、メンテナンスの頻度と費用が大幅に削減されます。
第三に、環境規制への対応です。欧州をはじめとする多くの都市で、ディーゼル車の乗り入れ規制が強化されています。将来的には、都市部の配送は電気自動車のみに限定される可能性もあり、今から電動化を進めておくことが重要です。
第四に、企業イメージの向上です。環境に配慮した電気自動車を使用することで、企業の環境意識の高さをアピールでき、ブランドイメージの向上につながります。特に、ESG(環境・社会・ガバナンス)を重視する投資家や消費者からの評価が高まります。
物流業界では、ラストワンマイル配送の電動化が特に注目されています。宅配便や食品配達など、都市部での短距離配送は、電気自動車に最適な用途です。航続距離が比較的短くても問題なく、頻繁に停止・発進を繰り返す配送業務では、電気自動車の回生ブレーキによるエネルギー回収効果が大きくなります。
また、深夜早朝の配送でも、電気自動車は静粛性が高いため、住宅地での騒音問題を軽減できます。都市部での夜間配送規制が緩和される可能性もあり、物流の効率化にもつながります。
グローバル市場への展開と各地域の戦略
Japan Mobility Show 2025では、各メーカーがグローバル市場を意識したモデルを展示しています。電気自動車の普及は世界的な潮流であり、各地域の規制やニーズに合わせた戦略が求められています。
日産は、中国市場向けの「N7」や欧州市場向けの「Micra」を展示し、グローバルな電動化戦略を示しました。中国は世界最大の電気自動車市場であり、政府の強力な支援により急速に普及が進んでいます。中国市場向けのモデルでは、大型のタッチスクリーンやコネクテッド機能など、中国の消費者が重視する装備が充実しています。
欧州市場では、環境規制が非常に厳しく、2035年以降はガソリン車の新車販売が事実上禁止される見込みです。欧州向けモデルでは、長距離走行性能や急速充電性能が重視されます。また、デザインも欧州の消費者の好みに合わせて、洗練されたスタイリングが採用されています。
ホンダの小型四輪EVプロトタイプは、日本、イギリス、アジア市場向けに開発されており、グローバルな電動化を推進しています。各地域の道路事情や使用環境に合わせて、適切なサイズと性能を備えたモデルを投入することで、グローバル市場での競争力を高めています。
BYDは、日本市場への本格参入を図っています。「ATTO 3」で既に実績を上げており、さらに軽EVの投入により、日本市場でのプレゼンスを高めようとしています。BYDは、価格競争力と技術力を武器に、世界中で急速にシェアを拡大しており、2023年には電気自動車販売台数で世界トップとなりました。
アメリカ市場では、大型のSUVやピックアップトラックが人気であり、電気自動車もこれらのセグメントでの展開が重要です。テスラのサイバートラックやフォードのF-150ライトニングなど、大型の電気自動車が次々と投入されています。
新興国市場では、手頃な価格の電気自動車が求められています。インドや東南アジアでは、低価格のコンパクトEVが普及の鍵を握っています。これらの市場では、航続距離や性能よりも、価格の手頃さが最重要視されます。
Japan Mobility Show 2025が示す未来のモビリティ社会
Japan Mobility Show 2025は、電気自動車と次世代モビリティ技術の現在地を確認し、未来を展望する絶好の機会となりました。各自動車メーカーが提示した電気自動車は、技術的な完成度が高まり、実用性も大幅に向上しています。充電時間の短縮、航続距離の延長、多様なラインナップ展開により、あらゆるユーザーのニーズに応えられる段階に達しつつあります。
全固体電池をはじめとする次世代バッテリー技術は、2027年から2030年にかけて実用化が見込まれており、電気自動車の性能はさらに飛躍的に向上します。充電時間が5分程度に短縮され、航続距離が1000キロメートルを超えるようになれば、電気自動車とガソリン車の使い勝手の差はほとんどなくなります。
充電インフラも着実に整備が進んでおり、政府の強力な支援により2030年には30万基という目標達成が現実味を帯びています。高速道路、コンビニ、商業施設、マンションなど、あらゆる場所で充電できる環境が整えば、電気自動車の利便性は格段に向上します。
自動運転とAI技術の進化により、電気自動車は単なる移動手段を超えて、社会課題を解決するプラットフォームへと変貌しつつあります。過疎地域での移動手段確保、高齢者の交通手段提供、物流の効率化など、さまざまな分野で電気自動車と自動運転技術が貢献することが期待されています。
カーボンニュートラルという世界的な目標に向けて、電気自動車は中心的な役割を果たします。再生可能エネルギーと組み合わせることで、真のゼロエミッション社会の実現が可能になります。V2G技術により、電気自動車が電力系統の調整役を担うことで、再生可能エネルギーの変動を吸収し、電力系統全体の安定化に貢献します。
Japan Mobility Show 2025で展示された数々の電気自動車と技術は、私たちが「ワクワクする未来」へと確実に進んでいることを示しています。来場者は、最新のEV技術に触れることで、持続可能で快適な未来のモビリティ社会を具体的にイメージできたはずです。
電気自動車の時代は、もはや遠い未来の話ではなく、今まさに始まっている現実です。2025年は、電気自動車が本格的に普及し始める電気自動車元年として、後世に記憶されることになるでしょう。トヨタの次世代バッテリー技術、ホンダの0シリーズとモビリティの多様化、日産の新型エルグランドとアリアの進化、スバルのSTIとWildernessブランドの展開、三菱の電動SUVコンセプト、ダイハツのミゼットX、そしてBYDやヒョンデといった海外メーカーの積極的な参入など、Japan Mobility Show 2025で発表された新型電気自動車は、それぞれが未来のモビリティ社会を形作る重要なピースとなっています。
電動化は、単なるパワートレインの変更にとどまらず、デザイン、インフォテインメント、エネルギーマネジメント、ライフスタイル全体に影響を及ぼす大きな変革です。電気自動車は、静粛性、スムーズな加速、低重心による優れたハンドリング、低いランニングコストなど、ガソリン車にはない多くの魅力を持っています。
さらに、スマートフォンとの高度な連携、AI運転支援、自動駐車、V2H・V2Gによるエネルギーマネジメント、遠隔アップデートによる機能追加など、デジタル技術との融合により、電気自動車は常に進化し続ける存在となっています。購入後もソフトウェアアップデートにより新機能が追加され、常に最新の状態を保つことができるのは、従来のガソリン車にはない大きなメリットです。
Japan Mobility Show 2025は、そうした未来の姿を具体的に体験できる貴重な機会となりました。「ワクワクする未来を、探しに行こう」というテーマの通り、来場者は最新の電気自動車技術と未来のモビリティ社会の可能性を存分に体感できたことでしょう。この経験は、多くの人々が電気自動車への関心を高め、実際の購入を検討するきっかけとなるはずです。
持続可能な社会の実現に向けて、電気自動車が果たす役割はますます重要になっています。Japan Mobility Show 2025で発表された新型電気自動車とそれを支える技術革新は、環境と利便性を両立させた、真に魅力的なモビリティの未来を示しています。


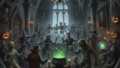
コメント