物価高騰を背景とした診療報酬の引き上げは、医療機関の経営悪化と深刻な人手不足に対応するために行われました。賃上げが進む他産業との格差が拡大し、医療従事者の流出を食い止める必要に迫られたことが最大の理由です。2025年12月の閣僚合意により、2026年度にプラス2.41%、2027年度にプラス3.77%という過去に例を見ない大幅な診療報酬引き上げが決定されています。
この記事では、なぜ今、診療報酬の引き上げが必要とされているのか、その背景にある物価高騰の実態から医療現場の賃上げ問題、さらには政府と医療界の財源を巡る攻防まで、詳しく解説していきます。医療費の仕組みに関心がある方はもちろん、窓口負担の変化が気になる方にとっても、今後の医療制度を理解するうえで欠かせない内容となっています。

診療報酬とは何か――医療サービスの「公定価格」が持つ意味
診療報酬とは、病院やクリニックが患者に医療サービスを提供した際に受け取る対価のことです。この価格は個々の医療機関が自由に決められるものではなく、国が定める「公定価格」として厳格に統制されています。一般の企業であれば、原材料費が上がればその分を商品価格に転嫁することができますが、医療機関にはその選択肢がありません。すべての診察料や検査料、手術料は、中央社会保険医療協議会(中医協)での議論を経て厚生労働大臣が決定し、原則として2年に1回の改定でしか変更されない仕組みになっています。
この公定価格の制度は、患者が安心して医療を受けられる「国民皆保険」の根幹を支えてきました。どの医療機関を受診しても同じ医療行為には同じ料金が適用されるため、経済的な理由で必要な治療を諦めるリスクが抑えられてきたのです。しかし、物価が安定していたデフレ時代には問題にならなかったこの仕組みが、インフレ局面では大きな弱点を露呈することになりました。物価が上昇してもサービスの価格を変えられないという構造は、医療機関にとって「収入は固定されたまま、支出だけが膨らんでいく」状態を生み出すからです。
物価高騰が医療機関の経営を直撃した理由
エネルギーコストと食材費の急騰がもたらした打撃
物価高騰が医療機関に与えた影響は、一般家庭やオフィスとは比較にならない規模に達しました。病院はMRIやCTといった高度医療機器の稼働、手術室の空調管理、入院病棟の24時間体制の維持などにより、莫大な電力を消費する施設です。電気代やガス代の高騰は、病院経営を根幹から揺るがしました。
入院患者に提供される病院給食の問題も深刻です。生鮮食品から加工食品まであらゆる食材の価格が上昇しましたが、病院が患者から受け取ることができる「入院時食事療養費」は公定価格で固定されたままでした。スーパーで食材が値上がりすればレストランはメニュー価格を引き上げますが、病院にはそれができません。食材費の上昇分はすべて病院側の持ち出しとなり、赤字として積み上がっていきました。
さらに、老朽化した病棟の建て替えや最新の医療機器への更新にかかるコストも、建設資材や半導体価格の高騰により大幅に跳ね上がりました。建て替え計画を凍結したり、必要な医療機器の更新を先送りしたりせざるを得ない医療機関が増えており、これは将来的に地域医療の質や安全性の低下につながるリスクをはらんでいます。
赤字が拡大し続ける病院経営の実態
日本医療法人協会や全日本病院協会などが実施した調査結果は、病院経営がいかに厳しい状況に追い込まれているかを如実に示しています。100床から199床規模の中小病院における経常損益率を見ると、2023年度の時点で既にマイナス2.0%という赤字状態にありました。それが2024年度にはマイナス4.4%へと、わずか1年で2.4ポイントも悪化しました。
マイナス4.4%という数字は、病院が1億円の収益を上げてもコストが1億440万円かかり、医療を提供すればするほど440万円の赤字が積み上がることを意味します。稼働100床あたりの医業利益の赤字幅は前年同月比で約241万円も拡大し、経常利益に至っては一月あたり350万円以上も赤字が増加しました。「働けば働くほど貧しくなる」という状態が、多くの病院で現実のものとなっていたのです。
コロナ禍においては、空床確保料などの行政からの補助金がコスト増を覆い隠していました。しかし、感染症法上の位置づけ変更に伴い補助金が縮小・廃止されたことで、物価高騰による経営悪化という「生の傷口」がむき出しになりました。
「医療倒産」が過去最多ペースで増加している現実
経営悪化は単なる会計上の数字にとどまらず、実際の倒産や閉院として顕在化しています。帝国データバンクの調査によれば、2024年から2025年にかけての医療機関の倒産件数は過去最多を更新するペースで推移しました。
特に脆弱なのが、地域医療の最前線を担う診療所やクリニック、歯科医院です。大病院に比べて資本力が弱く、価格転嫁もできないため、物価高や人件費の高騰に対する耐久力がありません。「地域のかかりつけ医」として親しまれてきた診療所が、経済的な理由でやむなく閉院に追い込まれるケースが増えました。倒産の主因は「物価高」と「人件費の高騰」による収益性の悪化であり、これらが複合的に作用して資金繰りを行き詰まらせています。
倒産には至らないまでも、不採算部門を縮小・閉鎖する動きも加速しました。救急医療、産科、小児科といった特に人手とコストがかかる部門がターゲットとなりやすく、地域によっては「救急車を呼んでも搬送先が見つからない」「お産ができる病院がない」といった医療崩壊の兆候が社会問題として浮上しています。
賃上げが進まない医療業界――他産業との深刻な格差
全産業平均の半分以下にとどまる医療従事者の賃上げ率
物価高騰と並んで医療機関を苦しめているのが「人手不足」と「賃上げ圧力」の問題です。2024年の春闘では歴史的な高水準の賃上げが実現し、大企業を中心に初任給の引き上げや大幅なベースアップが相次ぎました。日本経済全体が「賃金と物価の好循環」を目指して動き出した中で、医療業界はこの流れに完全に取り残されました。
全国保険医団体連合会などの調査によると、2024年度および2025年度の2年間における医療従事者の賃上げ率はわずか3.4%にとどまりました。これに対し、全産業の平均賃上げ率は7.3%に達しています。この格差は、医療現場で働く人々に対して「命を預かる尊い仕事であっても、給料の伸びは一般企業の半分以下」という厳しい現実を突きつけるものです。
その結果として、看護師や事務職員、コメディカル(医療技術者)が、より待遇の良い他産業へと流出する動きが加速しました。特に医療事務や介護補助といった職種は、他産業の事務職やサービス職との代替性が高く、賃金格差が直接的な人材流出につながりやすい傾向にあります。
「価格転嫁」ができない構造が賃上げを阻む
医療機関の経営者が従業員の賃金を上げたくないわけではありません。慢性的な人手不足の中で、賃上げをして人材を確保したいという切実な願いを持っています。しかし、それを実現できない構造的な理由が存在します。
飲食店や美容室であれば、原材料費や人件費が上がればサービス価格を値上げしてコストを消費者に転嫁できます。しかし、医療機関は個々の判断で「来月から診察代を10%値上げします」ということが法律上できません。診療報酬本体が引き上げられない限り、医療機関に入ってくる収入の総枠は増えず、収入が増えない中で無理に賃上げを行えば赤字がさらに拡大し、経営破綻のリスクが高まります。これが医療界における賃上げを阻む最大の構造的ボトルネックです。
2024年度に導入された「ベースアップ評価料」とその限界
政府もこの問題を放置していたわけではありません。2024年度の診療報酬改定において、医療従事者の賃上げを促進するための特例的な仕組みとして「ベースアップ評価料」が新設されました。これは対象職員の給与を上げることを条件に、診療報酬を加算できるという制度です。得られた収益の全額を賃上げに充てることが義務付けられ、賃上げ促進税制との併用も可能とするなど、政府の強い意志が反映された施策でした。
しかし、この制度は現場でいくつかの重大な課題に直面し、期待された効果を十分に発揮できませんでした。
まず目標と現実の乖離という問題があります。政府は「2年間で4.5%」の賃上げ目標を掲げていましたが、実際には3.4%程度にとどまり、目標を1%以上下回りました。制度設計上の計算式と実際の現場で必要な昇給原資との間にズレがあったことや、すべての医療機関がこの制度をフル活用できる体制になかったことが要因です。
次に事務負担の重さです。ベースアップ評価料を算定するためには複雑な「賃金改善計画書」を作成し、地方厚生局に届け出る必要がありました。さらに毎年8月には「賃金改善実績報告書」を提出し、実際に給与が上がったことを詳細に報告しなければなりません。専任の事務スタッフを持たない中小の診療所にとって、この手続きは極めて煩雑であり、制度の利用を躊躇させる大きな要因となりました。
さらに職種間の分断という問題も生じました。当初の制度設計では医師や事務職員はベースアップ評価料の計算対象から外れていたり、評価が限定的でした。チーム医療が基本の現場において、特定の職種だけ給料が上がり隣で働く事務員は据え置きという状況は、職場の士気を低下させ組織内の対立を生むリスクがあります。
2024年度改定が「期待外れ」に終わった経緯
2024年度の診療報酬改定は、6年に一度の「医療・介護・障害福祉」のトリプル改定という大きな節目でした。物価高と賃上げへの対応が最大の焦点でしたが、結果は医療界にとって厳しいものとなりました。
診療報酬の「本体」(技術料など)はプラス0.88%の引き上げとなったものの、その大半は賃上げ対応のベースアップ評価料などに割り当てられました。一方で医薬品の価格である「薬価」などはマイナス改定となり、全体としてのネット改定率はマイナスでした。
この改定結果が2024年度の病院経営悪化に直結しています。コロナ禍で投入されていた補助金が終了したタイミングと重なったことで、病院経営は「補助金という命綱」を外された状態でインフレの荒波に放り出される形となりました。多くの病院団体が「改定の影響で経営が悪化した」と訴えたのは、この改定が物価高騰の実態に追いついていなかったためです。
歴史的転換点となった2026・2027年度の「2段階改定」合意
過去に例を見ない大幅引き上げの決定
2024年度改定の不十分さを受けて、次期改定を待たずに何らかの手を打つべきだという声が医療界だけでなく与党内からも高まりました。そして2025年12月24日、厚生労働大臣と財務大臣の折衝により、2026年度および2027年度の診療報酬改定に関する閣僚合意が決定されました。
合意の核心は、物価・人件費の高騰に対応するため、2026年度にプラス2.41%、2027年度にプラス3.77%という過去に例を見ない大幅な本体引き上げを行うというものです。2年度の平均ではプラス3.09%となり、長年「マイナス改定」や「微増」が続いてきた中で、これは医療界にとって衝撃的な数字でした。
この合意には明確な政策意図が込められています。まず賃上げ目標の大幅な引き上げとして、2026・2027年度にそれぞれ3.2%ずつの賃金引き上げを目指すこととされました。特に処遇が低い看護補助者や事務職員については5.7%という高い目標が設定され、他産業との格差是正を図る姿勢が鮮明に示されています。
次にインフレ対応の制度化です。従来は曖昧だった「物価上昇分」を診療報酬の中に明確に組み込む方針が示されました。「物価対応料」の新設も検討されており、電気代や食材費の高騰を補填する仕組み作りが模索されています。
さらに異例の期中改定として、本来2年に1回の改定を、物価変動が激しい時代に対応するため奇数年の2027年度にも実施するという柔軟な姿勢が示されました。これはデフレ時代の「固定的な公定価格」からインフレ時代の「動的な価格設定」への転換を意味しています。
財源確保のための「痛み分け」――患者負担の増加
この大幅な引き上げは無条件で実現したものではありません。財務省は社会保障費の総額を抑えるという方針を持っており、診療報酬を引き上げるならばどこかで収入を増やすか別の支出を削る必要がありました。
財務省が引き上げに慎重な姿勢を崩さなかった最大の理由は「現役世代の負担限界」です。日本の医療保険制度は主に現役世代が支払う保険料と税金で支えられています。高齢化が進み医療費が膨張し続ける中で、これ以上診療報酬を引き上げれば現役世代の保険料が上がり手取り収入が減少します。財務省の財政制度等審議会は「現役世代の社会保険負担率が上昇しないように抑制努力が必要だ」と繰り返し主張してきました。
そこで今回の合意では「財源確保策」として、国民負担の増加と制度の厳格化がセットで提示されました。その象徴的な施策が「OTC類似薬」の患者負担導入です。OTC類似薬とは、湿布薬や保湿剤、軽度の花粉症薬など、ドラッグストアで処方箋なしに購入できる市販薬と同じ成分・効能を持つ医療用医薬品のことです。これらの薬を病院で処方してもらう場合に「薬剤費の4分の1」を患者が特別に負担する新しい仕組みが導入されることになりました。
加えて、入院時の食費は一食あたり40円の増額、光熱水費は一日あたり60円の増額が決定されました。物価高騰分の一部を患者が直接負担する形であり、診療報酬本体の引き上げ(医療従事者の賃上げ)の原資を確保するための「痛み分け」の構造となっています。
公定価格がインフレに弱い構造的な理由
日本の医療制度がこれほどインフレに弱い根本原因は、医療が公定価格で統制された一種の「計画経済」に近いシステムであることにあります。自由経済市場では需要と供給、そしてコストに応じて価格が柔軟に変動しますが、診療報酬は中医協での議論を経て厚生労働大臣が決定するため、価格変更には長い時間がかかります。
さらに問題なのは、改定の根拠となる実態調査が改定の1年から2年前のデータに基づいていることです。つまり「2年前の物価・コスト」を基準に「今後2年間の価格」を決めるというタイムラグが構造的に組み込まれています。デフレ時代には物価が安定していたためこのタイムラグは大きな問題になりませんでしたが、数ヶ月単位で物価が上昇するインフレ局面では常に「周回遅れ」の価格設定しかできません。その間、医療機関はコスト増分を自己負担し続けることになります。
歴史を振り返ると、日本は1974年の第一次オイルショック時にも同様の危機を経験しています。当時は物価が20%以上も上昇し、医療機関の経営は危機的状況に陥りました。日本医師会を中心とする医療界の働きかけにより、19%という異例の診療報酬引き上げが実現しています。しかし現在は、少子高齢化と膨大な国の借金という当時にはなかった制約があり、19%のような大幅引き上げは財政的に不可能です。そのため、今回の「2段階改定」と「患者負担増」という複合的なパッケージでの対応となりました。
地域医療への影響と今後の展望
このまま対応が遅れた場合に起こりうること
物価高と人手不足に対する有効な手当てが遅れれば、医療崩壊は「地方」と「不採算部門」から静かに進行していきます。最も影響を受けやすいのが救急医療です。24時間の待機体制を維持するには医師や看護師の人件費、照明や空調の光熱費が莫大にかかります。赤字に耐えきれなくなった病院が救急の受け入れを制限し始めれば、地域での「たらい回し」が発生します。
地方の公立・公的病院も深刻な状況にあります。自治体の財政も厳しいため赤字補填が限界に達し、病院の統廃合や病床削減が加速する恐れがあります。これは「医療へのアクセス」という国民の権利が、住む場所によって左右されるリスクを意味しています。
私たちの生活に及ぶ具体的な変化
今回の一連の動きは、私たち国民の生活にも直接的な影響をもたらします。まず窓口負担の増加として、2026年以降、湿布や花粉症薬などの処方薬に対する自己負担が増える見通しです。入院時の食費負担も上がり、「安価な医療」というこれまでの常識が変わりつつあります。
次に医療アクセスの変化です。近所のクリニックが経営難で閉院したり、大病院の紹介状なし受診の定額負担(選定療養費)が引き上げられたりと、医療機関への「かかり方」が変わる可能性があります。
一方で、負担が増える代わりに賃上げによって優秀な医療スタッフが確保されれば、医療の質や安全性は守られます。逆に負担増を拒んで診療報酬を抑制し続ければ、「必要な時に入院できない」「手術待ちが数ヶ月続く」といった事態を招く恐れもあります。
物価高騰、賃上げ、診療報酬という3つのキーワードは、複雑に絡み合いながら私たちの命と健康を守る社会インフラの未来を左右しています。安価で質の高い医療を維持するためには相応のコストが必要になる時代が到来しており、私たち国民もまたこの課題とどう向き合うかを考えていく必要があります。

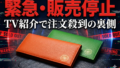
コメント